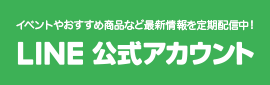【連載】創造する人のためのプレイリスト
2023.10.10
音楽ライター:徳田 満
アナログシンセの名曲・名演・名音 1967~1979年(洋楽編)
クリエイティビティを刺激する音楽を、気鋭の音楽ライターがリレー方式でリコメンドする「創造する人のためのプレイリスト」。今回は、近年その魅力が見直されている「アナログシンセ」を堪能できる1960年代、1970年代の名盤を紹介します。
カバーフォト:fornStudio/Shutterstock.com
2010年代以降、音楽業界ではレコードやカセットテープが人気を博すなど、デジタルからアナログへの回帰が顕著となっている。かつてそれらを聴いていた「アナログ世代」だけでなく、アナログの時代を知らないZ世代にも、アナログのニュアンス豊かで温かみのある音は好評のようだ。
そんな状況下で、同じく復権を果たしたと言えるのが「アナログシンセサイザー」だ。音のクリアさやアタックの強さなどはデジタルシンセに譲るものの、アナログ独特の音の太さや中域のふくよかさなどに加え、メーカーや機種によって音の個性(特徴)が大きく異なる点も魅力。現在では、かつての名機(ビンテージ機種)の復刻のみならず、新しいアナログシンセも続々と発売されている。今回は、そんなアナログシンセのオリジナルが大活躍していた時代から、主に1970年代、ポップ・ミュージックの世界で発表された洋楽作品を紹介してみたい。
1.ペリー&キングスレイ「バロック・ホウダウン」(1967年)
前史としてはいろいろあるようだが、楽器として完成したシンセサイザーは、アメリカの工学博士、ロバート・モーグ(Robert Moog)が開発し、1964年に公表した「モーグ・シンセサイザー(Moog Synthesizer)」が最初だといわれている。その後、モーグ博士とさまざまな音楽家たちの協力により、モーグは機能的にも使いやすさの面でも向上していったが、そのうちの1人がウェンディ(当時はウォルター)・カルロス(Wendy/Walter Carlos)。彼はモーグをフルに使ってバッハの作品をカバーした「スウィッチト・オン・バッハ(Switched-on Bach)」を1968年に発表し、ヒットを収めた。
ここで紹介するのも、やはりモーグを駆使して作り上げ、しかも「スウィッチト・オン・バッハ」より1年早い1967年に発表された作品(アルバム「カレイドスコピック・バイブレイションズ(Kaleidoscopic Vibrations)」に収録)。作者のペリー&キングスレイ(Perrey&Kingsley)は、フランス出身の電子音楽のパイオニア的存在で、「Moog Indigo」という傑作もあるジャン=ジャック・ペリー(Jean-Jacques Perrey)と、ドイツ生まれの作曲家ガーション・キングスレイ(Gershon Kingsley)によるユニットである。
聴いてもらえばすぐわかるのだが、実はこの「バロック・ホウダウン(Baroque Hoedown)」、ディズニーランドの「エレクトリカルパレード」のオープニングテーマ曲として、70年代より使われ続けている。多彩な音の歴史を経てきた現在でも楽しいサウンドに感じられるのだから、当時としては、とびきり未来的でファンタスティックに聞こえたはずだ。
2.エマーソン・レイク・アンド・パーマー「タルカス」(1971年)
1970年代に入っても、楽器として使えるシンセは、当初はモーグしかなかった。それも「モジュラー・シンセサイザー(Modular Synthesizer)」という、のちにYMOのライブで日本人にもおなじみとなるバカでかいタンス状のもので、さまざまなジャンルのアーティストに愛用されてきたが、ロック界でこれを最初に使い倒したのが、エマーソン・レイク・アンド・パーマー(Emerson, Lake and Palmer=ELP)のキース・エマーソン(Keith Emerson)である。
キースは1970年にELPを結成するとすぐにモーグを購入し、デビューアルバムの録音を開始。2曲でモーグを使ったソロを入れているが、本格的に使用するのは、次作の「タルカス(Tarkus)」からである。
このアルバムは、怪物(タルカス)が火山の中から現れ、破壊の限りを尽くして海へ帰っていくという物語を組曲形式でつづった、ELPの代表作のひとつで、20分以上にも及ぶ1曲目(タイトル曲)の1分10秒過ぎあたりから、まさに怪物の咆哮のようなソロが聞こえる。この「ぶっとい音」こそ、モーグの特徴なのである。ほかの曲でも、モーグならではのインパクトのある音が随所に入っており、モーグの音に浸りたいなら、まずはこのアルバム、と言えるほど、アルバム全編を通してモーグが大活躍している。
3.イエス「ヘンリー8世の6人の妻」(1973年)
1970年に、レッド・ツェッペリン(Led Zeppelin)の「レッド・ツェッペリンⅡ(Led Zeppelin Ⅱ)」とともに、ビートルズ(The Beatles)の「アビイ・ロード(Abbey Road)」をチャート1位の座から蹴落としたのが、キング・クリムゾン(King Crimson)の「クリムゾン・キングの宮殿(In The Court Of The Crimson King)」。前述のELPもそうだが、以後、70年代中期まではブームと呼べるほど、プログレッシブ・ロックが隆盛だった。そして、プログレとシンセを語る際に絶対外せないバンドがイエス(Yes)で、そこにキーボード奏者として在籍していたのが、リック・ウェイクマン(Rick Wakeman)である。
リックがイエスに加入したのは1971年で、この年の「こわれもの(Fragile)」、翌年の「危機(Close to the Edge)」といったバンドの代表作に参加している。今回紹介するのは1972年12月のツアーを収めた1973年のライブ盤「イエスソングス(Yessongs)」から、リックのソロ作である「ヘンリー8世の6人の妻(The Six Wives of Henry VIII)」。
この動画を見ていただければおわかりの通り、生ピアノ、エレクトリック・ピアノ、メロトロンなど、さまざまなキーボードによる「城」に囲まれて演奏しているが、3分20秒あたりから弾いているのが、前述のモジュラー版を小型化し使い勝手も改良した「ミニモーグ(Minimoog)」。アナログシンセの特徴であるポルタメント機能*を存分に生かした力強いソロを、実に気持ちよさそうにプレイしている。
* ポルタメント機能:ある音から別の音に移る際に、徐々に音程を変えられる機能。
4.ハービー・ハンコック「レイン・ダンス」(1973年)
大御所ジャズ・ピアニストであるハービー・ハンコック(Herbie Hancock)も、エレクトリック・ジャズ時代に、シンセを駆使したアルバムを残している。よく知られているのが、1973年の「ヘッド・ハンターズ(Head Hunters)」。1曲目の「カメレオン(Chameleon)」は、この前年に発売されたアメリカ・ARP社の「アープ・オデッセイ(ARP Odyssey)」によるシンセ・ベースと、ハーヴィー・メイソン(Harvey Mason)が叩くドラムスの絡みが実にファンキーで、後半のソロもアープである。
今回は、その前作「セクスタント(Sextant)」の冒頭曲「レイン・ダンス(Rain Dance)」を取り上げる。このアルバムは全部で3曲しかないが、「ヘッド・ハンターズ」がエレクトリック・ジャズ・ファンクとして手堅くまとまっているのに対し、本盤はどの曲も基本的にワンコードのアフロ・ファンク的(というか土俗っぽい)自由さと実験精神にあふれている。「レイン・ダンス」にしても、アープで作った雨粒のような音がアルペジオ的に流れ、そこに各プレイヤーが思い思いの即興演奏を乗せるといった作りで、「フリージャズmeetsテクノ・ポップ」といった趣もある。
5.クラフトワーク「アウトバーン」(1974年)
そのテクノ・ポップの元祖、クラフトワーク(Kraftwerk)の名を一躍世界に知らしめたのが、この「アウトバーン(Autobahn)」である。タイトル通り、ドイツ全土を走る高速道路をテーマにした曲で、車のドアが閉まる音、イグニッションキーを差し込みエンジンがかかる音、走行音、車と車のすれ違う音(ドップラー効果含む)、クラクションなど、高速を車で走る際のありとあらゆる音をシンセ(ミニモーグとアープ・オデッセイ、1972年に開発されたイギリス・EMS社のSynthi AKS)で模倣している。
この「模倣」というのがポイントで、現在ならデジタル(サンプリング)でそのままの音を容易に出せるが、それでは意味がない。現実音をシンセで「表現」していることが、この曲の面白さの源で、そのためにはアナログシンセでなければならないのだ。
もう1つ忘れてならないのは、それらの音を、リズムボックスによる一定のリズムに乗せ、音階やビーチボーイズをまねたコーラスまで付けて、「ポップ・ミュージック」として完成させた点。それがなければ、1970年の結成以来、このグループが試みてきた実験的な電子音楽の範疇で終わっていただろう。そして、シンセをただの効果音やリフ・ソロ用の音ではなく、主役(メイン楽器)として使っているのも画期的なことである。
6.タンジェリン・ドリーム「フェードラ」(1974年)
前述のクラフトワークや、シュトックハウゼン(Karlheinz Stockhausen)、カン(CAN)、ノイ!(NEU!)らとともに、ドイツの電子音楽を代表する存在がタンジェリン・ドリーム(Tangerine Dream)である。結成は1968年とクラフトワークより古く、初期は現代音楽に近い実験的な作品をリリースしていたが、4thアルバム「アテム(Atem)」がイギリスで話題となり、ヴァージン・レコードと契約。続く5枚目のアルバムが「フェードラ(Phaedra)」である。
「アテム」も「フェードラ」もドラムス(リズムマシン)やベースのない、シンセのみの作品だが、「アテム」はあくまで静かなアンビエント(環境音楽)という印象。対してこちらの「フェードラ」のタイトル曲は、ミニモーグで作った短いフレーズをミュージック・シーケンサー(コンピュータ)で反復させている(ポップ・ミュージックでコンピュータが使われた最初期のものといわれる)。
しかし、ただミニマルなだけでなく、抑揚や緩急の変化をつけることで「音の一大叙事詩」ともいえる壮大な内容に仕上げており、その幻想的な印象を好むファンからは、タンジェリン・ドリームの最高傑作とも呼ばれている。
7.ピンク・フロイド「クレイジー・ダイアモンド(第1部)」(1975年)
アナログシンセを語る際に、ピンク・フロイド(Pink Floyd)を忘れるわけにはいかない。プログレ・バンドはキーボーディストが音作りの主導権を握ることが多いので、シンセの名盤を取り上げる時にどうしても数が多くなるのだが、ピンク・フロイドの鍵盤奏者、リチャード・ライト(Richard Wright)はほかのプログレ・バンドのキーボーディストとは違い、テクニックを誇示したりソロを弾きたがったりというタイプではなかった。それよりも、コードワークや楽器の音色、音響やアレンジといった部分に関心があったと思われる。
ピンク・フロイドは、2023年に50周年記念リマスター盤がリリースされた最高傑作「狂気(The Dark Side of the Moon)」(1973年)から本格的にシンセを導入。3曲目の「走り回って(On the Run)」で延々と繰り返される機械的なフレーズ(EMS Synthi AKS内蔵のシーケンサーを使用)をはじめ、シンセで作られた「コインの落ちる音」や「心臓の音」などが随所にSE(効果音)的に入り、作品の幻想性を高めている。
ここで紹介するのは、その次作「炎~あなたがここにいてほしい(Wish You Were Here)」の1曲目「クレイジー・ダイアモンド(第1部)(Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5)」。かつてのメンバーであるシド・バレット(Syd Barrett)に捧げたというこの曲では、前奏や曲の中盤で、ミニモーグ特有の味わい深いシンセソロが聴けるが、このフレーズが喜多郎に影響を与えたのではないかと思うのは、筆者だけだろうか。
8.ジャン・ミッシェル・ジャール「躍動」(1976年)
ジャン・ミッシェル・ジャール(Jean-Michel Jarre)は、フランスが世界に誇るシンセサイザー・プレイヤー。「アラビアのロレンス」などで知られる映画音楽の巨匠、モーリス・ジャール(Maurice Jarre)を父親に持つ彼が初めて作ったシンセサイザーのアルバムが、今回紹介する「幻想惑星(Oxygene)」である。
ジャン自身がシンセとの関わりの歴史を語る動画によると、この組曲形式のアルバムで主に使用したのはEMS VCS3(1969年にEMS 社が開発した最初のシンセ)だという。
ただ、聴いた感じでは、(当時のリズムボックスを使っているということもあるが)ここに挙げた「躍動(Oxygene, Part 4)」も含め、「組曲」という言葉からイメージされる重厚さはなく、浮遊感に包まれるような「ショワー」というSEと、わかりやすいメロディーによる軽音楽という印象。聴きやすさという点では、今回紹介した作品の中でも群を抜いている。何よりも1976年の時点で、これだけ整理されたサウンドを提示していたというのは驚きだ。
9.ドナ・サマー「アイ・フィール・ラブ」(1977年)
1970年代も後期になると、ポップ・ミュージックの潮流がかなり変わってきて、メッセージ性のあるロックが影を潜め、産業(商売)としての音楽が主流となってくる。その最前線で活躍したのが、ジョルジオ・モロダー(Giorgio Moroder)である。
彼はプロデューサーや、「フラッシュダンス」「ネバーエンディング・ストーリー」「トップガン」といった映画音楽の作曲家として知られているが、シンセについても70年代初期から使い始めている。それが結実したのが、1977年にプロデュースしたドナ・サマー(Donna Summer)の「アイ・フィール・ラブ(I Feel Love)」。ディスコ・ブームに火をつけたといわれるこの曲は、モーグで作ったベース・ラインがシーケンサーで自動演奏されており、YMO結成のきっかけになるなど、世界のさまざまなアーティストに影響を与えた。そして46年後の現在でも、この曲の斬新さは色褪せていない。
本作の大ヒットを受け、ジョルジオは満を持してソロ・アルバム「永遠の願い(From Here To Eternity)」を同年にリリース。「アイ・フィール・ラブ」で成功したシーケンサー制御によるシンセ・ベースをはじめ、シンセによるSE、ヴォコーダー(人間の声を加工して出力するシンセの一種)なども駆使し、聴きやすくて未来的なディスコ・サウンドに仕上げている。
10.パーラメント「フラッシュ・ライト」(1977年)
ここまで読まれてきた方の中には、なぜスティービー・ワンダー(Stevie Wonder)が登場しないのか、疑問に思われた人もいるかもしれない。確かにスティービーはシンセを使った名曲を残してはいるが、どちらかといえば既存楽器(管楽器など)の代用としてシンセを使っていることが多く、アナログシンセ独自の音を紹介したいと考える本稿では見送ることにした。ただし、シンセ・ベースが活躍する「レゲ・ウーマン(Boogie On Reggae Woman)」などもあるので、興味のある方は聴いてみていただきたい。
さて、ここでは、パーラメント(Parliament)の「フラッシュ・ライト(Flash Light)」を取り上げる。パーラメントは、Pファンク(P-Funk)の「総帥」であるジョージ・クリントン(George Clinton)が結成したバンドで、メンバーにはブーツィー・コリンズ(William "Bootsy" Collins)やフレッド・ウェズリー(Fred Wesley)、バーニー・ウォーレル(Bernie Worrell)など錚々(そうそう)たる顔ぶれがそろう。
中でもこの「フラッシュ・ライト」は、バンド最大のヒットとなった。この曲もシンセ・ベースがキモだが、(おそらく)手弾きによる音の太さとねちっこさ、ポルタメント機能を使ったグリッサンドなど、存在感が半端なく、ワンコードなのにずっと聴いていても飽きさせないほど強靭なグルーヴを生み出している。なお、やはりジョージが作ったファンカデリック(Funkadelic)とはメンバーが重なっていることもあり、そちらでもこの曲がプレイされている。
11.ウェザー・リポート「貴婦人の追跡」(1978年)
ウェザー・リポート(Weather Report)は、1970年にジャズ・ピアニストのジョー・ザヴィヌル(Joe Zawinul)とウェイン・ショーター(Wayne Shorter)を中心として結成されたエレクトリック・ジャズ・バンド。1986年の解散までにかなりメンバーの変動があったが、ジャズファンには広く評価されているバンドであり、シンセ奏者としてのジョーの功績も讃えられている。
正直に告白すると、ウェザー・リポート及びジャズにあまり詳しくない筆者には、今ひとつ、(キーボード・プレイヤーとしてではなく)シンセストとしての彼の偉大さが実感できないのだが(ジャズ界にシンセを広めたという意味ではうなずけるが)、逆にウェザー・リポートのアルバムの中ではあまり評価が高くないらしい「ミスター・ゴーン(Mr. Gone)」を聴いてみると、なかなか面白いと感じた。
本盤はジャコ・パストリアス(Jaco Pastorius)との共同プロデュースで、ジャコ色が強いという批評も見たが、特に1曲目の「貴婦人の追跡(The Pursuit of the Woman with the Feathered Hat)」は、テクノ風のシーケンスで始まり、極太のシンセ・ベースにミニマルなリフと、何重にもシンセ(ARP社のARP2600をはじめ複数機種)を重ねた、エスニック風な曲。ウェザー・リポートの王道路線からはかなり逸脱しているのだろうが、アナログシンセ好きにはとても魅力的なトラックになっている。
12.ビー・バップ・デラックス「電気じかけの言葉」(1978年)
ビー・バップ・デラックス(Be-Bop Deluxe)は、日本ではあまり知られておらず、YouTube公式チャンネルもないのだが、高橋幸宏との交流で知られ、高橋やYMOのアルバムにも参加したビル・ネルソン(Bill Nelson)率いるイギリスのバンドである。
結成は1972年と古いが、以降何度かのメンバーチェンジを経るとともに音楽性も著しく変化。今回紹介する「電気じかけの言葉(Electrical Language)」が収録された「プラスティック幻想(Drastic Plastic)」がラストアルバムとなってしまうのだが、本盤では完全なシンセ・ポップバンドと化している。
ビル自身はヴォーカルとギターを担当しているが、このアルバムではギターを抑え気味にし、ベースも上モノもシンセ(複数機種を使っているようだが詳細不明)を使いまくっている。その結果、80年代前期に黄金時代を迎えるニューウェイブを先取りしたような、明るく華やかなサウンドが完成。改めて、ペリー&キングスレイからわずか10年で、シンセの進化とともに、シンセを使ったサウンドも、これだけ変化していることに驚く。
13.アジ厶ス「フライ・オーバー・ザ・ホライゾン」(1979年)
1970年代は「クロスオーバー」と呼ばれる、ジャンルの垣根を乗り越えた音楽が隆盛だった。そして日本には、その名も「クロスオーバーイレブン」というNHK-FMの番組まであった(レギュラー放送は1978~2001年)。そのオープニングテーマとして流れていたのが、この「フライ・オーバー・ザ・ホライゾン(Fly Over The Horizon)」である。
アジ厶ス(Azymuth)は1973年にリオデジャネイロで結成されたブラジルのバンド。結成当初は常にシンガーを迎えるスタイルで、歌もののボサノバやサンバを得意としており、1975年のデビューアルバムから各メンバーの優れた表現力が遺憾なく発揮されていたが、この曲が収められた1979年のアルバム「ライト・アズ・ア・フェザー(Light As A Feather )」では完全にインストゥルメンタル・バンドとなり、洗練度が格段に上がっている。商業的にも大ヒットし、当時のUKチャートでは8週連続20位以内に入っていたという。
中でもこの曲は、ARP2600による、倍音の豊かな美しいストリングス風の音色が奏でるメロディーとエレピが、心地よい浮遊感を味わわせてくれる。この時期に開発されたばかりのアメリカ・ポラード社製「SYN-DRUMS」(ピューン、ピューンという音を発する電子ドラム)も効果的。数あるアナログシンセの名曲の中でも、間違いなく上位にノミネートされる作品だろう。
14.ブロンディ「ハート・オブ・グラス」(1979年)
最後は、これまで登場してこなかった女性ヴォーカル曲で終わりたいと思う。
ブロンディ(Blondie)は1974年にデボラ・ハリー(Deborah Harry)とクリス・シュタイン(Chris Stein)が中心となって結成したバンド。その後、メンバーチェンジを経て1978年にリリースしたアルバム「恋の平行線(Parallel Lines)」からシングルカットされたのが、「ハート・オブ・グラス(Heart of Glass)」である。デボラの魅力も相まって、アメリカとイギリス両国で1位になるなど、世界中で大ヒットした。
冒頭、軽いジャングル・ビート風のリズム・シーケンスで始まり、エレキ・ベース、ドラムス、ギターが同時に入り、すぐに歌となる典型的なディスコ・サウンド。ただ、スタジオ盤は整理された音だが、同時期に行われたライブの動画を見ると、イントロからアメリカ、オーバーハイム・エレクトロニクス(Oberheim Electronics)社の2-Voice(おそらく)を使った持続音を流しているので、ディスコというよりニューウェイブ色が出ている。
いずれにしても、シンセの使い方としては特に変わったところはないが、見方を変えれば、この10年の間に、シンセサイザーが得体のしれないモノから、普通の楽器として(ミュージシャンにもオーディエンスにも)認知されるようになった、ということかもしれない。
※記事の情報は2023年10月10日時点のものです。
-

【PROFILE】
徳田 満(とくだ・みつる)
昭和映画&音楽愛好家。特に日本のニューウェーブ、ジャズソング、歌謡曲、映画音楽、イージーリスニングなどを好む。古今東西の名曲・迷曲・珍曲を日本語でカバーするバンド「SUKIYAKA」主宰。
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- 日本のポップスを世界がカバーする「逆カバー・バージョン」の歴史 音楽ライター:徳田 満
-

- 日本が世界に誇るテクノポップ、その創作の秘密 音楽ライター:徳田 満
-

- 和田永|役目を終えた家電を楽器に。「祭り性」を追い続けるアーティスト 和田永さん アーティスト/ミュージシャン〈インタビュー〉
NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事
-

- 冬に聴きたい、しっとりココロ潤うクラシック クラシック音楽ファシリテーター:飯田有抄
-

- LEO|箏の可能性を切り拓く新鋭箏奏者。古典と革新の演奏で箏の伝統をつなぐ LEOさん 箏奏者〈インタビュー〉
-

- 「黄金世代」のソングライター特集。1940~1942生まれの美メロメーカーたち ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ
-

- はいだしょうこ|宝塚歌劇団から歌のお姉さんへ。歌が誰かの支えになれるなら、歌い続けたい はいだしょうこさん 歌手〈インタビュー〉