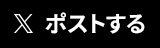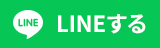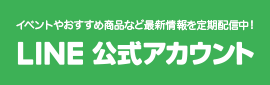【連載】創造する人のためのプレイリスト
2025.02.10
音楽ライター:徳田 満
冬のアンビエント【前編】
クリエイティビティを刺激する音楽を、気鋭の音楽ライターがリレー方式でリコメンドする「創造する人のためのプレイリスト」。今回は、冬の乾いた空気によく馴染む「アンビエント」、環境音楽を紹介します。
カバーフォト:Andreas Tormin/Shutterstock.com
「アンビエント(ambient)」とは環境のことで、音楽で言うアンビエントは「環境音楽」と訳される。このジャンルを提唱し、また第一人者でもある音楽家、ブライアン・イーノ(Brian Eno)は、「興味をそそると同時に無視できる」「落ち着きと思考の空間を誘う」と定義していたが、現在ではその枠は無限に広がり、どんな音楽をアンビエントと捉えるかは聴き手に委ねられている。
今回は、冬の乾いた空気によく馴染む(と筆者が感じた)作品を選んでみた。ぜひ、ヘッドフォンではなくステレオのスピーカーを通して、その音の響きに心も身体も浸してほしい。
〈冬のアンビエント【前編】 目次〉
- ブライアン・イーノ「1/1」
- ペンギン・カフェ・オーケストラ「Penguin Cafe Single(2008 Digital Remaster)」
- アリス・コルトレーン「Shiva-Loka(Live)」
- ラス・ガルシアとその楽団「Into Space」
- ラーキン「Communitizing」
- イエロー・マジック・オーケストラ(Yellow Magic Orchestra)「Nostalgia(Remastered 2020)」
- 坂本龍一「Ieta」
1. ブライアン・イーノ「1/1」(1978年)
まずは、「アンビエント・ミュージック」に馴染みのない人への入り口も兼ねて、ブライアン・イーノの楽曲を。「Ambient」シリーズの第1弾となるアルバム「Ambient 1: Music for Airports」の1曲目だ。このアルバム以前の作風は、普通のバンド編成によるロック。つまり、ここからイーノによるアンビエントの歴史が始まったわけだ。
聴いておわかりのように、ピアノの単音とシンセサイザーだけによる、シンプルな構成なのだが、不思議と心安らぐ響きで、ずっと聴いていたくなる。筆者が初めてこの「Ambient」シリーズ(4まで出ている)を聴いたのは高校生の頃で、当時は少し退屈さを感じていたが、年齢を重ねるごとに心地良さが増してくる。そうしたヒーリング効果にも優れた、のちのニューエイジ(New Age)*1の先駆けでもある作品。
*1 ニューエイジ:宇宙や生命、精神性、潜在能力といった大きな存在とのつながりを強調するインストゥルメンタル音楽のジャンル。
2. ペンギン・カフェ・オーケストラ「Penguin Cafe Single(2008 Digital Remaster)」(1976年)
そのブライアン・イーノが主催するオブスキュア・レコード(Obscure Records)よりデビューしたのが、ペンギン・カフェ・オーケストラ(Penguin Cafe Orchestra)。この「Penguin Cafe Single」(日本盤では「たった一つのペンギン・カフェ」という邦題がついていた)は、デビュー・アルバム「Music From the Penguin Cafe」(邦題「ようこそペンギン・カフェへ」)の1曲目である。
オーケストラといっても、固定メンバーはサイモン・ジェフス(Simon Jeffes)とスティーヴ・ナイ(Steve Nye、1988年まで)だけで、サイモンがギター、ベース、ピアノ、ウクレレといった基本的な楽器とヴォーカルを、スティーヴがミキシング(時にはキーボードも)を担当していた。ペンギン・カフェ・オーケストラのアルバムは作品ごとに少しずつ印象が変わるのだが、こぢんまりとした室内楽的な佇まいのこのファーストが筆者は一番好きで、高校生の頃から現在に至るまで、長年の愛聴盤となっている。
そして、冬のイメージが強いのもこのアルバムだ。理由はよくわからないが、全体のサウンドが少しくぐもっているところや、アコースティックな編成の中でエレクトリック・ピアノが鳴っているような音の感じが、そう思わせるのかもしれない。
3. アリス・コルトレーン「Shiva-Loka(Live)」(2024年)
夫のジョン・コルトレーン(John Coltrane)同様、いやそれ以上のスピリチュアルな音楽性で、没後さらに人気が高まっているアリス・コルトレーン(Alice Coltrane)。彼女のユニークな点は、ピアノやオルガンに加えてハープも演奏するところで、その幻想的な音色がジャズという枠を超え、幅広いファンを獲得している。
ここで紹介するのは、1971年にニューヨークのカーネギー・ホールで演奏したもの。長らく未発表だったが、2024年に「The Carnegie Hall Concert」として商品化された。ハープとウッドベース、サックスが絶妙に絡み合う魅惑の音世界を堪能してほしい。
4. ラス・ガルシアとその楽団「Into Space」(1958年)
まだシンセサイザーもない1950年代に発表されたのが、当時は遠い夢でしかなかった宇宙旅行をテーマとした「Fantastica - Music From Outer Space」。1916年生まれで、映画や舞台演劇のための作曲やアレンジを手がけていた、ラス・ガルシア(Russ Garcia)のリーダー・アルバムだ。
もちろんこの頃にはアンビエントなどという概念はなく、本作も基本はオーケストラによる演奏なのだが、オープニングを飾るこの「Into Space」は、エコーや楽器の鳴らせ方などに工夫を凝らし、まさにスペーシーでドリーミーな音響を聴かせてくれる。
宇宙空間とアンビエントは親和性が高く、世界中でさまざまなアーティストが題材としているが、中でもスティールパン奏者のヤン富田(やん・とみた)による「Music for Astro Age」(1992年)は傑作。また、この「Fantasica」自体も1990年代中期以降、「モンド・ミュージック*2」として再評価されている。
*2 モンド・ミュージック:ムード音楽、イージーリスニングミュージックなど、従来軽視されてきた匿名性の高い音楽の中に、マニアが珍奇さ・エキゾチシズムといった要素を見出し、ジャンルとして命名したもの。
5. ラーキン「Communitizing」(1980年)
アメリカのニューエイジ系レーベル、ナラダ(Narada)の代表的フルート奏者、ラーキン(Larkin)によるソロ5作目で、ゴールド・ディスクに認定されているアルバム「O'cean」の2曲目(といっても全部で2曲しかないが)。全編に流れる波の自然音とフルートの響きが素晴らしい。
筆者の年齢も関係していると思うが、これを聴いているとどうしても、昨年亡くなった西田敏行(にしだ・としゆき)が金田一耕助に扮した映画「悪魔が来りて笛を吹く」(1979年)を連想してしまう。この物語で重要な役割を果たすのがフルートで、劇中では日本のフルート奏者として名高い植村泰一(うえむら・やすかず)が見事な音色を奏でている。興味があれば、併せて聴いてみてほしい。
6. イエロー・マジック・オーケストラ(Yellow Magic Orchestra)「Nostalgia(Remastered 2020)」(1993年)
YMOの作品中、今ひとつ評価が低いのが、1993年にYMOが"再生"された際のアルバム「Technodon」。でも、筆者は発表当時から好きだった。
アルバム・タイトルにもなっている「テクノ」は、この当時(1978〜1983年にYMOが活動していた頃)に流行した「テクノポップ」ではなく、アメリカ・デトロイトを発祥とするエレクトロニック・ダンス・ミュージックを指していた。
再生YMOは、あえてその新しいテクノに挑んだわけだが、メンバーそれぞれが日本を代表するミュージシャンだけあって、ダンス・ミュージックの枠を遥かに超えたアイデアや実験が盛り込まれており、筆者としては「Technodelic」(1981年)の90年代版という印象。そして何よりも音のクオリティが素晴らしい。マドンナ(Madonna)やデペッシュ・モード(Depeche Mode)のミックスを手がけた、ゴウ・ホトダの貢献が大きい。
中でも感嘆したのが、7曲目の「Nostalgia」。坂本龍一(さかもと・りゅういち)による作品で、風の音や鳥の鳴き声など、坂本本人が収集してきた現実音と、オーケストラからサンプリングしたコードが鳴っているだけなのだが、荒涼とした大地を思わせる空間の奥深さがすごい。
なお、このアルバムは2020年にゴウ・ホトダと砂原良徳(すなはら・よしのり)によってリマスタリングされ、さらに音の解像度が増している。
7. 坂本龍一「Ieta」(2022年)
その坂本龍一が、約30年後に配信のみで発表したシングル。坂本自身は「今までアンビエントを作ったことはない」と言っていたようだが、先に挙げた「Nostalgia」のワーキング・タイトルが「アンビエント」だったことからわかるように、それは一種のポーズだろう。あるいは、一時期アンビエントに没入していた細野晴臣(ほその・はるおみ)を意識しての発言だったのかもしれないが、本人の意識はどうあれ、彼自身もアンビエントと解釈できる作品を多く残している。
そして、「Nostalgia」とこの「leta」を続けて聴けば、「あぁ、同じ人の曲だな」とわかる。漂う空気感、音の空間の捉え方が同じだからだ。現在では、インスト初のオリコン1位を獲得した「energy flow」で坂本龍一を知った人たちも多いだろうが、同じピアノの弾き語りでも、筆者はよりシンプルなメロディの、この「leta」に、より「癒やし」を感じる。
(参考資料)
・三田格 監修「AMBIENT definitive アンビエント・ディフィニティヴ -増補改訂版-」(Pヴァイン、2022)
・「別冊ele-king アンビエント・ジャパン」(Pヴァイン、2023)
・細野晴臣著「アンビエント・ドライヴァー」(筑摩書房、2016)
・【2025】美しきアンビエントの世界。一度は聴きたいおすすめの名盤まとめ
※記事の情報は2025年2月10日時点のものです。
後編に続く
-

【PROFILE】
徳田 満(とくだ・みつる)
昭和映画&音楽愛好家。特に日本のニューウェーブ、ジャズソング、歌謡曲、映画音楽、イージーリスニングなどを好む。古今東西の名曲・迷曲・珍曲を日本語でカバーするバンド「SUKIYAKA」主宰。
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- アナログシンセの名曲・名演・名音 1967~1979年(洋楽編) 音楽ライター:徳田 満
-

- 限りなく透明に近い、音楽 スーパーミュージックラバー:ケージ・ハシモト
-

- 日本が世界に誇るテクノポップ、その創作の秘密 音楽ライター:徳田 満
-
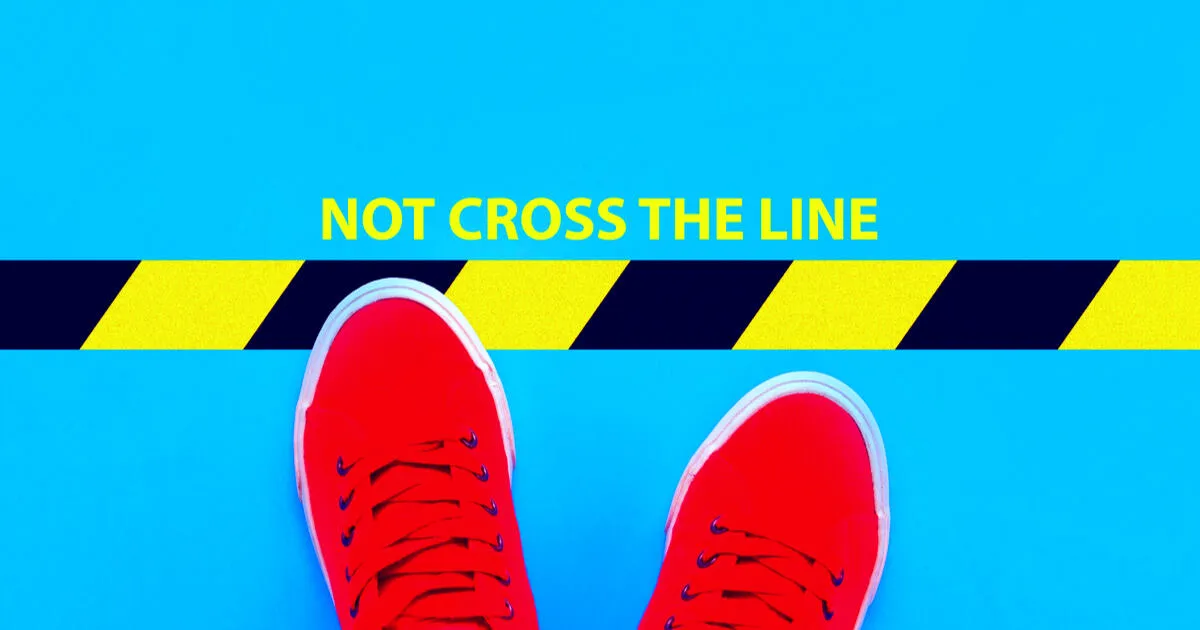
- ジャンルを超えろ! 越境者たちが創造する新たな音楽 スーパーミュージックラバー:ケージ・ハシモト
-

- 近ごろ気になる音楽の創り手たち ~ユトレヒト、ロンドン、フリータウンから~ ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ
NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事
-

- 冬に聴きたい、しっとりココロ潤うクラシック クラシック音楽ファシリテーター:飯田有抄
-

- LEO|箏の可能性を切り拓く新鋭箏奏者。古典と革新の演奏で箏の伝統をつなぐ LEOさん 箏奏者〈インタビュー〉
-

- 「黄金世代」のソングライター特集。1940~1942生まれの美メロメーカーたち ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ
-

- はいだしょうこ|宝塚歌劇団から歌のお姉さんへ。歌が誰かの支えになれるなら、歌い続けたい はいだしょうこさん 歌手〈インタビュー〉