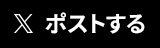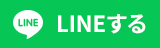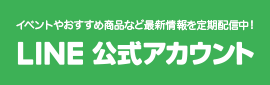【連載】創造する人のためのプレイリスト
2025.02.14
音楽ライター:徳田 満
冬のアンビエント【後編】
クリエイティビティを刺激する音楽を、気鋭の音楽ライターがリレー方式でリコメンドする「創造する人のためのプレイリスト」。今回は、「冬のアンビエント」の後編です。ブライアン・イーノ「1/1」や坂本龍一「Ieta」などの7曲を取り上げた前編に続き、冬の乾いた空気によく馴染む「アンビエント」、環境音楽を紹介します。
カバーフォト:Andreas Tormin/Shutterstock.com
「アンビエント(ambient)」とは環境のことで、音楽で言うアンビエントは「環境音楽」と訳される。このジャンルを提唱し、また第一人者でもある音楽家、ブライアン・イーノ(Brian Eno)は、「興味をそそると同時に無視できる」「落ち着きと思考の空間を誘う」と定義していたが、現在ではその枠は無限に広がり、どんな音楽をアンビエントと捉えるかは聴き手に委ねられている。
今回は、冬の乾いた空気によく馴染む(と筆者が感じた)作品を選んでみた。ぜひ、ヘッドフォンではなくステレオのスピーカーを通して、その音の響きに心も身体も浸してほしい。
〈冬のアンビエント【後編】 目次〉
- 細野晴臣「Naga」
- ドイター「Nada Himalaya 1」
- ススム・ヨコタ「Saku」
- ヨハン・ヨハンソン「The Jewish Cemetery on Møllegade」
- ニヴヘック「After its own death:side A」
- ソルト・オブ・ザ・サウンド & サイモン・ウェスター「Restore」
- グリーン・ハウス「Peperomia Seedling」
8. 細野晴臣「Naga」(1995年)
前編で紹介した坂本龍一(さかもと・りゅういち)から仮想敵(笑)とされた細野晴臣(ほその・はるおみ)。YMO「散開」後の1980年代中頃から90年代中頃まで、ずっと「アンビエントの海」を漂っていたと自ら語るだけあって、その間のソロ作品では、ほとんどインストゥルメンタルものしか発表していない(さらに言えばYMOが存在していた時期でも、アンビエントと呼べる作品はあるのだ)。
なので、当然ながら秀逸なアンビエント作も多く、どれを選ぶかとても迷ってしまう。「Mercuric Dance(マーキュリック・ダンス~躍動の踊り)」(1985年)の「To the Air」もブライアン・イーノのようなアプローチながら冬にぴったりだし、「Medicine Compilation-From the Quiet Lodge」(1993年)に収められた「Honey Moon」のセルフカバー(オリジナルは1975年発表の「Tropical Dandy」に収録)も、アンビエント感にあふれている。
で、今回はとりあえず、「Naga」(1995年)のタイトル・チューンにしてみた。細野らしいオリエンタリズムと宗教(仏教)的な佇まいが、この曲にはあるからだ。
9. ドイター「Nada Himalaya 1」(1997年)
1970年代から活動するドイツのニューエイジ・ミュージシャン、ドイター(Deuter)によるアルバム「Nada Himalaya」の1曲目。サブタイトルに「Music for Meditation」とあるように、最初から瞑想用に作られている。そもそも音楽としての「ニューエイジとは何か」ということだが、これもアンビエント同様に曖昧で、思想として「ニューエイジ・ムーブメント」の影響を受けているミュージシャンもいればそうでない人もいる。
このドイターがどちらなのかはわからないが、本作はヒマラヤ、チベットの鐘がドローン(持続音)の手法により延々と鳴っているだけ。と言ってしまっては身も蓋もないが、倍音効果も加わったこの響きにはただただ圧倒される。聴く人を深〜い瞑想(あるいは眠り)に誘ってくれるという意味では、とても優れた作品だと思う。
10. ススム・ヨコタ「Saku」(1999年)
ススム・ヨコタ(横田進)は、前編で紹介したYMOより一回り下の世代となる1960年生まれながら、2015年に54歳で亡くなってしまったアーティスト。デビューは1992年で、ドイツのレーベルからTENSHIN名義でシングルを発表。当時の作風は完全にデトロイト・テクノだったが、次第に静かなメロディやビートに移行していく。
数多い彼の作品の中でも世界で最も評価されているのが、この「Saku」から始まるアルバム「Sakura」である。リバーブ、テープエコー、ドローン、ミニマルといったエフェクトや手法を駆使して作り上げたのは、浮遊感に満ちていながらも心安らぐ音。同じ日本人から見るとよくわからないが、欧米人はこのサウンドに日本や東洋を感じるのだという。
11. ヨハン・ヨハンソン「The Jewish Cemetery on Møllegade」(2012年)
電子音楽(エレクトロニカ)の世界では、1990年代後期になると「グリッチノイズ」を取り入れたサウンドが流行し始める。グリッチノイズとは「プチッ」という技術的ミスから生じる雑音。それをわざと楽曲に入れることで、有機的な音世界を作り出そうという意図がある。
アイスランド出身の作曲家・キーボーディスト、ヨハン・ヨハンソン(Jóhann Jóhannsson)も、その手法を取り入れた一人(彼もまた48歳の若さで世を去ってしまった)。もともとはパンク・ロックを志向していたが、その後、映画やテレビの音楽から、ダンス音楽まで幅広く手がけるようになる。
この「The Jewish Cemetery on Møllegade」も、ドキュメンタリー映画のサウンドトラック「Copenhagen Dreams」の中の1曲。エレクトロニカ、室内楽やミニマル(反復)音楽といったヨハン・ヨハンソンを特徴づける要素が、寂しくも美しい音世界を構築している。
12. ニヴヘック「After its own death:side A」(2019年)
アメリカ・オレゴン州出身のリズ・ハリス(Lis Harris)によるプロジェクト(Grouperという別名義もある)で、この「Side A」を含む「After Its Own Death / Walking in a Spiral Towards the House」がNivhekとしてのデビュー・アルバム。
冒頭、彼女自身による神々しいまでに美しいコーラスに浸っていると、やがて不穏な電子音が侵入。かと思うと再び静寂が戻り、ビブラフォン*1のようなドローンが覆う。メロトロン*2やギター、フィールド・レコーディング、テープ・マニュピレーション、ジャンクのエフェクター・ペダルなどを駆使した音世界は、淡々としながらも圧倒的。ブライアン・イーノの正当な後継者のような印象もある。
*1 ビブラフォン:金属製の音板をピアノの鍵盤と同じように配列した鍵盤打楽器で、鉄琴の1種。
*2 メロトロン:1963年に登場したサンプル・プレイバックキーボード。各鍵盤に内蔵された録音済みテープをリアルタイムに再生する。
13. ソルト・オブ・ザ・サウンド & サイモン・ウェスター「Restore」(2024年)
アコースティック・ピアノに続く、透き通るような歌声に心癒やされる。
このソルト・オブ・ザ・サウンド(Salt of the Sound)は、アニタ・タットロウ(Anita Tatlow)とベン・タットロウ(Ben Tatlow)による夫婦デュオ・ユニット。「私たちの目標は、教会でも、個人的な時間でも、精神的な内省を促す音楽を創ること」と言うように、いわゆるクリスチャン・ミュージックではあるが、それにとどまらない一般性・普遍性が感じられる。
2013年のデビュー・アルバム「Jouneys」以来、シングル・アルバム合わせて32作を発表しており、この「Restore」が最新のシングル。イギリス・ロンドンからスウェーデン・ストックホルムへ、そして現在は香港に移住して活動している。
14. グリーン・ハウス「Peperomia Seedling」(2020年)
グリーン・ハウス(Green-House)は、アメリカ・ロサンゼルスを拠点とするノンバイナリー(性自認やジェンダー表現が男性/女性という枠組みに当てはまらない)・アーティスト、オリーブ・アルディゾーニ(Olive Ardizoni)のプロジェクト。デビューEP「Six Songs for Invisible Gardens」がいきなり世界中で高評価を受けたのだが、「Peperomia Seedling」はそのオープニング曲である。
このEPのコンセプトは「植物とその世話をする人々の相互のコミュニケーション」。鳥の鳴き声や水の音などの現実音とともに、シンプルで優しいシンセの音色がゆったりと奏でられている。
春を待ちながら過ごす、冬の午後――そんな時間にふさわしい音楽ではないだろうか。
(参考資料)
・三田格 監修「AMBIENT definitive アンビエント・ディフィニティヴ -増補改訂版-」(Pヴァイン、2022)
・「別冊ele-king アンビエント・ジャパン」(Pヴァイン、2023)
・細野晴臣著「アンビエント・ドライヴァー」(筑摩書房、2016)
・【2025】美しきアンビエントの世界。一度は聴きたいおすすめの名盤まとめ
※記事の情報は2025年2月14日時点のものです。
-

【PROFILE】
徳田 満(とくだ・みつる)
昭和映画&音楽愛好家。特に日本のニューウェーブ、ジャズソング、歌謡曲、映画音楽、イージーリスニングなどを好む。古今東西の名曲・迷曲・珍曲を日本語でカバーするバンド「SUKIYAKA」主宰。
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- アナログシンセの名曲・名演・名音 1967~1979年(洋楽編) 音楽ライター:徳田 満
-

- 限りなく透明に近い、音楽 スーパーミュージックラバー:ケージ・ハシモト
-

- 日本が世界に誇るテクノポップ、その創作の秘密 音楽ライター:徳田 満
-
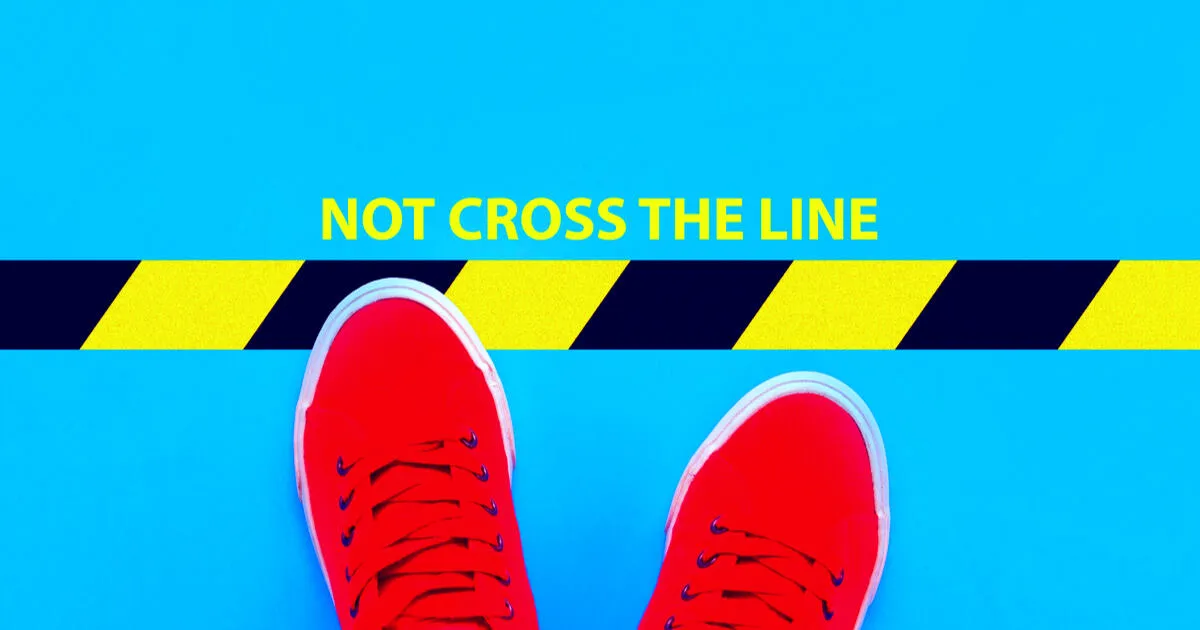
- ジャンルを超えろ! 越境者たちが創造する新たな音楽 スーパーミュージックラバー:ケージ・ハシモト
-

- 近ごろ気になる音楽の創り手たち ~ユトレヒト、ロンドン、フリータウンから~ ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ
NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事
-

- 冬に聴きたい、しっとりココロ潤うクラシック クラシック音楽ファシリテーター:飯田有抄
-

- LEO|箏の可能性を切り拓く新鋭箏奏者。古典と革新の演奏で箏の伝統をつなぐ LEOさん 箏奏者〈インタビュー〉
-

- 「黄金世代」のソングライター特集。1940~1942生まれの美メロメーカーたち ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ
-

- はいだしょうこ|宝塚歌劇団から歌のお姉さんへ。歌が誰かの支えになれるなら、歌い続けたい はいだしょうこさん 歌手〈インタビュー〉