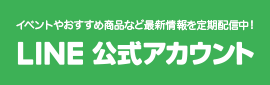【連載】創造する人のためのプレイリスト
2022.10.04
音楽ライター:徳田 満
「ムード歌謡」の系譜
ゼロから何かを生み出す「創造」は、産みの苦しみを伴います。いままでの常識やセオリーを超えた発想や閃(ひらめ)きを得るためには助けも必要。多くの人にとって、創造性を刺激してくれるものといえば、その筆頭は「音楽」ではないでしょうか。「創造する人のためのプレイリスト」は、いつのまにかクリエイティブな気持ちになるような音楽を気鋭の音楽ライターがリレー方式でリコメンドするコーナーです。
カバーフォト:piya Sukchit/Shutterstock.com
「ムード歌謡」と言っても、現在の40代以下の人には通じないかもしれない。昭和の時代に流行した歌謡曲の一形態ではあるのだが、実はムード歌謡とは何かという定義は存在しない。なぜなら「ムード」という言葉は、「雰囲気、気分、情緒」という主観的なものを意味する。つまり、聴いた人間が「これはムード歌謡だ」と判断すれば、その曲はムード歌謡になるからだ。実に日本人的な曖昧さゆえに成り立つ、日本にしかないジャンルなのだが、それらの楽曲は、現在のJ・POPからはほぼ失われてしまった「大人の音楽」の魅力にあふれている――というわけで、今回はムード歌謡の系譜をたどり、再評価を促したい。
1.淡谷のり子「別れのブルース」
1937(昭和12)年に発表された、ムード歌謡の元祖であり、「ブルース歌謡」の第1号でもある楽曲。それまでの歌謡曲が、小唄や民謡などの俗謡風、行進曲などのマーチ風、軽快なスイング・ジャズ調だったのに対し、初めて気だるい情緒(Blues=ブルース)を前面に押し出した画期的な作りとなっている。
原型は作詞の藤浦洸(ふじうら・こう)と作曲の服部良一(はっとり・りょういち)が横浜・本牧での取材を経て書き上げた「本牧ブルース」で、本来はソプラノキーだった淡谷のり子を強引に説得して、低音で歌わせた作戦が見事に成功。以後、淡谷は「ブルースの女王」と呼ばれるまでになる。
当時は日中戦争のさなかで、退廃的な雰囲気が時局に合わないとレコード会社は難色を示したが、いざ発売されると、満州(現・中華人民共和国東北地方)に渡っていた日本人の間で評判となり、厭戦(えんせん)気分が増していた国内でも大ヒット。スローでマイナー(短調)の曲調、低音で声を張り上げない歌唱、漂う哀愁など、その後、ムード歌謡としてヒットを飛ばす曲に共通する要素が、しっかりとこの音源に刻まれていることが分かる。
2.ディック・ミネ「上海ブルース」
淡谷のり子が「ブルースの女王」なら、「ブルースの王」はディック・ミネだろう。そうした呼び方がされない理由は、ディック・ミネが幅広い音楽性を持ち、さまざまなタイプのヒット曲を世に出しているからだと思う。実際、戦前に録音された音源を聴くと、ありとあらゆるリズムの楽曲をたやすく歌いこなす才能のきらめきに圧倒される。
それでも彼を「ブルースの王」と呼びたくなるのは、男性シンガーによるムード歌謡の元祖であり、ひとつの理想形を成しているからで、後述するフランク永井や石原裕次郎など、ディック・ミネに強い影響を受けた歌手も多い。
この「上海ブルース」は前述した淡谷のり子の「別れのブルース」から2年後、1938(昭和13)年の作品だが、当時日本租界のあった上海を舞台にした異国情緒あふれる歌詞に、イントロ、平歌、サビとメロディー構成も完璧。何よりも、エコーのたっぷりかかったクルーナー・ボイス*が魅力で、ムード歌謡の「ムード」とは歌声のことだと思い知らされる。
* クルーナー・ボイス:クルーン(croon)とは英語で「ささやくように優しく甘く歌う」といった意味。声を張り上げず、抑制した低い声でささやくように歌う歌い方をクルーナー唱法といい、その声をクルーナー・ボイスと呼ぶ。
3.フランク永井「有楽町で逢いましょう」
戦前を「プレ・ムード歌謡期」とすれば、戦後の昭和30~40年代は、「ムード歌謡黄金時代」と言える。敗戦で打ちひしがれた日本人が少しずつ立ち直って、諸外国が驚くほどのスピードで復興を成し遂げ、経済白書に「もはや戦後ではない」と書かれるまでになったのが1956(昭和31)年。その翌年に生まれたのが、ムード歌謡の代名詞的存在となった「有楽町で逢いましょう」である。
フランク永井は、それまで米軍(進駐軍)キャンプでジャズソングを歌っていたが、日本占領の終結とともに、ポピュラー歌手へと転向。ただ、ずっと英語で歌っていたので、日本語で歌うと奇妙な発音になってしまう。しかし、その英語なまりがあったからこそ、作曲者の吉田正(よしだ・ただし)が狙ったジャジーで都会的なサウンドに違和感なくマッチして、爆発的ヒットとなったのではないだろうか(これは先達のディック・ミネにも同じことが言える)。
4.石原裕次郎&牧村旬子「銀座の恋の物語」
ここまででお気付きかと思うが、ムード歌謡の重要な要素のひとつに、「都会調」というものがある。現在では必ずしもそうではないが、昭和30年代の日本においては、「都会」といえば東京都心部、端的に言えば銀座のことだった。今でも全国各地に「○○銀座」と呼ばれる繁華街があるように、銀座は当時の日本人にとって憧れの街だったのである。
前述のフランク永井自身にも「西銀座駅前」というヒット曲があるが、彼の成功でムード歌謡ブームが到来した芸能界では、銀座を題材にした歌が山ほど作られた。その中でも最も有名と思われるのが、現在でもデュエット曲の定番としてカラオケで歌われている、1961(昭和36)年発売のこの曲だろう。
言うまでもなく石原裕次郎は高度成長時代を代表する映画スターだが、もともと当人がディック・ミネの大ファンだっただけに、同じ低音のクルーナー唱法一本槍。歌手としては特にうまいとは思えないが、主演作品で主題歌として流れることもあり、出す曲出す曲すべて大ヒットしているのもご存知の通りである。
5.ザ・ピーナッツ「ウナ・セラ・ディ東京」
女性歌手によるムード歌謡の代表作と断じてしまいたくなるほど、完成度の高い楽曲。1963(昭和38)年に「東京たそがれ」というタイトルで一度リリースされているが、このときはヒットせず、翌年来日した「カンツォーネの女王」ミルバが完璧な日本語でカバーしたことで話題となり、改めて「ウナ・セラ・ディ東京」として再発売したところ、大ヒットとなった。
岩谷時子による哀愁漂う歌詞、ボサノバを取り入れた作曲の宮川泰による絶妙なアレンジもさることながら、それまで主に欧米ポップスのカバーや明るく元気な曲調のオリジナルを歌ってきたザ・ピーナッツが、大人のしっとりとしたバラードを見事に歌いこなしたことで、彼女たちの代表作のひとつにもなった。J・POPのスタンダードとしてさまざまなアーティストに歌い継がれているが、筆者は2006(平成18)年にたまたま生で聴いた、矢野顕子と大貫妙子によるデュエットが強く印象に残っている。なお、「ウナ・セラ・ディ東京(Una Sera di Tokio)」とはイタリア語で「東京のゆうべ」という意味。
6.和田弘とマヒナスターズ「泣かないで」
時代は少し戻って1958(昭和33)年。この年、ムード歌謡の歴史にとってはエポックメーキングな出来事が起こる。和田弘とマヒナスターズの「泣かないで」の大ヒットである。
彼らの功績は、①ムード歌謡コーラスというジャンルを開拓・確立したことと、②歌謡曲にスティール・ギターやファルセット(裏声)といったハワイアン音楽を導入したこと。もともとはハワイアンのバンドで、営業で演奏しているうち必要に迫られて歌謡コーラスバンドに変化していったわけだが、ムード歌謡の第一人者・吉田正の作曲とはいえ、この編成を当時の大衆がさして奇異に思わず、よく受け入れたと思う。
また、彼らは演奏も自身で行うため、松尾和子や吉永小百合、田代美代子などのゲストボーカルをフィーチャーすることでマヒナのサウンドを広めることができた。その結果、スティール・ギターの音色やファルセットは、ムード歌謡の世界を表現するものとして、日本人(のみ)に定着してしまったのである。
7.内山田洋とクール・ファイブ「長崎は今日も雨だった」
マヒナスターズの成功を受けて、歌謡界はムード歌謡コーラスブームを迎える。ハワイアンをルーツにしていたマヒナに対し、ラテンをルーツにしていたのが、1967(昭和42)年の「小樽のひとよ」で知られる鶴岡雅義と東京ロマンチカと、同年の「ラブユー東京」が代表曲となる黒沢明とロス・プリモス、翌年に「知りすぎたのね」でブレイクするロス・インディオス。そして、リズム&ブルースをルーツとしていたのが、内山田洋とクール・ファイブだった。
1969(昭和44)年に発売されたメジャーデビュー曲であり最大のヒット曲「長崎は今日も雨だった」のコーラスについて、大滝詠一はファイブ・サテンズの「In The Still of The Night」だと分析しているが、確かにリードを取る前川清のボーカルやクール・ファイブのコーラスには、1950年代のドゥーワップ・グループなどの影響が強く感じられる。
このあたりを、同時期にデビューしながらムード歌謡にいかず、そのまま本格的なドゥーワップに進んだザ・キング・トーンズと比較してみるのも面白いだろう。
※現在デジタルミュージックでは前川清バージョンのみ購入可
8.青江三奈「恍惚のブルース」
淡谷のり子の項で、ムード歌謡に共通する要素として低音を挙げたが、女性歌手の場合、ハスキーボイスというのも重要な特徴である。現在では宇多田ヒカルや椎名林檎といったところになるだろうが、その元祖的存在が、この青江三奈。ミリオンヒットとなった代表曲「伊勢佐木町ブルース」ではため息まで入っているが、そこまでしなくても歌声だけで十分にセクシーである。
この「恍惚のブルース」は1966(昭和41)年に発売されたデビュー曲だが、具体的にきわどいことを歌っているわけではないのに、「あとはおぼろ......」というフレーズだけで、まさに恍惚の状態をイメージさせてくれる。青江は当時25歳。クラブ歌手の経験があるとはいえ、新人でこれだけの色気を表現できるというのは、空前絶後ではないだろうか。また、イントロのテナーサックスも、ムード歌謡の「ムード」を盛り上げるには大変重要。石原裕次郎の「夜霧のブルース」や水原弘の「黒い花びら」のイントロを吹いた松本英彦のテナーの素晴らしさにも、ぜひ注目(注耳?)してほしい。
9.パープル・シャドウズ「小さなスナック」
1960年代後期になると、ザ・タイガースやザ・テンプターズなどのGS(グループ・サウンズ)ブームが訪れるが、それもわずか2~3年であっけなく衰退。彼らはビートルズやローリング・ストーンズなどに触発されてバンドを組んだ若者たちではあったが、その多くは歌謡界の作詞家・作曲家が作った歌謡曲を歌い演奏していた「バンド型アイドル」だったため、飽きられるのも早かった。
ほとんどのバンドは解散したが、開き直ってそのまま歌謡曲に移行したバンドや、逆に最初から歌謡路線で結成したバンドもある。その代表的存在が、1968(昭和43)年結成のパープル・シャドウズ。この「小さなスナック」はリーダーの今井久が作曲したデビュー曲で、バンドの最大にして唯一のヒットなのだが、エコーを効かせたエレキギターとシャッフルビートをうまく使った聴きやすいサウンドは、まさにGS版ムード歌謡だ。ちなみに「ブルー・シャトウ」で知られるジャッキー吉川とブルー・コメッツが同年にリリースした「雨の赤坂」も、隠れたGSムード歌謡の傑作。
10.増位山太志郎「そんな女のひとりごと」
時代は一気に飛んで1970年代後半。この頃になると、60年代のようなムード歌謡コーラスブームは終わっていたものの、内山田洋とクール・ファイブの作品はコンスタントにヒットしていたし、他にも敏いとうとハッピー&ブルーの「わたし祈ってます」「星降る街角」「よせばいいのに」や、先述のロス・インディオスに女性歌手を加えたロス・インディオス&シルヴィアの「別れても好きな人」など、散発的にヒットを飛ばすグループもあり、ムード歌謡というジャンルが一般に定着した時期だと言える。
ソロでも、小林旭の「昔の名前で出ています」など、男性が女性の一人称で歌うパターンが相変わらず人気を呼んでいたが、その極めつきと言えるのが、この増位山太志郎(ますいやま・だいしろう)の「そんな女のひとりごと」である。増位山は現役力士の頃から歌手デビューし、1974(昭和49)年の「そんな夕子にほれました」が大ヒット。その3年後に発売されたこの曲もミリオンヒットとなった。力士という男性的な本業とは裏腹に、繊細な歌声でつづられる女性の心のつぶやきが(女性以上に)艶っぽいことが、その大きな理由だろう。
11.丸山圭子「どうぞこのまま」
1970年代は、従来の歌謡曲とは成り立ちも音の感触も異なる、「ニューミュージック」と呼ばれる、若者向けの大衆音楽が生まれた時代でもある。そして、当時この言葉が最もふさわしく感じられる存在が、荒井由実(後の松任谷由実)だった。現在は「シティ・ポップ」の先駆的存在として捉えられているユーミンが最初に大ブレイクしたのが、1975(昭和50)年のシングル「あの日にかえりたい」。そしてその翌年に発売されたのが、54万枚を売り上げるヒットとなった、丸山圭子の「どうぞこのまま」であった。
この2つの作品には共通点が多い。どちらも1954(昭和29)年生まれの女性が自ら作った曲で、ボサノバを取り入れたマイナーのミディアムテンポ。ただし、「どうぞこのまま」には、「あの日にかえりたい」にはない歌謡曲、ムード歌謡っぽさが感じられる。おそらくは丸山圭子の歌い方や、主人公が受身的な歌詞が醸し出すのだろうが、逆に言えば、両者を分けているのは、そうしたわずかな違いだけだとも言えるのである。
12.ラッツ&スター「Tシャツに口紅」
内山田洋とクール・ファイブの項でドゥーワップの影響について述べたが、このラッツ&スター(当初はシャネルズ)も本格的ドゥーワップ・コーラスとしてデビューしたグループ。デビュー曲の「ランナウェイ」はまさに王道のドゥーワップだったが、次第に歌謡テイストを取り入れ始め、1983(昭和58)年、ラッツ&スターとしてのセカンドシングルとなる「Tシャツに口紅」では、80年代のムードコーラス歌謡と言っても過言ではない高みにまで到達している。
完成度が高いのは当然といえば当然で、作詞は松本隆、作曲はラッツの「師匠」でもある大滝詠一。大滝はドゥーワップの本家、ザ・ドリフターズの線を狙ったらしく、後に発売されたセルフ・カバー版では確かにその意図が見えるが、リードボーカルの鈴木雅之の個性なのか、同じオケでもラッツ版には「歌謡」の香りが漂うところが面白い。
13.EGO-WRAPPIN'「色彩のブルース」
昭和の終わりとともに歌謡曲の名称は消え、日本人によるポピュラー音楽は「J・POP」と呼ばれるロック/ポップス傾向のものと、衰退著しい演歌に大別されるようになった。ところが20世紀が終わろうとする頃、幼少時に歌謡曲に親しんだ世代による「昭和歌謡」の再発見が行われるようになり、その過程で生まれたのが、2000(平成12)年に発表された屈指の名曲「色彩のブルース」である。
結成当初のEGO-WRAPPIN'は、英語中心のミクスチャーミュージック路線だったが、やがて自分たちのルーツである歌謡曲や戦前ジャズ、キャバレー音楽などを取り入れた楽曲を作るようになる。ただ、取り入れるのはあくまでエッセンスであり、演奏や歌唱を細かく見てみると、昭和ではなく新たな時代の歌謡を目指していることが分かる。余談ながら、この曲がリリースされて数年後、大分・別府を旅していた筆者は、昭和初期~中期に建てられたと思しきキャバレーからこの曲が聴こえてきて、そのあまりのハマり具合に驚いたという経験がある。
14.タブレット純「百日紅(さるすべり)」
現在のところ、最新のムード歌謡と言えるのが、今年5月にリリースされた本作。現在はバラエティータレントとしても活動している「ムード歌謡漫談家」タブレット純の、デビュー20周年記念曲である。よく知られているように、タブレット純は先述したマヒナスターズの最晩年に加入し、ムード歌謡唱法(?)を会得(当時の芸名は田渕純)。
実はタブレット純とは、2011(平成23)年に筆者が森田公一とトップギャランのメモリアルブックを自費出版で上梓した折に知己を得たのだが、彼は昭和歌謡やGSの異常とも言えるマニアであり、今回の原稿もその著書を参考にさせてもらいながら書いてきた。だからというわけではなく、この動画を視聴していただければ分かる通り、歌手としての実力も申し分ない。ここまで来たら、「最後のムード歌謡歌手」として、命果てるまで歌い続けてほしいものである。
※記事の情報は2022年10月4日時点のものです。
-

【PROFILE】
徳田 満(とくだ・みつる)
昭和映画&音楽愛好家。特に日本のニューウェーブ、ジャズソング、歌謡曲、映画音楽、イージーリスニングなどを好む。古今東西の名曲・迷曲・珍曲を日本語でカバーするバンド「SUKIYAKA」主宰。
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- 1970年代・シティポップの歌姫たち 音楽ライター:徳田 満
-

- 筒美京平Covers|カバーだからこそ見えてくる不世出のメロディーメーカーの醍醐味 音楽ライター:徳田 満
-

- 「ポップス」としての日本映画音楽 昭和篇 音楽ライター:徳田 満
NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事
-

- 冬に聴きたい、しっとりココロ潤うクラシック クラシック音楽ファシリテーター:飯田有抄
-

- LEO|箏の可能性を切り拓く新鋭箏奏者。古典と革新の演奏で箏の伝統をつなぐ LEOさん 箏奏者〈インタビュー〉
-

- 「黄金世代」のソングライター特集。1940~1942生まれの美メロメーカーたち ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ
-

- はいだしょうこ|宝塚歌劇団から歌のお姉さんへ。歌が誰かの支えになれるなら、歌い続けたい はいだしょうこさん 歌手〈インタビュー〉