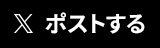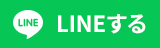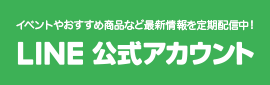【連載】「明日の体調」を変える「今日の食」
2025.04.28
管理栄養士:森由香子
寒くないのに手足が冷える......。冷え性を改善する栄養素とは!? |管理栄養士・森由香子が教える「明日の体調」を変える「今日の食」
1日中だるい、疲れが取れない、なかなか寝られない......。なんとなくバランスよく食事を摂っているつもりでも、体調は日々変化していきます。そんな何気ない体調の変化や不調は、体が今何を欲しているのかを雄弁に物語るサイン! 連載第3回は、冷え性を改善する栄養素を紹介します。「明日の体調」を変える「今日の食」を、管理栄養士の森由香子(もり・ゆかこ)さんに監修いただきました。
カバーフォト:Cookie Studio/Shutterstock.com
冷え性は冬だけではない。そもそもなぜ冷え性になるの!?
「冷え性」と聞くと寒い季節に限った症状のように思われがちですが、年間を通じて冷え性に悩まされている人は少なくありません。冷え性は単なる寒さだけが原因ではなく、実は血流の悪化や自律神経の乱れ、筋肉量の不足などが深く関係しているのをご存知でしょうか。
人の体温は血液によって維持されています。心臓から送り出された血液が全身をめぐり、各組織に熱を運ぶことで、私たちは平熱を保つことができます。しかし、血流が悪くなると体の隅々まで十分な血液が行き渡らず、手足が冷たくなったり、体の末端が冷える。これも冷え性のひとつの原因です。
また、自律神経の働きも重要な役割を担っています。通常、人は寒さを感じると、交感神経が活発になり、血管を収縮させて熱を逃がさないように調整します。しかし、ストレスや生活習慣の乱れによって自律神経の働きが乱れると、血管が必要以上に収縮し血流が悪くなったり、逆に広がりすぎて熱が逃げやすくなったりして、冷えの原因となるのです。

熱を生み出す力が弱いという点では、筋肉量が少ないと体も冷えやすくなります。人のエネルギー消費量の約6割が基礎代謝量といわれていますが、その基礎代謝量の約2割を筋肉が担い、筋肉がエネルギーを消費することで熱を生み出しています。そのため、筋肉量が少ないと熱をつくり出す力が弱くなり、冷えやすくなるのです。とくに、女性は男性に比べて筋肉量が少ないため、冷え性に悩む人が多いとされているのもこのためです。
冷え性の改善に役立つ栄養素を紹介していく前に、まずは次のリストをチェックしてみましょう。3つ以上当てはまる人は、食事の摂り方、栄養のバランスが冷え性の原因になっているかもしれません。
冷え性チェックリスト
→食べたものから、効率よく熱がつくられにくくなります。 →必要なエネルギーを供給できず、体温を上げるためのエネルギーが不足します。自律神経のバランスが乱れることで血行不良を引き起こし、冷えが起こりやすくなります。 →炭水化物や脂質は効率的なエネルギー源であるため、体温調節に必要なエネルギーが不足します。 →血液には熱を運ぶ役割がありますが、貧血になると、血液の循環が悪くなり、十分な酸素が届きません。そのためミトコンドリア(熱産生器官)が十分に機能せず、冷えを感じやすくなります。 →栄養バランスが乱れると、筋肉量や筋力の低下が起こりやすくなります。 →カフェインの摂取量が多いと、血管が収縮して血行が悪化、手足などの末端部分への血流が減少し、体温が下がりやすくなります。冷え性を改善する7つの栄養素
冷え性の改善には、エネルギーを産生し、熱をつくり出すことと、血行を促進し必要な栄養素や熱を体の隅々まで運ぶことが重要です。
まず、そのために大切な栄養素がたんぱく質です。たんぱく質は筋肉の材料となり、筋肉がエネルギーを消費することで熱を生み出します。糖質や脂質も重要なエネルギー源となり、エネルギー源が不足すれば熱の産生が低下、体温維持が難しくなります。
また、鉄は、体の各組織に酸素を運ぶ役割を担うヘモグロビンを血液中につくるため、鉄が不足すると貧血になりやすく、体が冷えやすくなります。ビタミンEは血流を促進し、手足の末端まで温かさを届ける働きを持ちます。
たんぱく質の役割と摂取できる食品
筋肉は収縮時(運動をする際や日常の動き)にエネルギーを消費し、その過程で熱を産生します。その筋肉の材料となっている栄養素がたんぱく質です。十分なたんぱく質を摂取することで筋肉は生成され、それにともない基礎代謝が向上、体温を維持しやすくなります。
肉、魚、卵、大豆製品などを食べ、良質なたんぱく質を摂取しましょう。とくに卵は完全栄養食品と呼ばれるほど栄養素が豊富で、卵に含まれるレシチンは、血流悪化の原因となるコレステロールを乳化し、コレステロールを分解、排泄する働きがあります。
たんぱく質を多く含む食品
▼横スクロールでご覧ください
| 食品名 | 100g 含有量 (g) |
1回使用量 | |
|---|---|---|---|
| 目安量 | 含有量 (g) | ||
| 若鶏ささ身 | 23 | 80g | 18.4 |
| 豚ヒレ肉 | 22.2 | 80g | 17.8 |
| 牛ヒレ肉 | 20.8 | 80g | 16.6 |
| 若鶏もも肉(皮なし) | 19 | 80g | 15.2 |
| 鶏卵 | 12.3 | 50g | 6.2 |
| まぐろ赤身 | 26.4 | 100g | 26.4 |
脂質の役割と摂取できる食品
脂質は体のエネルギー源となり、細胞膜の構成成分としても重要な役割を担います。脂質が不足するとエネルギー代謝が低下し、冷えやすくなります。
オリーブオイルをはじめとする植物油や青魚は、心血管の健康や血行促進に役立つ多価不飽和脂肪酸を含んでいます。
脂質を多く含む食品
▼横スクロールでご覧ください
| 食品名 | 100g 含有量 (g) |
1回使用量 | |
|---|---|---|---|
| 目安量 | 含有量 (g) | ||
| オリーブオイル | 98.9 | 大1(13g) | 12.9 |
| なたね油 | 97.5 | 大1(13g) | 12.7 |
| あまに油 | 99.5 | 大1(13g) | 12.9 |
| さば味噌煮缶 | 12.5 | 1缶(100g) | 12.5 |
| はまち | 13.4 | 1切れ(100g) | 13.4 |
糖質の役割と摂取できる食品
糖質は体内で最も効率的にエネルギーに変換される栄養素です。糖質が不足するとエネルギー不足になり、体温が低下しやすくなります。ただし、白米やパンなどの精製された糖質ではなく、玄米や全粒粉など未精製のものを摂ることで、血糖値の急上昇を防ぎながらエネルギーを供給できます。
血糖値の急上昇を抑えながら糖質を効率よく摂取する際は、野菜、海藻、きのこなど食物繊維が豊富な食品と一緒にとることがおすすめです。血糖値が急激に上がらず、自律神経の安定にもつながります。
糖質を多く含む食品
▼横スクロールでご覧ください
| 食品名 | 100g 含有量 (mg) |
1回使用量 | |
|---|---|---|---|
| 目安量 | 含有量 (mg) | ||
| コーンフレーク | 89.8 | 40g | 36 |
| フランスパン | 63.9 | 60g | 38.3 |
| もち | 50 | 50g | 25 |
| 精白米(ご飯) | 37.1 | 135g | 51.4 |
| 胚芽米(ご飯) | 37 | 135g | 51.2 |
| スパゲティ(茹で) | 31.8 | 200g | 62.6 |
| そば(茹で) | 26 | 200g | 54 |
ビタミンB群(B1、B2、B6)の役割と摂取できる食品
ビタミンB1は糖質の代謝を助け、エネルギー産生を促進し、ビタミンB2は脂質の代謝を調整し、血管や皮膚の健康維持に寄与します。たんぱく質の代謝をサポートし、エネルギーの効率的な供給をサポートするのがビタミンB6。自律神経を安定させる働きがあり、血行の改善につながります。
豚肉はビタミンB1、卵はビタミンB2、鶏肉やまぐろはビタミンB6を多く含むなど、食品により含有量が異なりますが、動物性食品にはビタミンB群が豊富に含まれています。
ビタミンB1を多く含む食品
▼横スクロールでご覧ください
| 食品名 | 100g 含有量 (mg) |
1回使用量 | |
|---|---|---|---|
| 目安量 | 含有量 (mg) | ||
| ロースハム | 0.60 | 1枚(30g) | 0.18 |
| 豚ヒレ肉 | 1.32 | 80g | 1.06 |
| 豚もも肉 | 0.96 | 80g | 0.77 |
| 鶏レバー | 0.38 | 50g | 0.19 |
| うなぎ蒲焼き | 0.75 | 100g | 0.75 |
| たらこ | 0.71 | 1/2腹(40g) | 0.28 |
| かつお(春獲り) | 0.13 | 1切(100g) | 0.13 |
ビタミンB2を多く含む食品
▼横スクロールでご覧ください
| 食品名 | 100g 含有量 (mg) |
1回使用量 | |
|---|---|---|---|
| 目安量 | 含有量 (mg) | ||
| 豚レバー | 3.6 | 50g | 1.8 |
| 牛乳 | 0.15 | コップ1杯(210g) | 0.32 |
| ヨーグルト(全脂無糖) | 0.14 | 1/2カップ(100g) | 0.14 |
| まさば | 0.31 | 1切(100g) | 0.31 |
| 豚ヒレ肉 | 0.25 | 80g | 0.2 |
| まがれい | 0.31 | 1切(150g) | 0.53 |
| 鶏卵(生) | 0.43 | 1個(50g) | 0.22 |
ビタミンB6を多く含む食品
▼横スクロールでご覧ください
| 食品名 | 100g 含有量 (mg) |
1回使用量 | |
|---|---|---|---|
| 目安量 | 含有量 (mg) | ||
| 牛レバー | 0.89 | 50g | 0.45 |
| 若鶏胸肉(皮なし) | 0.64 | 80g | 0.51 |
| 豚もも肉 | 0.33 | 80g | 0.26 |
| かつお | 0.76 | 1切(100g) | 0.76 |
| まぐろ赤身 | 0.85 | 100g | 0.85 |
| しろさけ | 0.64 | 1切(100g) | 0.64 |
ビタミンEの役割と摂取できる食品
ビタミンEは強い抗酸化作用を持ち、血管を広げて血流を促進する働きがあります。血流が改善されることで手足の末端まで熱が行き渡り、冷え性の解消につながります。
かぼちゃはビタミンEだけでなく、血管を健康に保つカロテノイドや血糖値の安定にもつながる食物繊維を多く含みます。鉄や良質な脂質を含むアーモンドなどのナッツ類もおやつ感覚で摂取できておすすめです。
ビタミンEを多く含む食品
▼横スクロールでご覧ください
| 食品名 | 100g 含有量 (mg) |
1回使用量 | |
|---|---|---|---|
| 目安量 | 含有量 (mg) | ||
| アーモンド(乾) | 30.3 | 10粒(20g) | 6.1 |
| コーン油 | 17.1 | 大1(13g) | 2.2 |
| かぼちゃ | 4.9 | 1/4個(200g) | 9.8 |
| 落花生(いり) | 10.6 | 10粒(20g) | 2.1 |
| まぐろ油漬缶(ライト) | 8.3 | 1缶(100g) | 8.3 |
| ほうれん草 | 2.1 | 1束(200g) | 4.2 |
ビタミンCの役割と摂取できる食品
ビタミンCは鉄の吸収を助ける働きがあるため、貧血予防にも役立ちます。また、LDLコレステロールを酸化させて動脈硬化を進行させる活性酸素を消去します。
柑橘類はビタミンCだけでなく血流を改善するクエン酸を含んでおり、食物繊維が豊富なキウイフルーツやイチゴは腸内環境を整える効果もあります。
ビタミンCを多く含む食品
▼横スクロールでご覧ください
| 食品名 | 100g 含有量 (mg) |
1回使用量 | |
|---|---|---|---|
| 目安量 | 含有量 (mg) | ||
| ブロッコリー | 120 | 1/2株(100g) | 120 |
| 柿 | 70 | 1個(160g) | 112 |
| ほうれんそう | 35 | 1束(200g) | 70 |
| キウイフルーツ | 69 | 1個(100g) | 69 |
| 赤ピーマン | 170 | 1/4個(40g) | 68 |
| 白菜 | 41 | 1枚(100g) | 41 |
| うんしゅうみかん | 35 | 1個(100g) | 35 |
| いちご | 62 | 4粒(50g) | 31 |
| じゃがいも(皮なし) | 28 | 1個(100g) | 28 |
鉄の役割と摂取できる食品
鉄は血液のヘモグロビンを構成し、酸素を体内に運ぶ役割を担っています。鉄が不足すると貧血になりやく、血流が悪化することで体の隅々まで熱が行き渡らず、冷えやすくなります。
体内に吸収されやすいヘム鉄を多く含む赤身の肉や青魚(血合い)がおすすめです。一方、ほうれん草やレバーなどに多く含まれる非ヘム鉄は体内に吸収されにくいのですが、ビタミンCと一緒に摂ることで吸収率がよくなります。
鉄(ヘム鉄)を多く含む食品
▼横スクロールでご覧ください
| 食品名 | 100g 含有量 (mg) |
1回使用量 | |
|---|---|---|---|
| 目安量 | 含有量 (mg) | ||
| 輸入牛ヒレ肉 | 2.8 | 80g | 2.2 |
| ぶり | 1.3 | 1切(100g) | 1.3 |
| 和牛もも肉 | 2.8 | 80g | 2.2 |
| 牛肩ロース(赤肉) | 2.4 | 80g | 1.9 |
| かつお | 1.9 | 1切(100g) | 1.9 |
| まぐろ脂身 | 1.6 | 1切(100g) | 1.6 |
森由香子さんからのワンポイントアドバイス!
冷え性の改善には、栄養バランスのよい食事を意識するだけでなく、日々の生活習慣を見直すことも重要です。とくに、適度な運動を取り入れることで筋肉量を増やし、基礎代謝を上げることで体温を維持しやすくなります。また、38~40℃程度のぬるめのお湯にゆっくり浸かることも効果的です。血行がよくなるだけでなく、リラックス効果も得られます。
体を冷やさないように衣服を工夫することも大切で、足を圧迫するようなソックスなども血行不良を招き、冷えの原因になります。同様にデスクワークなど、同じ姿勢で仕事を続ける人も血行不良になりやすいため、ストレッチや体操などを行うことで血流がよくなります。
参考文献
「改訂6版 臨床栄養ディクショナリー」(メディカ出版)
※記事の情報は2025年4月28日時点の情報です。
-

【PROFILE】
管理栄養士・日本抗加齢医学会指導士
東京農業大学農学部栄養学科卒業。大妻女子大学大学院(人間文化研究科 人間生活科学専攻)修士課程修了。医療機関をはじめ幅広い分野で活動中。クリニックで、入院・外来患者の栄養指導、食事記録の栄養分析、ダイエット指導、 フランス料理の三國清三シェフとともに、病院食や院内レストラン「ミクニマンスール」のメニュー開発、料理本の制作などの経験をもつ。食事からのアンチエイジングを提唱し、「かきくけこ、やまにさち」®食事法の普及につとめている。著書に『60歳からの「少食」でも病気にならない食べ方』『最新版 老けない人は何を食べているのか』『60歳から食事を変えなさい』『免疫力は食事が9割 』(青春出版社)など。2025年5月28日には『健康診断の数値がよい人は何を食べているのか』(廣済堂出版)を発売予定。
公式サイト https://moriyukako.com/
森由香子のパーソナル栄養指導 https://mori-yukaco.com
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- いまこそ知っておきたい「バランスの良い食事」の基本 森由香子さん 管理栄養士〈インタビュー〉
-

- もっと野菜を食べてほしい。美味しくてキレイで、クリエイティブだから。 庄司いずみさん 野菜料理家〈インタビュー〉
-

- 触覚――感触を楽しめる温泉 小松 歩
NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事
-

- お取り寄せで楽しむ、絶品ご当地餃子15選|小野寺力おすすめ! 全国お取り寄せ餃子道楽② ぎょうざジョッキー:小野寺 力
-

- 冷凍餃子のパリッとおいしい焼き方をプロが伝授! 羽根つきも簡単に焼くコツとは|小野寺力おすすめ... ぎょうざジョッキー:小野寺 力
-

- 稲垣貴彦|三郎丸蒸留所の革新は、ジャパニーズウイスキーの未来を形づくる 稲垣貴彦さん 三郎丸蒸留所〈インタビュー〉
-

- 寝付きが悪い、眠りが浅い......。睡眠の質を高める栄養素とは? 管理栄養士:森由香子