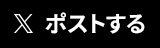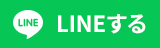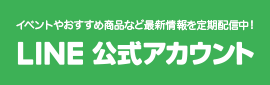【連載】創造する人のためのプレイリスト
2024.06.04
ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ
'20年代も創造を続ける名手たち(フェアーグラウンド・アトラクション来日記念特集)
クリエイティビティを刺激する音楽を、気鋭の音楽ライターがリレー方式でリコメンドする「創造する人のためのプレイリスト」。今回は、1980年代に一世を風靡しながらも、今なお新たな創造を続けるアーティストにフォーカス。その創作意欲と音楽にかける情熱は今なお健在です!
カバーフォト:CURAphotography/Shutterstock.com
今を去ること30数年、デビュー・シングルとアルバムがともに全英1位を獲得しながら、わずか2年で解散した伝説のバンドがありました――フェアーグラウンド・アトラクション(Fairground Attraction)。その再結成と来日というニュースに胸を躍らせたオールドファンも多いと思います。
しかし、もっと驚かされたのは、彼らが発表した新曲でした。そのレトロモダンなバンドサウンドは当時のままに、曲自体は今の2024年の気分にちゃんとリンクしていたからです。そこには1980年代から現在に至るまでのメンバー各人の音楽的な蓄積、培ってきた美意識と生命力が示されたような感動がありました。
今回は、このフェアーグラウンド・アトラクションをはじめ、80年代に一世を風靡しながら、40年ほど経過した2020年代にも新しい音楽の創造にチャレンジし続ける意欲的なベテラン・アーティストたちをピックアップしてみました。80年代当時の彼らを知るファンにも、その頃を知らない世代の方にも、その飽くなき創造への意欲とパワーを感じていただければ幸いです。
1. フェアーグラウンド・アトラクション「パーフェクト」(1988年)
まずはこのミュージックビデオ(MV)から。フェアーグラウンド・アトラクションが1988年3月にリリースしたファーストシングル曲です。跳ねるようなリズムとギターの3連ストロークが印象的なこの曲は、トラッド・ジャズにロカビリー、ニューオーリンズ音楽などが絶妙に交ざり合ったノスタルジックな雰囲気をもつ曲として、音楽のデジタル化が進む80年代末期にあって独特の個性を放っていました。
例えて言うなら、電子音が大音響で鳴るクラブを出た街角で、アコースティックの旅楽団に出くわしたような妙に爽やかな感動がありました。この曲は全英1位のヒットとなりました。
移動遊園地(Fairground)の出し物・演目(Attraction)という名前を持つ彼らは、4人編成。リードシンガーは、英国グラスゴー出身のスコットランド人のボーカル&ギタリスト、エディ・リーダー(Eddi Reader)で、その他の男性3人はイングランド人。ギター、ボーカル、ほとんどの曲の作詞作曲を手がけるマーク・ネヴィン(Mark Nevin)、ギタロンというメキシコの楽器を弾くサイモン・エドワーズ(Simon Edwards) 、そしてドラムス&パーカッションのロイ・ドッズ(Roy Dodds)というラインアップです。
この曲が収録されたファーストアルバム「The First Of A Million Kisses」(1988年)は3週間ほどの期間で全曲を録音したそうです。そのせいか、「これからは妥協せずに(自分たちのやりたいことを)パーフェクトにやるのよ!」と歌うこの曲は勢いとラフな感覚に満ちています。
写真家エリオット・アーウィット(Elliott Erwitt)の1955年の作品を使ったアルバム・ジャケットにも彼らのレトロモダンな嗜好が表れています。しかし、彼らは、スマッシュヒットを数曲出した後、あっさり解散してしまいます。アルバムがヒットしすぎて自由に活動できなくなったからというのが理由のようです。
2. フェアーグラウンド・アトラクション「ワッツ・ロング・ウィズ・ザ・ワールド?」(2024年)
1990年のバンド解散後、エディ・リーダーとマーク・ネヴィンはソロのシンガーソングライターとして、他のメンバーもミュージシャンとしてそれぞれ別に活動を続けました。しかし数十年が経ち、そんな彼らの活動のことも忘れかけていた2023年、再結成と新曲発表、来日公演という驚きのニュースが飛び込んできました。
再結成の経緯などはこの記事を書いている現在ではまだ詳しく語られていませんが、自分たちの直感に従って再び音楽仲間になることにしたという彼らが発表した新曲4曲のうちの1曲が「What's Wrong With the World?」です。
30数年ぶりに聴く彼らの新曲は、あの頃の曲の雰囲気は損なわず、若い頃に比べて肩の力が抜けて余裕を感じさせる演奏。エディの声にも円熟味が加わり、歌詞もより深まった気がします。しかし、細部をよく聴けば、この曲は「Perfect」の続編、あるいはアンサーソングであることに気づきます。
老境を迎え、さまざまな不安はあれども大丈夫だよ、気にしなくていいよと、自らと仲間を鼓舞するようなウィットと温かみのある歌詞、そして楽しい演出。フェアーグラウンド・アトラクション健在! と声を上げたくなる素晴らしいミュージックビデオだと感じました。
80年代末の激動の時代に「清涼剤」のように出現した彼らは一種のカウンター的な存在で、その活動が短命に終わることはある意味予定づけられていたのかもしれません。しかし、この2024年に、あえて80年代のスタイルで彼らが再び現れたことは、単なるレトロやノスタルジックな嗜好を超えた「意志」があると思います。彼らの考える「パーフェクト」な音楽がこれからも長く愛される存在になることを願います。
年齢を重ねたマーク・ネヴィン、エディ・リーダーたちが、2024年の今、その音楽を私たちの心にどう響かせるのか? 今年6月末から7月初めにかけて行われる来日公演は発売早々にソールドアウト。「Perfect」の歌詞を彼らと唱和する瞬間を心待ちにしている音楽ファンも多いことでしょう。楽しみですね。
3. ブルース・ホーンズビー&ザ・レインジ「ザ・ウェイ・イット・イズ」(1986年)
続いては、ブルース・ホーンズビー(Bruce Hornsby)。彼とそのバンド、ザ・レインジ(The Range)のデビュー・シングルです。シンプルながらも印象的なピアノのリフと、「いつだってそんな調子さ、何ひとつ変わりはしない」という歌詞が交互に繰り返されるキャッチーなこの曲は、1986年の米国音楽チャートで1位になりました。
筆者も 当時東京で行われた公演を見に行きました。この曲は貧困や階層、人種差別などの社会問題を直視する歌詞に、米国の公民権運動の残像を映しています。「何年経っても変わらない」という焦りを表現した同曲は、その後も2Pac(Tupac Amaru Shakur)をはじめとする複数のラッパー、ヒップホップアーティストにサンプリングされるなど、ポップス以外の世界でも共感を獲得しました。
ブルース・ホーンズビーは、1954年生まれ、米国バージニア州出身のピアニスト・アコーディオン奏者・作曲家です。大学で音楽を学んだ後、ロサンゼルスでセッション・ミュージシャンとして活動するかたわら、映画やテレビ音楽の作曲などを仕事にしていました。彼はヒットを飛ばす前から音楽業界の間では知られた存在で、いわゆるミュージシャンズ・ミュージシャンとしてリスペクトされていた人でした。
ザ・レインジとしての活動停止以降は、グレイトフル・デッド(Grateful Dead)のツアー・キーボード奏者としても知られ、またアメリカの伝統的なブルーグラスやジャズに傾倒したアルバムなども発表するなど、幅広い音楽ジャンルを横断する創作活動を長く展開。通算3度のグラミー賞にも輝いています。
4. ブリム「ディープ・ブルー」(feat. ブルース・ホーンズビー、ワイミュージック)(2024年)
そんな彼の名前を筆者が久しぶりに意識したのが、2019年発表のアルバム「Absolute Zero」です 。
ボン・イヴェール(Bon Iver)のジャスティン・ヴァーノン(Justin Vernon)や、ジャック・ディジョネット(Jack DeJohnette)、ブレイク・ミルズ(Blake Mills)といった米国を代表するアーティスト、さらにはニューヨークの室内楽アンサンブル「ワイミュージック(yMusic)」とコラボしたこの作品は、最新の音楽を取り入れつつ、米国の伝統的音楽、ロック、ジャズ、クラシックを横断する意欲的なアルバムでした。
そして2024年、ホーンズビーとワイミュージックは、「ブリム(BrhyM)」という共同プロジェクト名義で新アルバム「Deep Sea Vents」を発表しました。ホーンズビーのシンプルなメロディーに、クラシック~現代音楽~ポップスを縦横無尽に行き交うワイミュージックの管弦楽が絡みます。
曲によっては、より実験的でアバンギャルドなアプローチが見られ、バンジョーやマンドリンを使ったアメリカのカントリー風のメロディー&コーラスに不穏な不協和音を奏でるストリングスが入る曲もあります。この「Deep Blue」は音数を減らしたミニマルファンク風の味付けが新鮮。歌詞もファンタジックで隠喩に満ちていて、時折「The Way It Is」を彷彿とさせる印象的でシンプルなリフが聞こえる点も面白いです。
アメリカの音楽とインディークラシックが出会ったこのアルバム、さすがはミュージシャンズ・ミュージシャンという創造性の高さを感じます。まもなく70歳、ブルース・ホーンズビーが開く新しい音楽の扉の数はまだ尽きないようです。
5. エヴリシング・バット・ザ・ガール「ドライビング」(1990年)
トレイシー・ソーン(Tracy Thorn)とベン・ワット(Ben Watt)の2人によるユニット、エヴリシング・バット・ザ・ガール(Everything But The Girl、以下EBTG)。彼らは1982年デビュー。
当初のジャズやボサノヴァを基調とした内省的なアコースティック・サウンドから、ジャジーなビッグバンド・アレンジを加えたAOR的サウンド、さらに90年代以降はエレクトロニックに寄ったクラブ・ミュージック的なアプローチを見せ、その音楽世界を軽やかに広げてきたグループと言えます。
映像は、1990年発表のアルバム「The Language of Life」の1曲目「Driving」。ロサンゼルスでトミー・リピューマ(Tommy LiPuma)などのジャズのトップミュージシャン、アレンジャーと録音したこのアルバムは、ジャジーなAOR的アプローチを見せていた転換期の作品で、初期のシンプルなアコースティック・サウンドとは違った音の厚みがあり、ゴージャスなアレンジが魅力です。 映像は、デヴィッド・レターマンのテレビ番組に出演時のものですね。
90年代に入るとベン・ワットが難病を患い、活動は一時停滞しますが、かつてアコースティック・アレンジで発表した「Missing」を、NYのハウスミュージックDJトッド・テリー(Todd Terry)がリミックスしたバージョンを発表。エレクトロニック・サウンドを取り入れ、ハウスミュージックとして生まれ変わった同曲は全米2位、全英3位となるヒットとなりました。
その後、彼らはクラブ・ミュージックと親和性の高い作品を次々に発表、1999年の「Temperamental」などは電子音を生かした無機質なサウンドテクスチャーがすでに現代に通じるものがありました。しかし、このアルバムを最後にEBTGは事実上の解散。2000年以降の2人はパートナーとして家庭生活を営みながらもソロ・アーティストとしてそれぞれ個別の活動を続けてきました。
6. エヴリシング・バット・ザ・ガール「ナッシング・レフト・トゥ・ルーズ」(2023年)
7. エヴリシング・バット・ザ・ガール「ラン・ア・レッド・ライト」(Live for 6 Music)(2023年)
こうして20年以上が経った2022年11月、トレイシー・ソーンが突然自身のSNSでEBTGの活動再開を告知し、2023年1月に、先行シングルの「Nothing Left To Lose」を発表。4月にはアルバム「Fuse」がリリースされました。ここでは「Fuse」収録の2曲の映像をご覧ください。
「Nothing Left To Lose」は、ビンテージシンセとデジタルサウンドが併用され、現代的なバイブスを感じる曲です。また、ピアノとドローンシンセが融合する「Run a Red Light」の映像には60代となった現在の2人の姿が収められています。かつてパンク少女だったトレイシー、その着こなしの変わらぬかっこよさ! 深みを増したボーカルにも注目です。
全体のトーンは抑鬱的で気だるいのに、その中に結晶のような気高いものを感じる。そう、時間が経ち、ビートやサウンドは変わっても、EBTGの本質的な魅力は変わらないように思います。
トレイシー・ソーンの声は80年代にも、多くのアーティストたちの感性を刺激しましたが、彼女の低く独特の陰影のあるボーカルは、現代のジャジーなクラブ・ミュージックとの相性が非常にいいと感じます。新しい音楽に挑戦を続けるEBTGの次の作品が楽しみです。
8. ザ・スタイル・カウンシル「タンブリング・ダウン」(1985年)
英国の80年代はポスト・パンクの波が引いた後に、ソウルやR&Bに影響を受けた音楽性をもつグループやアーティストが一気に出現した時代でした。ワーキング・ウィーク(Working Week)、ユーリズミックス(Eurythmics)、ポール・ヤング(Paul Young)、アリスン・モイエ(Alison Moyet)、シンプリー・レッド(Simply Red)、ワム!(Wham!)のジョージ・マイケル(George Michael)等々。
彼らは、カーティス・メイフィールド(Curtis Mayfield)やマーヴィン・ゲイ(Marvin Gaye)といったひと世代上の米国黒人アーティストの音楽を下敷きにしながら、そこに英国の若者としての解釈を加えることで、新しいポップ・ミュージックを生み出していきました。このいわゆる英国版「ブルーアイド・ソウル」の代表格と言えるバンドが、ポール・ウェラー(Paul Weller)率いるザ・スタイル・カウンシル(The Style Council)でしょう。
この「Walls Come Tumbling Down!(邦題:タンブリング・ダウン)」は、彼らのセカンドアルバムからのシングルヒット曲。1985年の映像です。メンバーはウェラー(g & vo)の他、ディー・C・リー(vo、Dee C. Lee)、ミック・タルボット(key、Mick Talbot)、スティーヴ・ホワイト(ds、Steve White)。
当時のサッチャー政権や世界への若者世代の嘆き・怒りを歌詞で表明しながらも、外見はあくまでスタイリッシュに、そして当時流行の先端を行くサウンドで、鮮烈な印象を残した曲です(余談ですが、この数年後、ベルリンの壁が崩壊したニュース映像を見ながらこの歌詞のことを思い出しました)。
9. ポール・ウェラー「コズミック・フリンジズ」(2021年)
10. ポール・ウェラー「メイキング 66: イントロダクション [Episode 1]」(2024年)
ポール・ウェラーは、自分が気に入ったアーティストの音楽にインスピレーションを受けた曲づくりを、素直に実行してきた人という気がします。ザ・ジャム(The Jam)時代にはザ・フー(The Who)やスモール・フェイセス(Small Faces)といった60年代のバンドやモータウンからの影響を受け、ジャムの後期からスタイル・カウンシルの時代はカーティス・メイフィールドをはじめとするソウル・ミュージック、さらにはボサノヴァからの影響も隠そうともしませんでした。
そしてソロの初期にはスペンサー・デイヴィス・グループ(The Spencer Davis Group)やトラフィック(Traffic)、キンクス(The Kinks)といったバンドの曲から触発された曲づくりが目立ちます。好きなものが実にわかりやすい。正直に、好きなものを興味の赴くままに自らの音楽やスタイルに取り入れていく姿勢は、昔から変わらないようです。
映像は、2021年発表のアルバム「Fat Pop」の1曲目「Cosmic Fringes」、そして2024年5月に彼の66歳の誕生日に合わせてリリースされた新アルバム「66」のメイキング映像です。常に自らの限界を押し広げるという姿勢を貫いてきたポール・ウェラーの姿をここでも見ることができます。
3ピースバンドのジャムと、シンプルなロックに回帰したソロ初期の間に挟まれたスタイル・カウンシルは、80年代の当時は一部のロックファンからは軟弱と評された存在でした。しかし、この新曲のMVとメイキング映像を見て筆者は確信しました。
スタイル・カウンシルに見られた、「自分の音楽的ルーツに忠実に、その時その時の新しい要素を取り入れて自らの世界を広げていく姿勢(言い換えれば、いい意味でのミーハー精神)」こそがポール・ウェラーの真骨頂であり、それは60代後半になった今も彼の創造力の根っこにあるものなのだと。気骨があって、好きなものに正直で、いつもお洒落なウェラー兄貴は、80年代も今も我々のお手本なのです。きっと。
※記事の情報は2024年6月4日時点のものです。
-

【PROFILE】
シブヤモトマチ
クリエイティブ・ディレクター、コピーライター。ジャズ、南米、ロックなど音楽は何でも聴きますが、特に新譜に興味あり。音楽が好きな人と音楽の話をするとライフが少し回復します。
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- 近ごろ気になる音楽の創り手たち ~ユトレヒト、ロンドン、フリータウンから~ ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ
-

- 「伝統×現代」の接点で、名前を付けられない新しい音楽を創造する人びと ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ
-

- ネオソウル入門|最先端のリズムと洗練されたサウンド スーパーミュージックラバー:ケージ・ハシモト
-

- 創造するシニアたち Life starts at 50 ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ
NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事
-

- ウィスパー・ヴォイスの歌姫たち(洋楽編) Part2 音楽ライター:徳田 満
-

- ウィスパー・ヴォイスの歌姫たち(洋楽編) Part1 音楽ライター:徳田 満
-

- 冬に聴きたい、しっとりココロ潤うクラシック クラシック音楽ファシリテーター:飯田有抄
-

- LEO|箏の可能性を切り拓く新鋭箏奏者。古典と革新の演奏で箏の伝統をつなぐ LEOさん 箏奏者〈インタビュー〉
-

- 「黄金世代」のソングライター特集。1940~1942生まれの美メロメーカーたち ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ