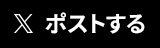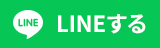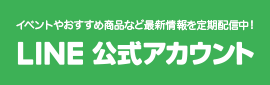音楽
2025.11.25
LEOさん 箏奏者〈インタビュー〉
LEO|箏の可能性を切り拓く新鋭箏奏者。古典と革新の演奏で箏の伝統をつなぐ
伝統楽器の箏(こと)を用い、クラシック、ジャズ、エレクトロニクスといったジャンルを超えた革新的な演奏で人々を魅了するLEO(れお)さん。19歳でデビューし、現在は多彩なアーティストとのコラボレーション、「ブルーノート東京」や「SUMMER SONIC(サマー・ソニック)」への出演など、箏奏者として異例の活躍を遂げています。箏の可能性を追求し続けるLEOさんに、箏や音楽への思いについてうかがいました。
写真:山口 大輝
小学校の授業で出会い、箏にのめり込んだ
――LEOさんは9歳の時、インターナショナルスクールの授業で箏と出会ったそうですね。
音楽の授業で箏が必修だったんです。僕は音楽家の家庭に生まれたわけではないので、楽器に触れるのも箏が初めてでした。ピアノと一緒で弾けば音が出るので、初心者でも親しみやすく、楽器に触れる楽しさを感じていました。管楽器やバイオリンのように初心者にとって音を出しづらいということはないですし、ギターのようにFコードで挫折する、といったこともない楽器です。深く考えずに音を鳴らせるので、"楽しい"が先行していた記憶があります。

――箏のどんなところに魅力を感じたのでしょうか。
僕は当時シャイな子どもで、日本の伝統楽器である箏に、自分の日本人的な要素と重なる面を感じたように思います。
自分がハーフ(父がアメリカ人、母が日本人)ということもあって、日本人なのかアメリカ人なのかとか、自分のアイデンティティに悩んでいた時期だったんです。箏は音自体も大きく派手ではない楽器なので、そんなところも自分のパーソナリティと似ている感覚があって。その後、ドラムやベースなどほかの楽器も触りましたが、一番しっくりきてのめり込んだのが箏でした。

――箏を極めたい、プロになりたいと思ったのはいつ頃でしたか。
中学生くらいからは、この道でプロになれたらいいなと考えていました。僕の家庭は厳しくて、ゲームで遊んでいると「勉強しなさい」「宿題やったの?」とうるさく言われましたが、楽器を練習している時だけは何も言われなかったんですよね。それをいいことに、一日中弾いていた時期があります。小中高一貫の学校で、ずっと箏をやっている上手な先輩を目標に、少しでも練習する時間をつくっていました。
和楽器の世界は、家系を継いで親に倣って始める人が多くて、早いと3歳くらいから始めているので、最初は差を感じました。でもコンクールに出て徐々に成績を残せるようになって、高校生の頃には、その差も埋まってきたなという実感が持てるようになりました。
「くまもと全国邦楽コンクール」以降、舞台でのあがり症を克服
――プロに進むひとつのきっかけが、16歳の時、史上最年少で最優秀賞・文部科学大臣賞を受賞された「くまもと全国邦楽コンクール」だったのではないかと思います。その時の心境はいかがでしたか。
大人が出るコンクールに初出場して、初めて全く緊張せずに舞台に立てたのが印象深いです。コンクールには11歳頃から出ていて、それまで舞台に立つたびにすごく緊張していました。けれど、「くまもと全国邦楽コンクール」では、いい成績を取ろうというよりも、プロを目指している方々の演奏を聴けて、熊本でおいしいごはんを食べて、思い出になればいいな、くらいの感覚で出場したので、気軽な気持ちで舞台に立てたんです。
本番で過度に緊張するあがり症だったのが、このコンクール以降、克服されました。今でも時々緊張はしますが、緊張で押しつぶされそうになるようなことはなくなった。そのきっかけとなったコンクールでもあるので、一番印象に残っています。それから、コンクールの審査員だったレコード会社のプロデューサーに声をかけてもらい、19歳でのメジャーデビューにもつながりました。
デビューアルバム「玲央 1st」
――2017年、19歳でデビューされ、同年に東京藝術大学音楽学部邦楽科に入学されました。そのままプロへ進むという道もある中で、大学への進学を選んだのはなぜですか。
古典の基礎を学ぶためです。僕の所属している流派は、ここ50~80年くらいの新しい曲を弾くことが多く、箏の文化ではもっと昔の曲を弾くのが当たり前という認識があります。邦楽界の方々から認めてもらうには藝大を卒業して、古典の基礎もできているという実績が必要なのではないかと考えました。箏のプロとしてソロで食べていける人はあまり前例がないので、一般的な奏者ができることは全てできた上で、個性がないと生きていけないと思いました。
――大学では、実際にどんな学びがありましたか。
礼儀作法や人間性の面を鍛えられました。インターナショナルスクールって、普通の日本の学校と比べて上下関係がなく、先輩に敬語を使う文化もないですし、先生も下の名前で呼んでいたんです。だから、大学で急に上下関係の厳しい世界に入ったことが一番大変でしたね。
特に入学した時は、誰がどの科の人なのか分からないので、「とりあえず全員に挨拶しなさい」と言われました。知らない人にも挨拶しないといけないのが億劫だなと反抗して、よく怒られていました。でもそのおかげで敬語を使えるようになり、礼儀作法を学べたのは良かったと思っています。

箏の魅力を多くの人に伝えるため、ジャンルを超えた音楽に挑戦
――LEOさんといえば、古典の枠にとどまらない、ジャンルを超えた演奏が印象的です。そうした革新的なスタイルで演奏されるようになった背景を教えてください。
20歳くらいまでは、箏の世界にあるレパートリーとその延長線上のものしか演奏していませんでした。でもそうした演奏をしていると、どう頑張っても邦楽が好きな人にしか届かなかったんです。市場規模も大きくないですし、聴き手の年齢層も高いので、あまり将来性を感じなくて。
僕は元々いろんなジャンルの音楽が好きだったので、その音楽を箏で試してみようと思って始めました。まずは一番親和性がありそうなクラシックから始めて、いろんな技術や知識がついてきたので、最近は箏とは全く結びつかないようなエレクトロニクスと掛け合わせてみたりと、いろんな音楽に挑戦しています。
正直そうしたところで、お客さんが極端に増えるわけではないですが、少しでも多くの人に箏の魅力が伝わればいいなと思っています。
Bach : Cello Suite No.1 in G Major Prelude - Koto cover(LEO) 無伴奏チェロ組曲 第1番 プレリュード
――箏という伝統楽器を広めていく使命感やプレッシャーについて、どのように感じていますか。
若くしてデビューして、当初は上の世代の方々からの期待や、責任を背負っている感覚がありました。もちろん今もそうした感覚はあるのですが、いろいろな経験を重ねて変わってきましたね。
自然体で自分の好きなこと、新しい音楽を作ることを続けていけば、自然と箏の普及にもなる。最終的に僕が弾いているわけで、箏が勝手に鳴っているわけではないですから。僕ありきだからこそ僕の好きなことをやっていこうと、最近はポジティブな考えになりました。

――ジャンルの垣根を超えた、さまざまなアーティストとのコラボレーションも話題ですね。LEOさんにとって、コラボレーションの意義とは何でしょうか。
自分とは違う楽器を弾き、違う人生を歩んできた人と同じ音楽に向き合った時、違った角度からいろんな意見が飛んできて、お互いに刺激をし合えるのが一番の醍醐味です。それとともに自分の引き出しも増えていくように感じています。
1919:LEO(箏)・伊藤ハルトシ(チェロ)・角野隼斗(ピアノ)
多彩なアーティストと実験的なコラボで創り上げた、最新作「microcosm」
――今年7月にリリースされた7枚目のアルバム「microcosm(マイクロコズム)」でも、多彩な音楽家やアーティストとコラボレーションされています。共演者はどのように決めたのですか。
今までは音楽として箏と親和性があるような方に声をかけていたのですが、今回は全く親和性を考えず、ただ普段自分が好きで聴いているアーティストさんに声をかけていきました。例えば、「LAUSBUB(ラウスバブ)」というテクノポップ・バンドとのコラボは、テクノと箏という、過去に曲の前例がない組み合わせなので、どのように作ればいいか互いに分からず、手探りで作っていくような感覚でした。
僕はそれまで楽譜をベースにして作曲していましたが、LAUSBUBさんはDAW(音楽を制作するソフトウエア)で楽曲を制作するので、共通言語も異なりますし。そのあたりは共同プロデュースに入っていただいた網守将平さんにも協力してもらいながら、コミュニケーションを取っていきました。今までのコラボ以上に障壁はありましたが、その分今まで以上の新鮮さを感じられましたね。
今回は箏とコラボさせるというより、自分と相手、人と人とのコラボという感覚が強かったので、曲によっては箏が箏っぽく聴こえないものもあると思います。今までとは違う形で、音楽を通していろんな人とつながれた作品になりました。
microcosm
Vanishing Metro(LEO&大井一彌/produce&music:網守将平)
――アルバムの楽曲を聴いて、斬新で衝撃を受けました。即興的な演奏もあるように感じましたが、曲はどのように制作されたのでしょうか。
曲によっては本当に即興ですね。例えば、1曲目の「Cotton Candy(feat.梅井美咲)」は、何も決めずにスタジオに入って、ピアノと箏だけで約20分の即興を3テイクほど回して、その素材を基に後から梅井さんがパソコンで編集して制作していきました。
「Night Scape」というソロの曲も、ほぼ何も準備せずにスタジオに入って弾いた音源を家に持ち帰って、自分でパソコンでつなぎ合わせるという手法を採っています。逆に、最後の曲「落葉(feat.フランチェスコ・トリスターノ)」は譜面を事前に作ってスタジオに入るという、オーソドックスな方法です。いろんな手法を試しました。
LEO × Francesco Tristano 「落葉」レコーディングMV
――どんな時に聴いてほしいですか。
ドライブや移動中に聴いてほしいです。箏の曲を聴くとなると、静かな時にゆっくり聴く、ヒーリングやアンビエントといったジャンルに寄りがちな気がします。そうではなく、どんなシーンでもかけられる曲があったらいいなという思いで作りました。落ち着くだけじゃない、いろんな感じ方ができるアルバムにしたので、さまざまなシーンで楽しんでもらえたらと思います。
――今年11月5日には、新宿FACE(東京・新宿)にてアルバム発売記念ライブ「LEO - microcosm」が行われました。ステージを客席が360度取り囲むスタイルで、距離が近く、音楽の中に没入するような一体感を味わいました。なぜこの会場を選ばれたのでしょうか。
今回のアルバムやライブの音楽性を考えると、挑戦的なスペースがいいなと思って選びました。360度ステージだとお客さんとの一体感が生まれたり、新鮮な感覚で楽しめるのではないかなと考えました。
――前半がバイオリンとチェロ、後半がシンセサイザーとドラムとのセッションで、アルバム曲を軸としながらも、全く新しい音楽を体感できる豪華な構成でしたね。エフェクターを使い、自然の音や歌声などさまざまな音を取り入れているのも印象的でした。
前半では、自然の音や呼吸のような"生命のリズム"を、電子音やエフェクトと同じ次元で扱うことで、境界のない音世界を描きたいというイメージがありました。扱う楽曲も自然なゆらぎを感じられるものにし、後半との対比としました。
 アルバム発売記念ライブ「LEO - microcosm」前半の様子。左から、中川裕貴(Vc)、LEO(箏)、町田匡(Vn)ⒸRyuya Amao
アルバム発売記念ライブ「LEO - microcosm」前半の様子。左から、中川裕貴(Vc)、LEO(箏)、町田匡(Vn)ⒸRyuya Amao
後半では、箏をひとつのツールとして扱い、エレクトロなサウンドのビートミュージックに箏を介したサウンドが違和感なく乗ることを目標としました。ある意味、箏という楽器を新たな楽器として見つめ直すような感覚で演奏しておりました。
 ライブ後半の様子。左から、大井一彌(Dr)、LEO(箏)、網守将平(Synth)ⒸRyuya Amao
ライブ後半の様子。左から、大井一彌(Dr)、LEO(箏)、網守将平(Synth)ⒸRyuya Amao
普段から多様な音楽を聴く探求心。「音色が面白い曲が好き」
――演奏の際に心がけていることはありますか。
一緒に演奏する相手によって柔軟に対応できるようにしたいと思っています。例えば、本番で相手が思わぬ仕掛けをしてきて、楽譜にないような強弱で遊んできた時に、相手に合わせて、音色や音楽の進み方を変えていく余裕があった方が面白い演奏になります。なので、練習の時はこうしようと決めきらず、手が素直に動く状態になるようにして、あとは本番の時の流れに身を任せる、というようなやり方で曲を仕上げていくことが多いです。
――さまざまなジャンルの音楽とのコラボ演奏は、いろんな音楽を知っていないとできない技だと思います。普段から幅広く音楽を聴かれるのですか。
ジャンルを問わず、とにかくいろんな音楽をインプットするように心がけています。自分がどの方向に進めば、今の時代と親和性のある音楽が作れるのか、ずっと意識していないといけないと思っています。
特に今回のアルバムのように、幅広いジャンルのアーティストとコラボする時には、共通言語がなくて話が膨らまなかったりします。音楽の知見があった方がスムーズにコミュニケーションができるので、普段からいろんな音楽を聴くのは大事なことだなと改めて感じました。
 「本番で演奏している瞬間が一番楽しくて好き」と話す。セッションを通して楽器での対話ができ、お客さんに反応をもらえるのが幸せだという
「本番で演奏している瞬間が一番楽しくて好き」と話す。セッションを通して楽器での対話ができ、お客さんに反応をもらえるのが幸せだという
――LEOさん自身はどんな音楽が好きなのですか。
特にエレクトロミュージックが好きです。いわゆるハウスミュージックみたいな、クラブでかかっているような4つ打ちの曲や、テクノポップなど、ビートのある曲とか。もっと実験的な、聴いたことのない音が鳴っている曲や、音色が面白い曲も好きです。
――それは最近のLEOさんの楽曲にも通ずるものを感じます。作曲する時、曲はどんな場所でどのように生まれるのでしょうか。
お風呂に入っている時が多いです。血行が良くなって頭の回転も良くなり、ほかの余計なことをしていない分、想像に集中できるんですよね。シャワーを浴びながら、ふっとメロディーが思い浮かんだら、すぐにシャワーを止めて、スマホのボイスレコーダーに鼻歌を入れています。
作曲の期間が決まっていて、自然と湧いてくるものに頼っている時間の余裕がない時は、哲学的なアプローチで先にテーマを固めて、それに合う音を探すという方法を採る場合もあります。

箏の可能性を追求し続けるとともに、箏本来の日本的表現を深めたい
――海外での活動についてはどう考えていますか。日本との反応の違いはあるのでしょうか。
何度かヨーロッパや海外で演奏した時は、歓迎いただきました。でも、それは僕の演奏が良かったからなのか、単純に聴きなじみのない珍しい楽器だから面白いねって拍手されているのか、いまいち自分の中で納得できていなくて、ただ拍手をもらっただけでは達成感がなかったんですよね。
自分が作った音楽で拍手をもらえれば、納得がいくんじゃないかなと思います。もちろん古典の音楽も演奏しつつ、海外の好きなアーティストとコラボしたりして、自分のオリジナルの曲も聴いていただいた上で、喜んでいただければ一番幸せだろうなと思います。

――これから挑戦したいことをお聞かせください。
最近はパソコンや電子的な機材を使って、音楽を作る技術を勉強しているので、作曲の幅はもっと広がっていくだろうと感じています。箏と、今までになかった新しい音や聴いたことのないジャンルとの組み合わせを追求し続けたいです。
その半面、そうした活動で精神的に満たされるようになってきたので、昔から大事にされている箏本来の日本的な表現を深めていきたいとも考えています。同世代の和楽器奏者と一緒に、和楽器だけの編成で古典的な音楽を演奏するといった活動も、今少しずつ広げているところです。伝統と革新、両極端なものを持てていると、自分自身がすごく楽しいなって最近気づきました。
――箏の可能性は広がりますね。LEOさんの演奏を聴いて、箏の魅力に気づかされる人も多いと思います。
箏に対する古くておとなしいイメージが払しょくされて、若い世代に魅力が届けばいいなと思います。昔みたいに箏が一般的な習い事として広がったらうれしいですね。
箏の業界は、昔から続いている流派の制度が根強く残っているせいで、横の連携がうまく取れていない現状があります。それがマイナスに作用している部分もあると思うので、同世代や若い世代の奏者たちともっと交流して、一丸となって業界を盛り上げていきたいです。

ヘアメイク:綱島 泰子
――ありがとうございました。ライブ「LEO - microcosm」は、箏の新しさとその場限りのセッションに心奪われるスリリングな時間でした。今後もLEOさんが生み出す箏の革新性と日本らしさ、どちらの世界も楽しみにしています!
◆宮田大(チェロ)×LEO(箏) デュオ・リサイタル
2026年1月17日 @静岡 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
1月18日 @愛知 扶桑文化会館
3月14日 @神奈川 横浜市青葉区民文化センター フィリアホール
3月15日 @山形 山形テルサ テルサホール
3月18日 @富山 高岡文化ホール
3月20日 @大阪 枚方市総合文化芸術センター 関西医大 大ホール
3月21日 @福岡 宗像ユリックス ハーモニーホール
3月22日 @香川 レグザムホール(香川県県民ホール) 小ホール
詳細:https://www.leokonno.com/live/
〈LEOさんコメント〉宮田大さんとは今まで数回ご一緒して演奏していますが、ツアーは初めてです。クラシックの音楽と日本の古典音楽をチェロと箏で演奏します。クラシックも日本の曲も、今回のために新しくアレンジしたものを用意しました。互いに寄り添い、チェロと箏で聴きたい王道の曲が全部聴けるような、とっても心地のいいコンサートになると思います!
※記事の情報は2025年11月25日時点のものです。
-

【PROFILE】
LEO(れお)
箏奏者
1998年、横浜生まれ。9歳より箏を始め、カーティス・パターソン、沢井一恵の両氏に師事。「くまもと全国邦楽コンクール」の最優秀賞・文部科学大臣賞を16歳で史上最年少受賞。2017年、19歳でメジャーデビュー。同年、東京藝術大学に入学。MBS「情熱大陸」、テレビ朝日「題名のない音楽会」「徹子の部屋」など多くのメディアに出演。セバスティアン・ヴァイグレ、井上道義、沖澤のどか、東京フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽団などと共演。2021年、藤倉大委嘱新作の箏協奏曲を鈴木優人指揮・読売日本交響楽団との共演で世界初演。2022年、箏奏者として初めて「ブルーノート東京」や「SUMMER SONIC」にも異例の出演を果たすなど、箏の新たな可能性を広げる活動に注目と期待が寄せられている。出光音楽賞、神奈川文化賞未来賞、横浜文化賞文化・芸術奨励賞受賞。
Official Website https://www.leokonno.com/
X https://x.com/leonokoto
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- 反田恭平|指揮者になりたくてピアノを極めた 反田恭平さん ピアニスト・指揮者〈インタビュー〉
-

- 和田永|役目を終えた家電を楽器に。「祭り性」を追い続けるアーティスト 和田永さん アーティスト/ミュージシャン〈インタビュー〉
-

- シシド・カフカ|el tempoの即興の楽しさを多くの人に知ってもらいたい シシド・カフカさん 歌手・ドラマー・女優 〈インタビュー〉
-

- 弓木英梨乃|マレーシア音楽留学で気づいた、自由にギターを弾く楽しさ 弓木英梨乃さん ギタリスト 〈インタビュー〉
-

- 「幻の楽器」に導かれ、北欧流の「幸せ」を追い求める 山瀬理桜さん バイオリニスト・ハルダンゲルバイオリニスト〈インタビュー〉
NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事
-

- ウィスパー・ヴォイスの歌姫たち(洋楽編) Part2 音楽ライター:徳田 満
-

- ウィスパー・ヴォイスの歌姫たち(洋楽編) Part1 音楽ライター:徳田 満
-

- 冬に聴きたい、しっとりココロ潤うクラシック クラシック音楽ファシリテーター:飯田有抄
-

- LEO|箏の可能性を切り拓く新鋭箏奏者。古典と革新の演奏で箏の伝統をつなぐ LEOさん 箏奏者〈インタビュー〉
-

- 「黄金世代」のソングライター特集。1940~1942生まれの美メロメーカーたち ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ