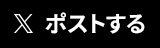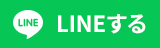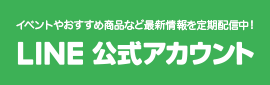音楽
2025.09.02
はいだしょうこさん 歌手〈インタビュー〉
はいだしょうこ|宝塚歌劇団から歌のお姉さんへ。歌が誰かの支えになれるなら、歌い続けたい
明るいキャラクターと、伸びやかで透き通る歌声でお茶の間を魅了するはいだしょうこさん。特に「歌」は自己表現やコミュニケーションの手段として、はいださんにとってなくてはならないものだそうです。童謡歌手、宝塚歌劇団、歌のお姉さん、そして現在に至るまで、はいださんの音楽人生をうかがいました。
写真:松井 康一郎
歌を歌う時だけは積極的だった子ども時代
――幼少期のはいださんと歌との関わりは、どのようなものだったのでしょうか。
父がピアニスト、母が声楽家だったので、家の中はいつも音楽であふれていました。生まれた時からクラシック音楽に囲まれて育ち、音楽はとても身近な存在でした。
私はとても引っ込み思案で、いつも姉や母の後ろに隠れているような子どもでした。そんな私を見た両親が、この子が自分を表現できるものはないかと探していたところ、歌を歌っている時だけは生き生きと自分を表現できていることに気づいたそうです。
クリスマスや誕生日会などでは、父が弾くピアノの周りに家族が集まり、伴奏に合わせて歌うのが恒例でした。その時だけは私もとても積極的で楽しそうにしていたようで、それを見た両親が「全国童謡歌唱コンクール(現・童謡こどもの歌コンクール)」に応募してくれたんです。
そのコンクールは、「ちいさい秋みつけた」や「めだかの学校」などを作曲された中田喜直(なかだ・よしなお)先生が審査員でした。小学3、4年生の頃、コンクール後に「私のコンサートで童謡歌手として歌ってみませんか?」と中田先生に誘っていただいたことが、歌の世界へ足を踏み入れるきっかけとなりました。
――その後、子どもの頃はどんな活動をされていたのですか。
小学5年生の頃から中田先生と一緒に全国を回って本格的に歌い始め、童謡コンサートに「子どもの童謡歌手」として出演したりしていました。宝塚音楽学校に入学する直前の高校2年生まで活動していました。

厳しい規律や上下関係を学んだ、宝塚音楽学校での日々
――宝塚歌劇団を目指されたのはなぜですか。
両親が宝塚歌劇団の熱心なファンで、私も母のお腹の中にいた頃から家族で観劇していたそうです。東京公演の際は、全組の公演を家族で観に行き、出待ちまでするほど(笑)。幼いながらにその華やかな舞台と夢のような世界に魅了され、漠然と「いつかこの舞台に立ちたい」と感じていました。
――童謡歌手の活動と受験準備を両立されていたのですね。宝塚音楽学校の受験は非常に厳しいと聞きますが、大変だったのではないでしょうか。
そうですね。小中高と、土日は童謡のコンサートで忙しく、平日は学校が終わった後にクラシックバレエのレッスンへ向かうという毎日でした。レッスンが終わるのは深夜12時を過ぎることもあり、そこから帰宅して翌日また学校へ行くという、非常に多忙な日々を過ごしていました。
友人たちが学生時代の青春を謳歌している間、私は宝塚受験のためにバレエや声楽のレッスンに打ち込んでいたので、いわゆる「学生らしい青春」はあまり経験できませんでした。しかし、「宝塚に入りたい」という明確な目標があったため、レッスンが苦になることはなく、むしろ「もっとやらなければ」と常に思っていました。
――宝塚音楽学校に入学後、環境が大きく変わったと思います。どんな困難がありましたか。
合格発表から寮に入るまで3日間ほどしか時間がなかったため、両親とゆっくり別れの挨拶をする時間もないまま、慌ただしく準備をして寮生活が始まりました。何より衝撃的だったのは、厳格な規律と上下関係です。のほほんと育ってきた私にとって、その厳しい世界は想像以上でした。
例えば、街中で上級生と思われる人がいたら、とにかく大きな声で挨拶をします。たとえ振り返った方が上級生ではなかったとしても、挨拶はきちっとするように教えられていました。あの方は何組で、今はお稽古が終わった後だから「お疲れ様です」なのか、これからお稽古に向かうから「おはようございます」なのか、といったことを一瞬で判断する必要が当時はありました。常にアンテナを張り、気を配る毎日でした。
――音楽学校のレッスンはいかがでしたか。
レッスンももちろん大変でした。足の皮がむけても踊り続けなければなりませんでしたし、朝の掃除から始まり、日本舞踊やタップダンスなどさまざまなレッスンが続きます。限られた時間の中で、素早く着物に着替えて日本舞踊の授業に向かうなど、短時間で物事をこなす力も求められました。
――辞めたいと思ったことはありましたか。
何度もあります(笑)。寮に入ってすぐの頃、「もう帰りたい」と母に電話したこともありました。母は「自分で決めた道でしょう。40倍もの倍率を突破して入ったのだから、もう少し頑張ってみなさい」と励ましてくれました。
私が実家に少しずつ荷物を宅配便で送っていることに気づいた母は、いよいよ私が追い詰められていると感じたようです。ある日、私がまた「もう帰る」と電話すると、母は「分かった。もう帰っていらっしゃい」と言ったんです。その一言にハッと目が覚めて......。「自分があの舞台に立ちたくて頑張ってきたのに、ここで諦めてはいけない」と強く思い、それ以降、二度と「帰りたい」とは口にしなくなりました。
母の「帰っていらっしゃい」という言葉に、むしろ「待てよ」と気づかされたのです。まだ舞台にも立っていないのに、ここで挫折して帰るのは違うと思い直し、そこから精神的に立て直して、その世界にきちんと順応していくことができました。大人になってからでは身につけられないような厳しさや規律を、成長過程で学べたことは、本当に良い経験だったと思います。

夢が叶った宝塚歌劇団でのエトワール大抜擢
――音楽学校を卒業し、いよいよ歌劇団員になった時のお気持ちはいかがでしたか。
宝塚大劇場の初舞台に立てた喜びは格別でした。のちに各組に配属されるため、同期39名全員で同じ舞台に立てるのはこの初舞台が最後なんです。共に頑張ってきた仲間たちと初めて、そして最後に立つ舞台は、非常に思い出深いです。初舞台で披露するラインダンスのお稽古もとても厳しかったですが、プロとして舞台に立つ責任感をひしひしと感じました。
目が回るほど忙しい日々でしたが、宝塚大劇場の舞台から客席を眺めた時、「ああ、ここが自分の見たかった世界、立ちたかった場所なんだ」と心から感じたことを覚えています。
――宝塚歌劇団で特に勉強になった経験はありますか。
舞台人としての責任の重さを痛感しました。例えば、ソロの歌をいただいた場合、自分の失敗が作品全体に迷惑をかけてしまいます。それは個人の責任ではなく、連帯責任となることもあります。
また、1カ月半の公演期間中、常に安定したパフォーマンスを維持することの難しさも学びました。「この日は上手くいったけれど、次の日は駄目だった」ということは許されません。今日1日しか観劇できないお客様もいらっしゃる中で、体調管理を含め、常に高い水準のパフォーマンスを出し続ける厳しさを経験しました。
それから、下級生として上級生の早替わりを手伝う中で、「どうすればスムーズに舞台に出られるか」を想像し、試行錯誤しながら学ぶことができました。裏で支える側の動きを知ることで、裏方さんやスタッフさんのありがたみ、そして多くの方々の力で舞台が成り立っていることを実感できました。
――配役はどのように決まるのですか。
希望を出すことはできず、演出家の先生が決定します。作品の集合日に配役が壁に張り出され、そこで初めて自分がどんな役をもらえたかを知ります。下級生の頃は役がないことも多いのですが、自分の名前を探して「今回はこの作品のこの場面に出られるんだな」と、その日の朝に分かる、という仕組みです。
――入団4年目でエトワール*に抜擢された時も、そのような形で知らされたのですか。
はい、その時も壁に張り出された配役表で知りました。私が上級生のお手伝いをしている間に、先に見に行った同期が「しょうちゃん、エトワールだよ!」と教えに来てくれたのです。「うそでしょう?」と思って配役表を見に行くと、自分の名前の下の方に、フィナーレの欄に小さく「エトワール」と書かれていました。
* エトワール:オペラでいうプリマドンナに当たる歌手で、いわゆる「歌姫」を指す。宝塚歌劇団では公演のフィナーレで最初に登場し、大階段の中央で、その演目の主題歌などを歌う。
――その時はどんなお気持ちでしたか。
「私がエトワールをやるんだ」と、怖さと興奮で胸がドキドキしたのを覚えています。当時は若くても入団6年目くらいの方が務めるのが一般的でしたので4年目での抜擢は異例でした。正直なところ、喜びは一切なく、「この1カ月半、無事に責任を果たさなければ」という責任感と恐怖、そして「自分にできるだろうか」という不安でいっぱいでした。とにかく、自分の役目をきちんと務め上げなければという思いが強かったです。
私は下級生だったため、エトワールに集中できるわけではなく、直前のラインダンスやほかのナンバーにも出演してから、大急ぎで早替わりをして大階段の上に立ち、フィナーレのトップで歌い始めるという流れでした。踊った直後に息が整うのか、アカペラで歌いきれるのかと心配だったのは母も同じで、母は千秋楽を終えた後、安堵感から緊張が解けて倒れてしまったほどでした。
――宝塚歌劇団を退団されたのは、一つの区切りと感じたからですか。
はい。エトワールを務めたことで、自分の夢が叶ったと感じ、「もうやりきった」と思いました。トップになりたいという気持ちもありませんでしたし、あの歌を歌えたという達成感が非常に大きかったのです。嫌になったからではなく、満足感から「もう辞めよう」と決意しました。
もう一つの夢だった歌のお姉さんへの挑戦

――「歌のお姉さん」のオーディションは600倍もの倍率だったそうですね。受けた経緯を教えていただけますか。
宝塚歌劇団を退団してから3カ月ほどは、エアロビクスに通ったり運転免許を取りに行ったりと、自由な時間を過ごしていました。そんな時、子どもの頃に童謡コンサートでお世話になった、歌のお姉さんから「今度、NHK『おかあさんといっしょ』のオーディションがあるよ。受けてみたら?」と連絡をいただきました。
私自身はもう年齢的に難しいだろうと思っていましたが、宝塚を辞めたのが23歳で、ちょうど大学を卒業する年齢と重なり、タイミングとしては良かったのです。宝塚の受験が先にあったのでそちらを選びましたが、歌のお姉さんも子どもの頃からのもう一つの夢でした。「オーディションがあるなら挑戦してみたい」と思い、受けることにしました。
――オーディションはいかがでしたか。
最終審査に残った方々は音大出身者ばかりで、歌の上手な方が大勢いらっしゃいました。私は「おかあさんといっしょ」という番組が大好きで、宝塚時代も歴代のお姉さんたちをずっと見ていたので、オーディション中も「この方がお姉さんをやったら素敵だろうな」「この方でもいいな」と、自分が受けていることを忘れてしまうほど、ほかの方々のパフォーマンスに見入っていました。自分が受かるとは本当に思っていなかったです。
――合格の決め手は、ほかの受験生の面倒を見ていたことだった、というのは本当ですか。
はい、それは合格してから聞きました。最終審査で6名が控え室にいた時、次に歌う曲の楽譜が配られて、ある方が「どうやって歌えばいいの?」と周りの人に尋ねていました。でも皆自分の試験のことで精一杯で、誰も応じられなかったんですね。私は童謡歌手の経験があって知っている曲だったので、「こうやって言葉を入れて歌うんだよ」と教えていたところ、自分の練習時間を全く取れないまま試験本番になってしまいました。
実は、私たちを試験会場へ案内してくださった方も審査員の1人で、控え室での様子も審査対象だったんです。後日、「歌が上手な方や、お姉さんらしい雰囲気の方はほかにもいたけれど、自分の時間を割いてほかの人に教えてあげていた、その姿が合格の決め手になりました」と教えていただきました。自分のことだけでなく、子どもたちのことも見られるかどうか、という点も見られていたのかもしれないですね。
私自身は、不思議なことに、オーディションでありながらライバルという感覚はあまりなく、むしろ「同志」のように感じていました。自分が同じ立場だったら不安だろうな、と思っただけです。
――歌のお姉さんになられてから、また違うご苦労があったと思います。思い出深いエピソードはありますか。
子どもたちは本当に素直です。宝塚とは全く異なる現場で、最初の1年目はどうしても「お姉さんを演じている」部分がありましたが、子どもたちは、お姉さんが心から楽しんで一緒に遊んでくれているのかを、すぐに見抜いてしまいます。ですから、自分自身が素直な気持ちで、心から楽しむことを常に心がけていました。
実は一度だけ、「辞めます」と言ったことがあります。あるディレクターさんが担当された収録のフィナーレで、泣いている子がいました。その子が「お姉さんと一緒なら行ける」と言ってくれたので、手をつなぎながら片手で踊って収録に参加したところ、ディレクターさんから「両手で踊ってくれ」と注意されたのです。今思えば、テレビの前にいる多くの子どもたちのために、きちんとした振り付けを見せてほしいという意図だったのでしょう。しかし、当時の私には、目の前で泣いている子を放っておくことはできませんでした。
私自身も引っ込み思案な子どもだったので、輪の中に入りたいけれどきっかけをつかめずに不安になっている子の気持ちが痛いほど分かりました。それなのに、「泣いている子は気にしなくていい」というようなニュアンスで言われた時、「私にはできません」と反論してしまいました。「画面の中だけでお姉さんを演じて、目の前で泣いている子を放っておくことはできません。もしそういうお姉さんを求めていたのなら、私ではないと思います」と。
――その時のディレクターさんの反応は?
私がそれまで自己主張をするタイプではなかったので、とても驚いていました。今考えれば、長年番組に携わってこられたベテランの方のプロ意識や、考えも理解できます。しかし当時は、どうしても納得できませんでした。
――収録はほぼ生放送のような形で行われるそうですね。
はい。私たちの時代は、オープニングからエンディングまで一度も止めずに30分間収録する「完パケ」という方式でした。よほどの怪我や体調不良などがない限り、子どもたちの集中力が途切れてしまうため、撮影は止めませんでした。だからこそ、現場でのハプニングも含めて、子どもたちが自由にいられる、あの空気感が生まれるのだと思います。
目の前のことを丁寧に取り組むことで世界が広がっていく
――現在はステージやミュージカル、YouTubeなど幅広く活動されていますが、それぞれ取り組む上で気持ちの違いはありますか。
いただいたお仕事は、どのようなものでも一つひとつ大切に、全力で取り組むことを信条としていますので、活動によって気持ちが大きく変わることはありません。
ただ、YouTubeであれば、コンサートに来たくても来られない方々にも、聴きたいと思ったタイミングで私の歌を届けることができます。それは私にとっても本当にうれしいことです。一方で、コンサートには、その瞬間にしか生まれない生の歌声をお届けできるという、ライブならではの魅力があります。
歌を届けるという本質は同じですが、さまざまな場所や方法で歌わせていただけていることに、心から感謝しています。歌っている時が、一番「生きている」と感じる瞬間です。
はいだしょうこ「ひこうき雲」- 松任谷由実/荒井由実(フル)〈公式〉
YouTubeチャンネル「はいだしょうこの歌とか、、、」では、さまざまなカバーソングを披露
――今後、挑戦してみたいことや目標はありますか。
この年齢になって、これまで点と点だった経験が、ようやく線でつながってきたように感じています。もちろん、上手くいかずに悔しい思いをしたことも数えきれないほどありましたが、それらの点がつながり、今、さまざまな番組やステージにお声がけいただけるようになりました。
特に、ほかの方と一緒に歌わせていただく時間は、自分1人では感じられない化学反応が生まれ、非常に貴重で楽しいものです。
大きな夢に向かって進むというよりは、目の前のことを一つひとつ丁寧にやっていくことで、また何かにつながり、世界が広がっていくのだろうと考えています。ただ、漠然とした夢としては、お世話になった方々や、また一緒に歌いたいと思う方々をお招きして、「しょうこフェス」のようなイベントが開催できたら素敵だな、と考えています。
「あと少しだけ頑張ってみよう」を続けることが、何かを見つける鍵になる
――好きな「歌うこと」を続けてこられた秘訣は何でしょうか。
私の人生には常に歌が寄り添ってくれましたが、それほど好きな歌でさえ、立ち止まったり壁にぶつかったりすることはありました。この世界は、実力も必要ですが、それだけで評価されるわけではありません。タイミングや運、人との出会い、持って生まれた星のようなものも関係してきます。そうした中で、「ここまでやっても認められなかったか」と落ち込むことはありましたし、点数がつけられるものではないからこそ悩むことも多く、「自分は向いていないのかもしれない」「もう辞めた方がいいかもしれない」と思うこともありました。
それでも、歌が好きで、自分で始めた道だから、「あと少しだけ頑張ってみよう」と思い続けてきました。誰かが見てくれているかもしれない、という希望を捨てませんでした。
「辞めるのはいつでもできる」と思っています。もう無理だと感じても、人間には波がありますから、少し休めば「やっぱり歌が好きだ」「歌で届けたい」と思える時が何度もありました。だから、「もう1日だけやってみよう」という気持ちで続けていくことが、何かを見つける鍵になるのではないかと思っています。

――続けてきて良かったと思うのはどんな時ですか。
何より、ライブで私の歌を聴いて涙を流してくださる方がいる。自分の歌が人の心を動かし、誰かの支えになれるのだと実感した時、続けてきて本当に良かったと感じます。
テレビでの姿だけを見ていると「悲しいことなどなさそう」とよく言われます(笑)。しかし、実際にはさまざまな葛藤があります。それでも、私の歌を聴いて元気になってくださる方や、明日を生きる希望を感じてくださる方が1人でもいらっしゃるなら、私は歌い続けたいと思っています。
※記事の情報は2025年9月2日時点のものです。
-

【PROFILE】
はいだしょうこ
歌手
3月25日生まれ。東京都出身。作曲家の中田喜直のもと、幼少期より童謡歌手として全国各地のコンサートを回る。1998年、宝塚歌劇団入団。娘役として活躍。2002年に退団。2003年、NHK「おかあさんといっしょ」第19代うたのおねえさんに就任。2008年、番組卒業後も役者や歌手活動のほか、テレビ番組への出演多数。NHK大河ドラマ「真田丸」に浅井三姉妹の一人の初役として出演するなど活躍の場を広げ、子どもから大人まで幅広い年齢層から人気を集めている。ピアニストの実父と共演しているCD「中田喜直の世界 ほしとたんぽぽ」も発売中。最近では、YouTube「はいだしょうこの歌とか、、、」でも数多くの歌を届けている。
YouTubeチャンネル「はいだしょうこの歌とか、、、」
https://www.youtube.com/channel/UCzswDbWBykQq8CzTaFcM6-g
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- 純名里沙|歌っていない自分は、自分じゃない 純名里沙さん 歌手・女優〈インタビュー〉
-

- 高岡早紀|ゴールが見えないから、面白い 高岡早紀さん 女優・歌手〈インタビュー〉
-

- 中島美嘉|今、歌うのが最高に楽しい 中島 美嘉さん 歌手〈インタビュー〉
-

- アン・サリー|音楽のそのものが持つ美しさを、そのまま歌いたい アン・サリーさん 歌手・医師 〈インタビュー〉
-
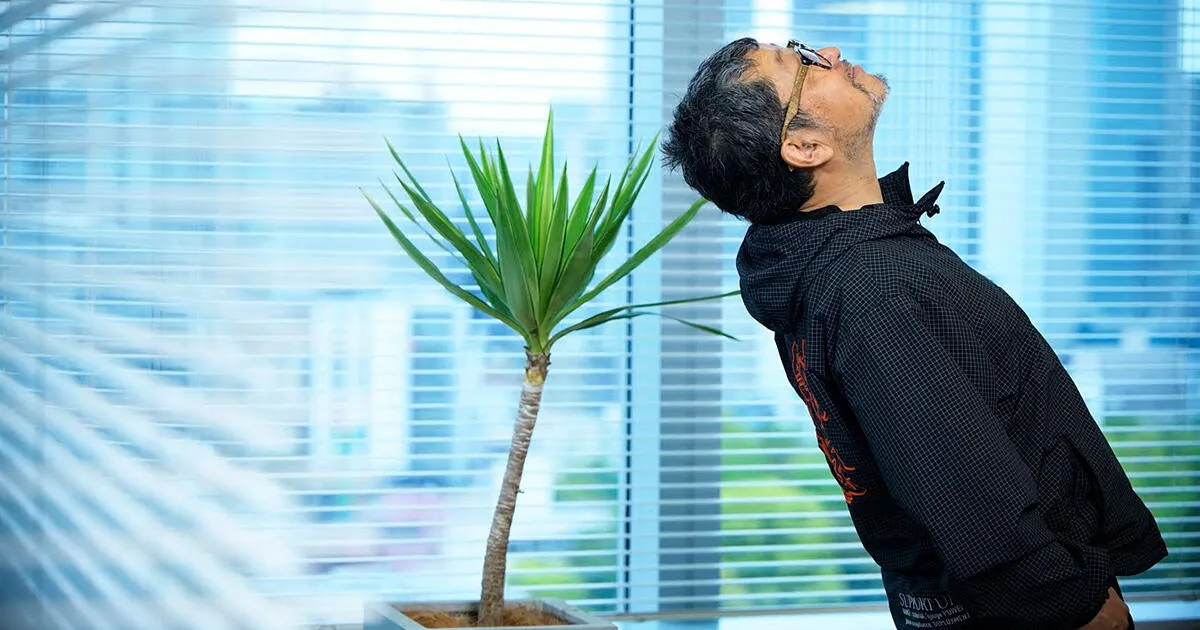
- 大江千里|ニューヨークへのジャズ留学から僕のチャプター2が始まった 大江千里さん ジャズピアニスト〈インタビュー〉
NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事
-

- 冬に聴きたい、しっとりココロ潤うクラシック クラシック音楽ファシリテーター:飯田有抄
-

- LEO|箏の可能性を切り拓く新鋭箏奏者。古典と革新の演奏で箏の伝統をつなぐ LEOさん 箏奏者〈インタビュー〉
-

- 「黄金世代」のソングライター特集。1940~1942生まれの美メロメーカーたち ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ
-

- はいだしょうこ|宝塚歌劇団から歌のお姉さんへ。歌が誰かの支えになれるなら、歌い続けたい はいだしょうこさん 歌手〈インタビュー〉