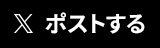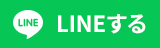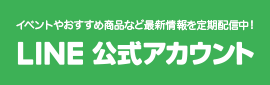【連載】創造する人のためのプレイリスト
2025.08.05
音楽ライター:徳田 満
Singers came from Osaka & Hyogo~極私的 大阪・兵庫出身の唄うたい12選【前編】
クリエイティビティを刺激する音楽を、気鋭の音楽ライターがリレー方式でリコメンドする「創造する人のためのプレイリスト」。ジャズ、ブルースなど多様な音楽文化が育まれた大阪や兵庫にルーツを持つアーティストたちの音源を紹介します。
東京に住んでいるので、盛り上がっているのかどうか今ひとつよくわからないのだが、現在開催中の大阪・関西万博。そして執筆している時点ではプロ野球セントラル・リーグの首位を快走する阪神タイガースと、関西圏は今年の(例年の?)猛暑のようにアツい。
そこで今回は、そんな大阪府および、お隣の兵庫県出身ヴォーカリストを特集(京都や奈良、滋賀など他府県出身者はまた別の機会に)。「なんであの人がいない?」「なぜあの曲がない?」などのご意見もあろうが、「極私的」ということで、ひとつお許しを。ほな、行きまひょか。
〈目次〉
- ウルフルズ「大阪ストラット」(1995年)
- 和田アキ子「古い日記」(1974年)
- 憂歌団「出直しブルース」(1978年)
- ファニー・カンパニー「スウィート・ホーム大阪」(1972年)
- 金延幸子「み空」(1972年)
- BORO「大阪で生まれた女」(1979年)
1. ウルフルズ「大阪ストラット」(1995年)
一発目はやはり、元気のいいところでウルフルズ。大ヒット曲「ガッツだぜ!!」「バンザイ〜好きでよかった〜」以前の通算7枚目となるシングルで、後にアルバム「バンザイ」にも収められたが、まずはこのYouTubeのオフィシャル・ビデオを見てほしい。当時30歳になったばかりのトータス松本(とーたす・まつもと)がいろんなコスプレで1人何役もこなしつつ、今となっては懐かしい新世界など、30年前の大阪の街を闊歩するさまが楽しすぎる。
この曲はもともと、アメリカ・ニューオリンズのR&Bバンド、ミーターズ(The Meters)の「Chicken Strut」(1970年)に着想を得た大瀧詠一(おおたき・えいいち)による「福生ストラット」(1975年)のカバー。当時、ウルフルズをプロデュースしていた伊藤銀次(いとう・ぎんじ)が大瀧の古くからの仲間だったこともあり、大瀧自身が歌詞も書き換え、トータスによる大阪弁のラップも入れて会心のカバーとなった。後半部分にドクター・ジョン(Dr.John)もカバーした「Iko Iko」の「替え歌」が出てくるのも大瀧らしい(ちなみに「待ちきって」という歌詞が出てくるが、これは「待ち合わせして」という大阪弁)。
なお、トータス自身は兵庫県黒田庄町(現在の兵庫県西脇市黒田庄町)出身だが、他のメンバーは全員大阪府生まれで、ジョンB(ベース)は吹田市、サンコンJr.(ドラムス)は茨木市、現在ウルフルズとしての活動を休止しているウルフルケイスケ(ギター)は高槻市の出身である。
2. 和田アキ子「古い日記」(1974年)
ウルフルズの次は、「ダイナマイト・ソウル」の代名詞を持つ、この人に登場してもらおう。
大阪市天王寺区に生まれ、15歳の頃からジャズ喫茶(現在で言うところのライブハウス)などで歌い始めるとたちまち注目を浴び、芸能界にスカウト。「和製リズム・アンド・ブルースの女王」というキャッチコピーで売り出される......といった経歴はあまりにも有名なので割愛する。
この曲は、昭和歌謡の作詞家、安井かずみ(やすい・かずみ)が描く、同棲時代を振り返った1970年代らしい歌詞を、当時流行していたブラス・ロック調のサウンドに乗せたもの。現在では和田アキ子の代表曲の1つだが、物真似だけでなく作品として真っ当に評価されるようになったのは、渋谷系*の流行とともに1960~70年代のR&Bなどが再評価されるようになった1990年代以降のことだろう。
*渋谷系:渋谷を発信地として1990年代に音楽シーンを席巻した日本のポップスのムーブメント。
もし、1990年代に彼女がデビューしていれば、宇多田ヒカル(うただ・ひかる)をも凌ぐヴォーカリスト/アーティストとして、現在とは桁違いな評価を受けていたはずだ。けれど、一般の人がR&Bもソウルも知らなかった時代にそれらを知らしめ、歌謡界において、たった一人でそのジャンルを開拓してきた功績は、いくら賞賛しても足りることはない。
3. 憂歌団「出直しブルース」(1978年)
かつて、「関西は日本のブルース発祥地」と言われていた。確かに、歌謡曲のタイトルで使われる「ブルース」ではなく、マディ・ウォーターズ(Muddy Waters)やハウリン・ウルフ(Howlin' Wolf)といった本場アメリカのブルースは、1970年代前期、関西で盛んに聴かれ、演奏されていた。日本のブルース・バンドの草分け的存在であるウエスト・ロード・ブルース・バンドをはじめ、上田正樹(うえだ・まさき)とサウス・トゥ・サウス、村八分(むらはちぶ)など、その後プロになった関西出身のバンドやアーティストも多い。
中でも憂歌団(ゆうかだん)は、1975年の結成以来、活動休止時期やメンバーチェンジを経ながら、現在も続いている息の長いバンド。よく知られている「おそうじオバチャン」のほか、「嫌んなった」「パチンコ」「胸が痛い」など人気曲も多い。
今回紹介するのは、3枚目のオリジナル・アルバム「四面楚歌」に収められた「出直しブルース」。筆者がこの曲を知ったのは、岡本喜八監督の映画「大誘拐 RAINBOW KIDS」(1991年)で使われていたことから。憂歌団の歌詞は女にふられた自分を憐れむ内容が多いが、これはきっぱりと過去を断ち切って出直すぜ、といった前向きな印象。まさにブルースを歌うために生まれてきたような「天使のダミ声」を有する木村充揮(きむら・あつき、大阪市生野区出身)のヴォーカルも、内田勘太郎(うちだ・かんたろう、大阪市出身)のギターをはじめとする軽快なジャンプ・ブルースの演奏もノリにノッていて、さすがは岡本喜八、よくぞこの曲を見つけてきたなと感心するほどの隠れた名曲だと思う。
4. ファニー・カンパニー「スウィート・ホーム大阪」(1972年)
「西のファニカン、東のキャロル」と言われたのが、2012年に59歳で亡くなった桑名正博(くわな・まさひろ、大阪市天王寺区出身)がいたファニー・カンパニーである。
桑名は江戸時代から続く廻船問屋の御曹司で、当初は音楽活動も遊びのつもりでやっていたという。そのため、貧しい境遇から這い上がった矢沢永吉(やざわ・えいきち)のいるキャロル(CAROL)と並び称されるのが心苦しかったそうだが、持って生まれた資質か、ヴォーカリストとしての実力は、デビュー・シングルとなる、この「スウィート・ホーム大阪」からずば抜けていた。
その後、ソロとなり、1979年に松本隆(まつもと・たかし)と筒美京平(つつみ・きょうへい)という歌謡界のゴールデン・コンビが作詞・作曲を手がけた「セクシャルバイオレットNo.1」がチャート1位を獲得。一躍時の人になるが、業界内やロック、ポップスファンの間では、実妹の桑名晴子(くわな・はるこ)と共に、以前からその歌唱力は高く評価されていたのである。
ちなみにこのタイトル、ブルース好きには説明不要だが、伝説のブルースマンであるロバート・ジョンソン(Robert Johnson)が1936年に発表した「Sweet Home Chicago」を意識している。ただし、この楽曲が制作されたのは、すでに桑名らメンバーが活動拠点を東京に移した後であり、「~シカゴ」では「故郷のシカゴに帰ろう」と歌っているのに対し、「~大阪」では「大阪から出ていく」という真逆の内容になっている。
5. 金延幸子「み空」(1972年)
「スウィート・ホーム大阪」と同じ1972年、大阪市北区生まれの女性シンガー・ソングライターが鮮烈なアルバム・デビューを果たした。金延幸子(かねのぶ・さちこ)である。
憂歌団のところで触れたように、この頃、関西はブルースのメッカだったが、同時に「関西フォーク」と呼ばれるフォーク歌手たちの拠点でもあった。1960年代末期から、高石ともや(たかいし・ともや)、岡林信康(おかばやし・のぶやす)、ザ・フォーク・クルセダーズ、加川良(かがわ・りょう)、高田渡(たかだ・わたる)、遠藤賢司(えんどう・けんじ)など、従来のカレッジ・フォークとは異なる、反戦・反体制などのメッセージ性の強い歌をつくって自ら歌うフォーク・シンガーたちが次々とデビューしていたが、彼らの多くは東京ではなく、大阪や京都などに住んで(または滞在して)活動していた。ただし、実際に大阪出身なのは金延と中川五郎(なかがわ・ごろう)、「五つの赤い風船」のメンバーくらいだった。
金延は1969年、五つの赤い風船の中川イサト(なかがわ・いさと)らと「愚(ぐ)」というフォーク・バンドを結成し、レコード・デビューもしていたが、彼女自身はリード・ヴォーカルを担当しただけで、詞や曲には携わっていない。その本領が発揮されるのは、1972年に細野晴臣(ほその・はるおみ)がプロデュースし、大半の曲を金延が作詞・作曲・編曲・演奏(アコースティック・ギター)した初のソロ・アルバム「み空」である。
現在では名盤との評価が定まっているので多くは語らないが、収録されたすべての楽曲が、「日本のジョニ・ミッチェル」と呼ばれるにふさわしい完成度と輝きを備えている。未聴の方はぜひ一度、その類まれなる歌声に耳を傾けてみてほしい。
6. BORO「大阪で生まれた女」(1979年)
1979年当時、四国在住の中学生だった筆者は毎晩、大阪のラジオ局による深夜放送を愛聴していたが、朝日放送ラジオの「ABCヤングリクエスト」というリクエスト番組で盛んに流れてきたのが、この「大阪で生まれた女」だった。
同年にデビューしたBORO(ぼろ、兵庫県伊丹市出身)の2枚目のシングルで、詞・曲も本人[作曲は岡山準一(おかやま・じゅんいち)との共作]。ただし、最初に発表されたのは萩原健一(はぎわら・けんいち)が歌ったバージョン(同年5月)の方で、BOROの方はそのヒットを受けて8月にリリースされた。
この曲は、以前BOROが大阪の北新地で流しの弾き語りをしていた頃、若い客から「自分たちの歌えるような曲がない」という不満を聞いてつくったものだという。歌詞の内容は、大阪から東京に出ていくという彼氏に自分はついていけないと拒むものの、最終的には一緒に行く女性を主人公にしている(実はこの曲のオリジナルの歌詞は18番まであり、全長34分にもなる大長編だそうだ)。プロコル・ハルム(Procol Harum)の「A Whiter Shade of Pale(邦題は『青い影』)」調のアレンジが施された名バラードである。
筆者は若い頃、なんとなくジメジメとしたこの歌があまり好きではなかったのだが、そうした湿り気があったからこそ、大阪人のみならず多くの日本人に受け入れられたのだろう。この後にやはり大ヒットした上田正樹の「悲しい色やね」(1982年)と並ぶ、大阪を歌ったポップスの代表作でもある。
なお、萩原健一によるライブ・バージョン(複数あり)は、そうした湿気のない、全く別の曲のような趣があるので、機会があればそちらも聴いてみてほしい。
※記事の情報は2025年8月5日時点のものです。
後編に続く
-

【PROFILE】
徳田 満(とくだ・みつる)
昭和映画&音楽愛好家。特に日本のニューウェーブ、ジャズソング、歌謡曲、映画音楽、イージーリスニングなどを好む。古今東西の名曲・迷曲・珍曲を日本語でカバーするバンド「SUKIYAKA」主宰。
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- 歌う女優たち 21世紀篇 音楽ライター:徳田 満
-

- 1970年代・シティポップの歌姫たち 音楽ライター:徳田 満
-

- アナログシンセの名曲・名演・名音 1974~1985年(邦楽編) Part1 音楽ライター:徳田 満
-

- 「ムード歌謡」の系譜 音楽ライター:徳田 満
-

- 日本人がカバーしたジャズ・ソング Part1 音楽ライター:徳田 満
NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事
-

- 冬に聴きたい、しっとりココロ潤うクラシック クラシック音楽ファシリテーター:飯田有抄
-

- LEO|箏の可能性を切り拓く新鋭箏奏者。古典と革新の演奏で箏の伝統をつなぐ LEOさん 箏奏者〈インタビュー〉
-

- 「黄金世代」のソングライター特集。1940~1942生まれの美メロメーカーたち ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ
-

- はいだしょうこ|宝塚歌劇団から歌のお姉さんへ。歌が誰かの支えになれるなら、歌い続けたい はいだしょうこさん 歌手〈インタビュー〉