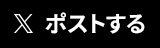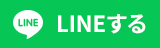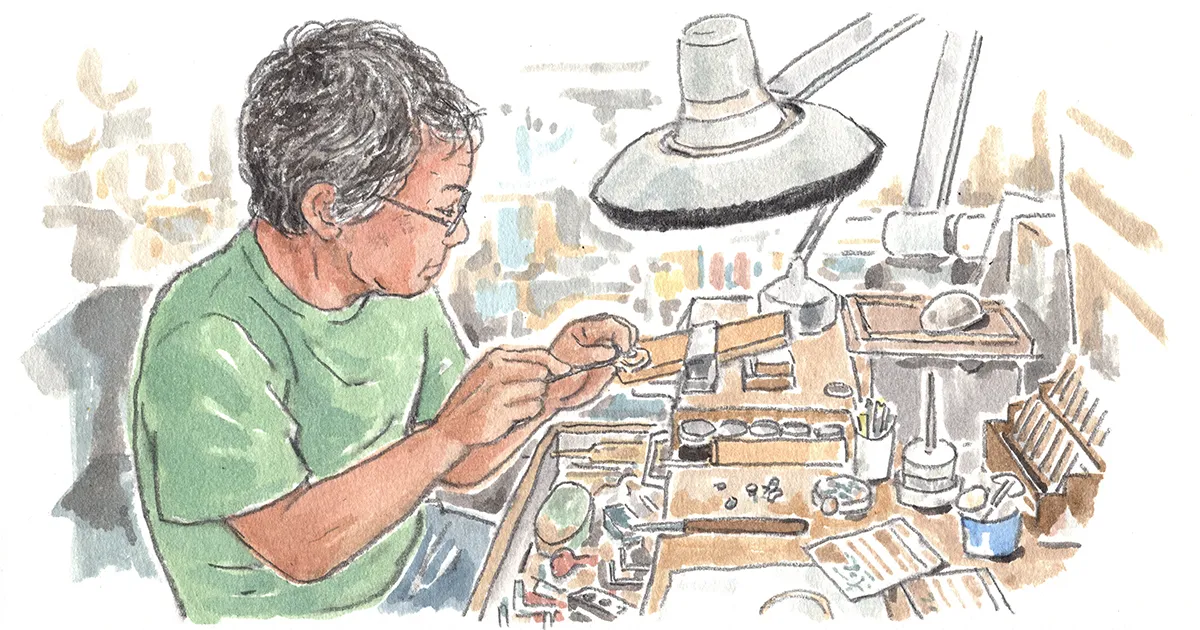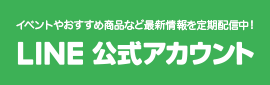【連載】仲間と家族と。
2025.06.24
ペンネーム:熱帯夜
仕事をするということ
どんな出会いと別れが、自分という人間を形成していったのか。昭和から平成へ、そして次代へ、市井の企業人として生きる男が、等身大の思いを綴ります。
イラスト:Hiromichi Ito
昨年(2024年)4月、息子が社会人になった。早いもので1年以上が過ぎたことになる。この連載でもすでに書いたが(記事はこちら)、高校生ぐらいから、将来は小学校の教師になりたいと言い出し、その思いを大学卒業と同時に叶えた。詳細についてはここでは書けないことが多いが、このわずかな期間でも、いろいろなことを経験したようである。
初任で小学校1年生のクラス担任を任された。学生時代に実習を積んだとはいえ実際の現場で働くとなると、教師という仕事について何も分かっていない状態だったと思う。
補助にベテランの先生が付いてくださったようだが、学生と社会人では世界も条件も全く異なる。社会人になるということは全ての責任を負うことになるのだから当たり前である。
でも彼を頼って幼稚園から小学校という未知の世界に入ってきた数十名のクラスの児童たちにとって、息子は他のクラス担任の先生と同じ、担任の先生なのである。1年目だろうが10年目だろうが、児童たちには関係ない。親御さんも、大切な自分の子どもの担任はどんな人なんだろうかと不安も期待もしていただろう。ましてや1年目の教師となれば不安が増すこと間違いなしである。
幸いにも児童や親御さんにも恵まれ、大きな問題もなく1年間を終えることができたようである。ただ一方で自分の社会人としての振る舞いや教育方針については、補助の先生から厳しく指導をされたこともあった。大切なことだと思う。
補助の先生と方針の違いが生じ、行き違いがあり、息子は悩んだ時があった。私には直接相談してこなかったが、少し話ができた時に、いつも彼に伝えてきた「謙虚さとひたむきさ」をもう一度思い出せと伝えた。
息子の意見や考え方があるのは理解できる、ただし大先輩の考えや方針にも学ぶべきことが、とてもたくさんある。だから、いきなり意見を主張するよりも、一旦相手の考え方や方針を素直に聞く気持ちが大切だと彼には伝えた。自分の考えを捨てろとか、持つなという話ではない。
自分よりも40歳以上年上の先輩の経験はやはり敬意を持って聞くべきだと思う。多くの考え方や指導方法を学び、知り、そこから自分の考え方を進化させていくことは、将来にわたって必要だと思うのである。
私も社会人になって2年目ぐらいまでは、一つひとつの仕事についていくのに必死で、自分の考えに沿って仕事をすることはほとんどできなかった。3年目ぐらいから徐々に仕事を1人で任されたり、自分で企画して仕事になった案件については1人で行うように命じられたりするようになった。
そんな仕事でも、先輩や上司から様々な意見や叱責を受けることも多く、自分で回している案件については、時々ムッとくることも多かった。ただ3年目の若輩者が考えることなどたかがしれていて、たいていは先輩のアドバイスが功を奏すことがほとんどだった。悔しい気持ちがありながらも、仕事では結果が出てしまうので、その現実を受け入れるしかない。
その悔しさがいつの間にか、自分の中に多くの考え方や知識となって蓄積されていった気がする。5年、10年と経験を積むうちに、どんどん大きな責任を伴う案件を実施することになるが、その時にそれまでの経験や知識の一つひとつが大きな力となって私を支えてくれたことは間違いない。
息子の仕事と私の仕事は全く異なるので、全てが通じるわけではない。私の携わってきた仕事は、売り上げや利益を上げてこそ自分の仕事の評価が生まれる、そういう仕事だった。息子は教師なので当然売り上げや利益が目的ではない。
子どもたちの人格形成、基礎学力向上、道徳観の醸成、社会で生きるためのルールや振る舞いなどなど、学力にとどまらず、一人ひとりの児童の「人間形成」と言っても過言ではないことが彼の仕事である。当然、評価基準も異なってくる。ただし自分が継続的に進化、進歩していくためには、息子も私も同じような意識や考え方が必要だと感じている。
教育の現場でも研修や研究など、授業以外の自己研鑽の場があると聞く。そのような機会を大きく生かしていくことはもちろん、異なる職業に就いている友人、先輩、後輩との付き合いの中からも広く学ぶことが大切である。常に自分から学ぶことや知ることを心掛けて継続し、素直に自分の中に一度は取り入れてみる、このような姿勢が本当に大切だと思う。
昨今の若い社会人についていろいろと言われていることはあるが、同じ仕事を続けるにせよ、転職で新しい仕事に就くにせよ、自らが起業していくにせよ、自らが動いて、学ぶという姿勢は共通して必要なことだと思っている。昭和生まれの私は古い考えなのだろう。
「石の上にも三年」という言葉もいずれ死語になるのかもしれない。ただ私が経験してきたことから考えると、この言葉には「言い得て妙」と実感する。本当に仕事が面白くなったのが3年目や4年目だったから。面白くなる代わりに辛いことやうまくいかないで悩むことも増えたが、それでも生きていくためには仕事をするということは大切なことの1つである。
だからこそ「自分の仕事」と思えるものと向き合い、格闘し、悩んで、最終的に成果が出た時に得られる達成感や充実感が、次のモチベーションにつながる気がする。それを得られるのは、その時の仕事に真剣に向き合った人間だけなのだと思う。それを経験しだしたのは社会人3年目以降だった気がする。
息子は教師2年目を迎え、今年も小学1年生の担任を任された。去年に引き続き、再度1年生の担任である。ただ今年はサポートをしていただけるベテラン先生はいない。1年目の経験を生かして独り立ちを期待されているのだろう。
当然のことながら、去年の児童と今年の児童は全く異なる人格を持っている。去年うまくいったことが今年通じるかは分からない。息子の向き合う相手はそれぞれが異なり、唯一無二の存在なのである。本当に大変な仕事だと思う。
それでも知恵を振り絞り、心を開き、ありとあらゆる自分という存在で接していかなければならない。日々、息子も仕事をするということ、という課題に向き合っている。
私は会社人生としては終局に入っている。それでも日々、「仕事をするということ」という課題に知らず知らずに向き合っている気がする。どこの組織にもベテラン、若手、中堅という仲間がいる。それぞれがきっと「仕事をするということ」の意義を感じているのだろう。
息子の日々の生き様、それを目の当たりにしながら、私もまだまだ進んでいく。明確な答えは見つからないとは思うが、それでも自分なりの意味を見つけて、人生に彩りを加えていきたいものである。
※記事の情報は2025年6月24日時点のものです。
-

【PROFILE】
ペンネーム:熱帯夜(ねったいや)
1960年代東京生まれ。公立小学校を卒業後、私立の中高一貫校へ進学、国立大学卒。1991年に企業に就職、一貫して広報・宣伝領域を担当し、現在に至る。
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- 夢へ向かって ペンネーム:熱帯夜
-

- 小学校、担任のA先生 ペンネーム:熱帯夜
-
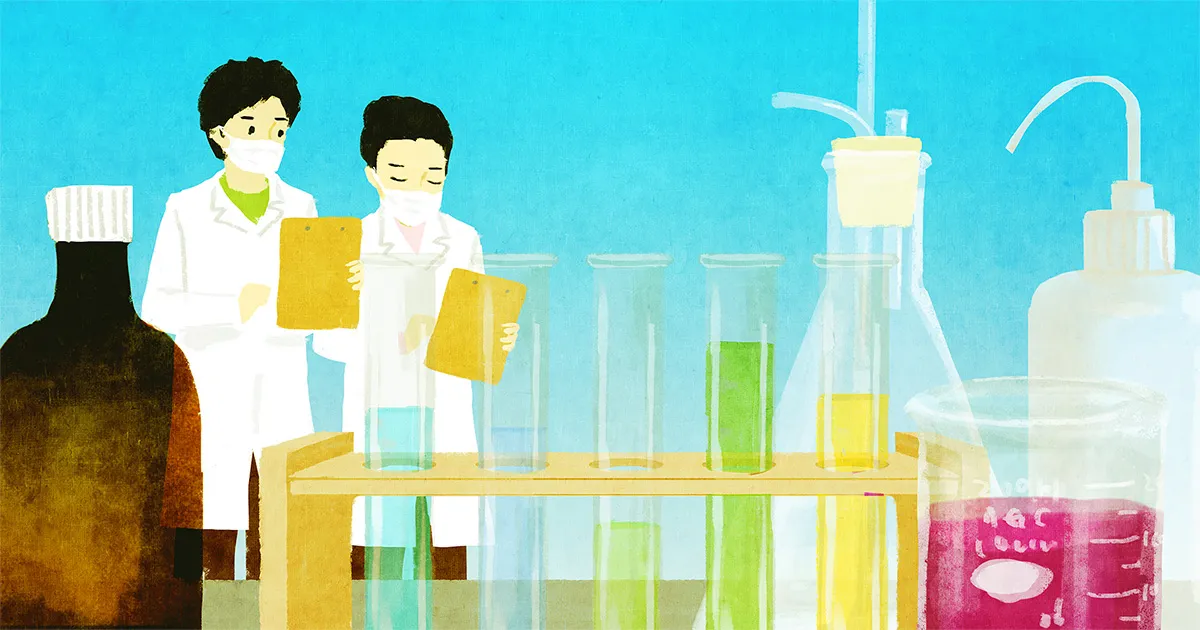
- 大学の研究室 ペンネーム:熱帯夜
-

- 「らしくない」生き方 ペンネーム:熱帯夜
-

- 私を創った人たちへ向けて <今を生きること> ペンネーム:熱帯夜