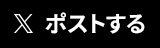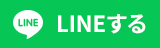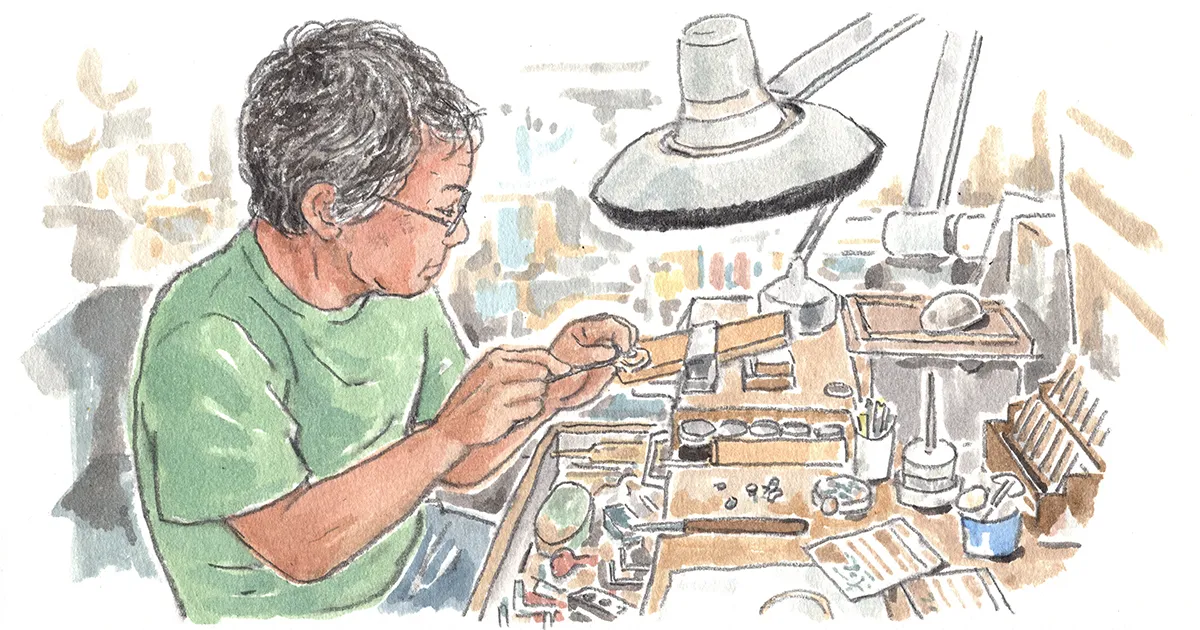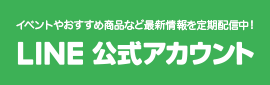【連載】人生100年時代、「生き甲斐」を創る
2025.09.09
小田かなえ
"プレシニア"から始めるシニア暮らし
人生100年時代、「あなた」はどう変わるのか。何十年も前から予測されていた少子高齢社会。自分に訪れる「老い」と家族に訪れる「老い」。各世代ごとの心構えとは? 人生100年時代をさまざまな角度から切り取って綴ります。
イラスト:岡田 知子
高齢者擬似体験グッズとは?
まだ私がとても若かった頃、何かのテレビ番組で「高齢者の動きを体験する」という企画があった。詳細は覚えていないが、脚に重いサポーターなどを装着して階段を上り下りし、出演者が「こんなに動きにくいとは思いませんでした」と驚く。
現代では高齢を疑似体験するグッズも多種多様に揃っていて、小中学校の授業で採り入れているところもあるようだ。難聴の感覚がわかる耳栓、老眼や白内障を体験するメガネ、背中や腰が曲がった状態をつくるリュックやベスト、関節の動きにくさを再現するサポーター。
それらを使ってみた子どもたちは一様に「おじいちゃんやおばあちゃんは大変なんだ」とビックリ。そして、なぜ高齢者が事故に遭いやすいのかを理解し、家の中に危険な場所があれば片付けるようになり、街中でもお年寄りに目配りできる大人に育つのだ。こういった取り組みは介護業界の人材を育成することにもつながるだろう。
ただ上記の場合、子どもたちは元気いっぱいの状態から急に身体が動きにくくなるため、一般的な高齢者の感覚とは少し違うかもしれない。加齢による不具合は、ある日突然襲ってくるわけではなく、ゆっくり進行する。毎日起床して1日を過ごし眠る......その繰り返しを何十年も続けているうちに少しずつ、最初は気づかないほど緩慢に私たちは老化していくのだ。恐ろしや。
この"今まで出来たことが少しずつ出来なくなっていく"という過程、最初のうちは笑い話から始まることが多い。
「このあいだ1㎝ぐらいの段差に躓いたら、近くにいたイケメンの高校生が支えてくれたの」
「それ、わざとじゃないでしょうね?」
こんなのは面白いレベルだが......
「最近よく転ぶのよ、あっちこっちアザだらけ」
この段階になると本人より家族が心配し始める。出かけようとすると「どこへ行くの? 誰と行くの? いつ帰るの?」なんて、気付けばかつて自分が子どもや孫を追いかけ回して聞いていたことを、そのまま言われたりして。
それでも楽しいことを諦めない爺婆たち
しかし人間は楽しいことを諦めない生き物だ。ちょっとぐらい年老いても今まで通り友達に会いたいし、趣味も楽しみたいし、旅行だってしたい。私もあと20年ぐらいは遊びたいなぁと......いや、私のことはさておいて。
そういう"遊び盛りの高齢者"をターゲットにして増えてきたのが、さまざまなツアーである。近場の日帰り温泉から豪華客船で行く世界一周まで、それぞれのフトコロ具合や忙しさによって選べる。私もいくつか取材(と称して遊び半分)で参加してみた。いずれ近い将来訪れる本格的なシニア生活の予行演習、高齢者擬似体験の一環だ。
たとえば大人気の温泉バスツアー。目的地によって違いはあるが、基本的には自宅から行きやすい出発地を選んで申し込む。往復交通費込みの2食付きで1泊7,000円前後とリーズナブル。食事は朝夕ともバイキングだがオプションで別料理を頼めるところも多い。部屋はホテルによってさまざまなタイプが用意されており、老舗旅館をリフォームした宿などは豪華な貴賓室があったりする。
特筆すべきは、高齢者を意識したサービスの数々だ。カラオケルームはもちろん、ダンスホールがあったり麻雀卓がたくさん用意されていたり。知人は毎月のように2泊3日の麻雀ツアーに参加しているが、自宅に近いターミナル駅からの送迎バス、天然温泉の大浴場とバストイレ付きの客室、食事も朝晩4回用意され、なんと2万円でお釣りが来るという。
また、無料でお芝居や歌謡ショーが楽しめるプランもある。月替わりでいろいろな劇団が登場し、あまり観る機会のない人情時代劇などを上演してくれるのだ。こちらも何度か回を重ねるうちに贔屓の役者ができたりして、旅行プラスαのお楽しみが味わえる。
この手のツアーは参加者の年齢層が近いため(言わずと知れたオバさん&お婆さんと、その配偶者や友達の男性陣)、何度も行くうちに顔見知りができるようだ。
「あら、また会えたわねぇ!」
「お元気でした?」
そんな会話が夕食会場や大浴場、お芝居の合間に聞こえてきて、無関係な私まで和気あいあいとした雰囲気に癒やされる。
そのような格安ツアーのほかにも「75歳以上限定ツアー」や「歩かないツアー」など、後期高齢者をターゲットにした各種多様なプランが次々と企画されていて心強い。
さらに増えてきたのがユニバーサルルームのある宿だ。こちらはツアーではなく個人でも予約できるので、ポイントが溜まっている旅行サイトで探してみた。もちろん季節はずれの平日をチョイスする(本当にユニバーサルルームを探している人たちに迷惑をかけてはいけないからね)。
そうして予約した初めてのユニバーサルルームは、中部地方のホテルだった。部屋に案内され、その広さに感動。客室内に段差がないのは当然として、 ツインベッドの間隔、トイレのドアの開閉など、車椅子でストレスなく動ける仕様になっている。
私が泊まった部屋は安全のため浴室の壁が透明で、高齢者だけでなく子連れの家族にも安心だ。さらに部屋の定員が多いところや愛犬と泊まれるところも増えてきて、家族みんなで旅行できるのはうれしい限り。
また、ユニバーサル仕様ではないが、準バリアフリールームが何部屋かあるホテルにも泊まってみた。完全なバリアフリールームと比較すれば動線の広さなど物足りなく感じる部分もあるが、部屋数が比較的多く用意されているため、急に思い立って旅行する際に予約しやすくて便利だと思う。
なお、私はお願いしなかったが高齢のお客さんへのおもてなしを重視している宿のなかには、柔らかい刻み食などの注文に応じてくれるところもある。これらの点を予約時に確認しておけば、より安心して旅行プランが立てられるだろう。余談だが、ヘルパーさんや看護師さんが付き添ってくれるサービスもある。それもアタマの片隅にメモしておこうと思った。
ところでプレシニアって何歳から?
先日、友人に「プレシニアって何歳から何歳までなの?」と聞かれた。別に私をシニア問題の権威だと思っているわけではなく、単なるランチの雑談である。
この答えは幅広い。ザックリ言うと、下は50歳、上は64歳の間の一部を区切ってプレシニアと呼ぶことが多いようだ。なぜ区切りが曖昧なのかというと、プレシニアを語るテーマよって対象年齢が変わるから。
たとえば、マーケティングの世界でプレシニアというと、団塊ジュニアの50歳から60歳を指すことが多い。高齢の親を持つこの世代は企業にとって重要なターゲットで、さまざまな経済戦略に役立っている。
ひとつ例をあげると、若い人たちの認識として"お年寄りは和室のほうが好き"というイメージがあったが、これは間違いだ。プレシニアたちは50歳を過ぎたあたりでそれに気づく。「膝が痛いと正座できない」「畳に布団を敷くよりベッドのほうがラク」等々。
そして親たちの生活を見直しはじめる。覚えている方もいらっしゃると思うが、昭和の年寄りたちは、正座した時に自分の体重が膝にかからぬよう工夫された補助椅子を使うことがあった。これは今でも販売されているから、座敷で生活している両親にプレゼントすると喜ばれるかも知れない。
......と、まあそんな感じで、高齢者に優しい世界を創造するには、お年寄りの生活の不便さを体験してみるのが手っ取り早い。
ということで、話を最初に戻そう。機会があったら、ぜひ高齢者擬似体験にチャレンジしていただきたいのだ。
学校やサークル単位で高齢者の擬似体験ができれば簡単だが、そういう機会がない場合は、高齢者擬似体験器具を貸し出している市町村や団体もあるので調べてみても良いだろう。祖父母のため、あるいは自分が年老いた時のため、さらには地域社会での非常時対応や今後のビジネスにも役立つに違いない。
※記事の情報は2025年9月9日時点のものです。
-
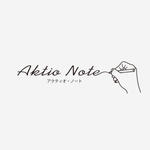
【PROFILE】
小田かなえ(おだ・かなえ)
日本作家クラブ会員、コピーライター、大衆小説家。1957年生まれ、東京都出身・埼玉県在住。高校時代に遠縁の寺との縁談が持ち上がり、結婚を先延ばしにすべく仏教系の大学へ進学。在学中に嫁入り話が立ち消えたので、卒業後は某大手広告会社に勤務。25歳でフリーランスとなりバブルに乗るがすぐにバブル崩壊、それでもしぶとく公共広告、アパレル、美容、食品、オーディオ、観光等々のキャッチコピーやウェブマガジンまで節操なしに幅広く書き続け、娯楽小説にも手を染めながら、絶滅危惧種のフリーランスとして活動中。「隠し子さんと芸者衆―稲荷通り商店街の昭和―」ほか、ジャンルも形式も問わぬ雑多な書き物で皆様に“笑い”を提供しています。
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- あっちにもこっちにも遊び盛りの先輩たち! 小田かなえ
-

- さて、100歳になる準備はOK? 小田かなえ
-
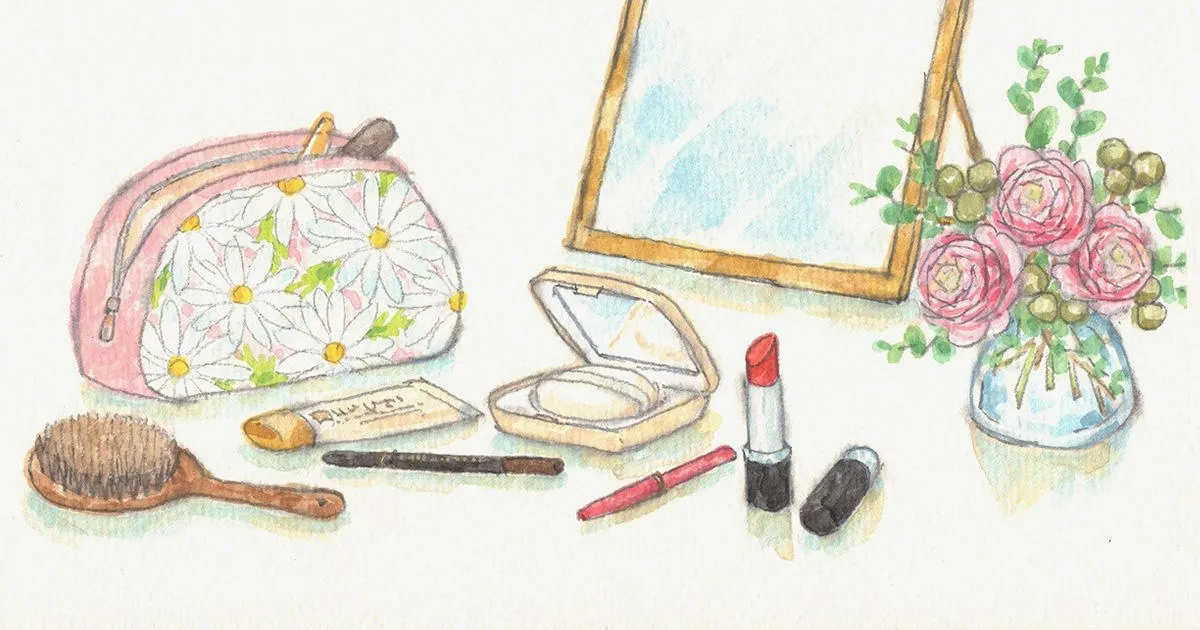
- 老後を楽しく心地良く! 秘訣は小さなお洒落心 小田かなえ
-

- モビリティジャーナリスト・楠田悦子さんが語る、社会の課題を解決するモビリティとそのトレンド 楠田悦子さん モビリティジャーナリスト〈インタビュー〉
-

- 「新しい常識」をつくる革新的な近距離モビリティ。ポジティブに移動する人を増やして、社会全体を元... 菅野絵礼奈さん 小松岳さん WHILL株式会社〈インタビュー〉