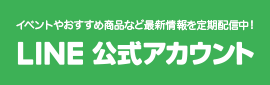【連載】創造する人のためのプレイリスト
2024.10.08
音楽ライター:徳田 満
アナログシンセの名曲・名演・名音 1974~1985年(邦楽編) Part1
クリエイティビティを刺激する音楽を、気鋭の音楽ライターがリレー方式でリコメンドする「創造する人のためのプレイリスト」。今回は、日本で「アナログシンセ」を使った音楽が一気に花開いた、1970年代中期~1980年代前半までの名盤を紹介します。
カバーフォト:Peter Csotonyi/Shutterstock.com
2023年10月に「アナログシンセの名曲・名演・名音 1967~1979年(洋楽編)」を紹介したが、今回はその邦楽編。1970年代中期から1980年代前半までを取り上げる。
この時期はロック、ポップス、ジャズ、映画・テレビ番組の主題歌(テーマ曲)やBGM、CM音楽など、日本でアナログシンセを使った音楽が一気に花開き、そこかしこで流れていた。ちょうど筆者が10代を過ごした頃でもあるので、「極私的アナログシンセの名曲・名演・名音」だとも言える。
では、今回も魅惑的でレトロ・フューチャーな、アナログシンセの時間旅行にご招待しよう。
1. 冨田 勲「月の光」(1974年)
日本のシンセサイザー音楽を語る上で、触れないわけにはいかない作品。そう、冨田勲(とみた・いさお)が「世界のトミタ」となるきっかけをつくったのが、この「月の光」である。
「洋楽編」で書いたように、シンセサイザーが楽器として使えるようになったのは1960年代後期で、当初はモーグ(Moog)社のバカでかい「モジュラー・シンセサイザー(Modular Synthesizer)」しかなかった。
だが、すでに映画・テレビ音楽の分野で名を成していながらも、常に新しい音を追求していた冨田は、1971年、そのタンス状の「モーグⅢ-P(MoogⅢ-P)」を果敢にも個人輸入したのである(羽田空港の税関で「これは楽器ではない」と判断され、1カ月も受け取れないなどのトラブルに見舞われながらも)。
冨田はその後、半年以上をかけて、マニュアルすらろくにないモーグⅢ-Pの機能をマスター。その成果が「月の光」をはじめとする、世界的に評価されている一連のシンセサイザー作品だ。
「月の光」はフランスの印象主義音楽の作曲家・ドビュッシーのカバー。旋律は原曲そのままながら、こだわり抜いた音色と巧みなエフェクター使いによって、まるで宇宙空間にいるような幻想性と空間的な広がりを感じさせてくれる。その素晴らしさは、発表から半世紀が経過した現在でもまったく揺るぎない。日本のシンセサイザー音楽は、まさにここから始まったのである。
2. 深町純と21stセンチュリーバンド「六喩」(1975年)
日本のジャズ・ミュージシャンもシンセサイザーに注目するのは早かった。ピアニスト、キーボーディストの佐藤允彦(さとう・まさひこ)は、冨田勲よりも早い1970年、発売されたばかりの「ミニモーグ(Minimoog)」を個人輸入。その翌年にはミニモーグで多重録音したレコードを発表している。だが、「洋楽編」でも触れたように、70年代初期に作られたシンセは機種が限られ、操作も難しかったため、再現性やライブでの使用には不向きだった。
70年代中期になると、ジャズの世界では電気・電子楽器の導入とともに、ロックやラテン音楽を取り入れた「クロスオーバー」や「フュージョン」と呼ばれるスタイルが台頭してくる。「洋楽編」で紹介したアジムス(Azymuth)の「フライ・オーバー・ザ・ホライゾン(Fly Over The Horizon)」もそうだが、ここで取り上げる「六喩(ろくゆ)」も、アナログシンセが大活躍するクロスオーバー、フュージョンの隠れた名盤である。
深町純(ふかまち・じゅん)自身は、ジャズというよりプログレッシブ・ロックに近い音楽を志向していたが、シンセサイザーの造詣も深かった。特にこのアルバムではミニモーグのほか、「アープ・オデッセイ(ARP Odyssey)」や国産の「YAMAHA SY-11」などの各種シンセを駆使。村上秀一(むらかみ・しゅういち)や大村憲司(おおむら・けんじ)、小原礼(おはら・れい)、浜口茂外也(はまぐち・もとや)といった凄腕ミュージシャンたちと怒涛のようなセッションを繰り広げている。
やがて1980年代になると、カシオペア(CASIOPEA)やザ・スクエア(THE SQUARE)といったフュージョン・バンドが人気を博すようになり、シンセはギターとともにソロも受け持つ、花形パートとなっていくのである。
3. 坂本龍一「ダス・ノイエ・ヤパニッシェ・エレクトロニッシェ・フォルクスリート」(1978年)
1978年、「シンセサイザーの申し子」とでも呼ぶべきミュージシャンが登場する。坂本龍一(さかもと・りゅういち)である。
坂本は東京藝術大学および同大学院でアカデミックな音楽を学ぶ一方、現代音楽としての電子音楽も研究していた。またアルバイトでスタジオ・ミュージシャンもやっていたため、そこでもシンセに触れていた。
そうした資質と志向が結実したのが、この「DAS NEUE JAPANISCHE ELEKTRONISCHE VOLKSLIED」が収められたファーストアルバム「千のナイフ(Thousand Knives)」である。
このアルバムは、これまでに紹介したモーグⅢやミニモーグ、アープ・オデッセイのほかにも、ポリフォニック(和音)の出る名機「オーバーハイム8(Oberheim 8)」、コルグ(KORG)の国産シンセやボコーダー(声を模倣するシンセ)など、シンセサイザー・マニピュレーター、オペレーターの松武秀樹(まつたけ・ひでき)と坂本が所有する全てのシンセを録音スタジオに持ち込み、長時間かけて多重録音を繰り返し作られた。
高橋悠治(たかはし・ゆうじ)とのアコースティック・ピアノ連弾による「Grasshoppers」以外の全曲でシンセが主役を務めており、ベースやドラムスの音も全てシンセで作り出されている。坂本による手弾きに加え、前年の1977年に発売された、国産メーカー・ローランド(Roland)の「MC-8」というシーケンサー(コンピューター)を用いた自動演奏が随所で聴かれるという意味でも画期的だった。
筆者がこのアルバムを初めて聴いたのは、坂本の参加したイエロー・マジック・オーケストラ(Yellow Magic Orchestra=以下、YMO)が大ブレイクした1980年のこと。YMOを聴き慣れた耳でも独特のサウンドという印象で、何度繰り返して聴いてもまったく飽きることがなかった。おそらくその理由の一つは、この曲のように、前述した多種多様なシンセが巧みな構成やユニークなリズムとともに展開する音の面白さにあるのだろう。
4. ゴダイゴ「西遊記」(1978年)
冒頭で、テレビ番組でもアナログシンセを使った音楽が流れていた、と書いたが、その最たるものが、この「西遊記」である。
50代以上の読者には説明不要だろうが、1978年10月から翌年4月にかけて放映されたテレビドラマ「西遊記」は爆発的大ヒット番組となった。当時中学2年だった筆者も、もちろん毎週欠かさず観ており、本編のドラマ以上に好きだったのが、ゴダイゴ(Godiego)による主題歌「Monkey Magic」である。全編英語詞というのも画期的だったが、とにかくサウンド、アレンジが素晴らしい。
まず、冒頭で天地創造から孫悟空が誕生するまでの場面に流れる前奏「The Birth Of The Odyssey」はMC-8の自動演奏による低音の変拍子リフとシンセソロ。さらに、高音のリフ、中国風のフレーズがおっかけで流れるイントロから歌のパートへと続くと、シンセのオブリガートやギターのカッティングが絶妙なタイミングで入ってくる。それ以前はもちろん、以後も、筆者はこんなにカッコいいドラマの主題歌を聴いたことがない。
よく知られているように、ゴダイゴのリーダー・ミッキー吉野は、ザ・ゴールデン・カップス(THE GOLDEN CUPS)などでの経験やバークリー音楽大学への留学など、テクニックにも知識にも秀でたキーボーディストだが、シンセの音色選びやフレーズの決め方・入れ方のセンスも群を抜いている。こうしたミッキー吉野の、シンセストとしての再評価も高まってほしいと思う。
なお、このアルバムは、奇しくも前述の「千のナイフ」と同じ日(1978年10月25日)に、同じレコード会社(日本コロムビア)から発売されている。シンセが大活躍する1980年代が、すぐそこまで来ていた。
5. プラスチックス「コピー」(1980年)
1980年代が始まった。日本の音楽シーンはYMOに代表されるテクノ・ポップ・ブームの只中にあった。その中で「テクノ御三家」と呼ばれていたのが、P-MODEL、ヒカシュー、プラスチックス(PLASTICS)である。
P-MODELはリーダーの平沢進(ひらさわ・すすむ)がプログレッシブ・バンド出身だったこともあり、デビューアルバムから演奏技術も作品もハイレベルだった。また、ヒカシューは後編で紹介する井上誠(いのうえ・まこと)と山下康(やました・やすし)によって母体がつくられ、その後、巻上公一(まきがみ・こういち)などが合流。巻上の独特の(クセの強い)ヴォーカルが強い印象を残すバンドで、メンバーチェンジを繰り返しながら現在も続いている。
その中で最もテクノっぽいというかユニークだったのが、今回紹介するプラスチックスである。というのも、このバンドにはドラムスもベースもいないのだ(結成当初など短期間いた時期もある)。
この画質の悪い公式動画(当時のPV=プロモーションビデオ)で観られるのが一番長く続いた編成で、ミュージシャンとしてキャリアがあったのは元・四人囃子のキーボード・佐久間正英(さくま・まさひで)だけ。しかも彼の本来の担当楽器はベースで、あとはイラストレーターにグラフィックデザイナー、ファッションスタイリスト、作詞家という素人集団である。
ドラムスはPVの頃はリズムボックス(ローランドのCR-68または78)を代用していたが、非常にチープな音。またギター担当の立花ハジメも難しいことはできないので、必然的にメイン楽器はシンセ(同じくローランドのSH-1やSYSTEM-100M)となる。それが逆に個性として評価されたのだろう、プラスチックスは日本より早く、1979年にイギリスでシングル盤デビュー。その曲がこの「COPY」である。
のんきなリズムとシンセの単純なリフに乗って、この世にオリジナルなんて存在しない、あるものはコピーだけという(特に日本人にとって)非常にシニカルな歌詞が、音楽専業ではない、つまりいつやめてもいいと思っている男女によってあっけらかんと歌われる。そうした、それまでの音楽(業界)へのアンチ的な佇まいは、確かにこの時代、とても新鮮に見えた。
6. 喜多郎「シルクロード」(1980年)
多くの日本人がシンセサイザーという楽器を認識したのは、ここからかもしれない。そう、1980年4月から放送された「NHK特集 シルクロード」のテーマ曲がこれである。
喜多郎(きたろう)の本名は、プログレッシブ・バンドのファー・イースト・ファミリー・バンド(Far East Family Band)のメンバー、高橋正則(たかはし・まさのり)。1970年代初めの海外レコーディング時に、ドイツのシンセサイザー奏者であるクラウス・シュルツェ(Klaus Schulze)と出会ったことで、シンセに魅了されたという。
そもそも、「洋楽編」で紹介したように、プログレとシンセはとても結びつきやすい。それは、シンセの音色が壮大で幻想的な世界観を表現できるからだろう。日本でもフラワー・トラベリン・バンド(Flower Travellin' Band)やコスモスファクトリー(Cosmos Factory)、前述の佐久間正英がいた四人囃子、平沢進がいたマンドレイク(Mandrake)などが、他ジャンルのロックバンドに先駆けて、70年代にシンセを取り入れている。
高橋正則は1978年、バンドを脱退して喜多郎と改名、アルバム「天界」でソロ・アーティストとしてデビュー。その2年後がこの「シルクロード(絲綢之路)」なので、順調な道のりで認められたと言えるだろう。彼は人里離れた山中などで暮らしつつ制作をしてきたわけだが、確かにその音楽性は瞑想を連想させる、インナー・スペース(内宇宙)的なもので、聴いていると非常に心地よい。
筆者は、今回初めて喜多郎の音楽をじっくり聴いてみて、自分がアナログシンセ(ローランドのJUNO-106)を買った当初の頃を思い出した。もちろん規模は天地ほど違うが、部屋の電気を暗くし、ヘッドフォンを着けてシンセを弾いていると、こうしたメディテーション的な陶酔感に浸れるのだ。その意味では、喜多郎の音楽は、アナログシンセへの原初的な衝動を保っていると言えるかもしれない。
(参考資料)
・田中雄二 著「電子音楽 in JAPAN」(アスペクト、2001年)
・美馬亜貴子 監修「THE DIG PRESENTS DISC GUIDE SERIEDS TECHNO POP」(シンコーミュージック、2004年)
・松武秀樹 著「松武秀樹とシンセサイザー「限定愛蔵版」 MOOGⅢ-Cとともに歩んだ音楽人生」(DU BOOKS、2015年)
・コラム「シンセサイザー鍵盤狂 漂流記 ~音楽を彩った電気鍵盤とシンセ名盤の数々~ その81」(サウンドハウス公式サイト、2022年)
・各作品CD盤解説
※記事の情報は2024年10月8日時点のものです。
後編に続く
-

【PROFILE】
徳田 満(とくだ・みつる)
昭和映画&音楽愛好家。特に日本のニューウェーブ、ジャズソング、歌謡曲、映画音楽、イージーリスニングなどを好む。古今東西の名曲・迷曲・珍曲を日本語でカバーするバンド「SUKIYAKA」主宰。
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- アナログシンセの名曲・名演・名音 1967~1979年(洋楽編) 音楽ライター:徳田 満
-

- 日本が世界に誇るテクノポップ、その創作の秘密 音楽ライター:徳田 満
-
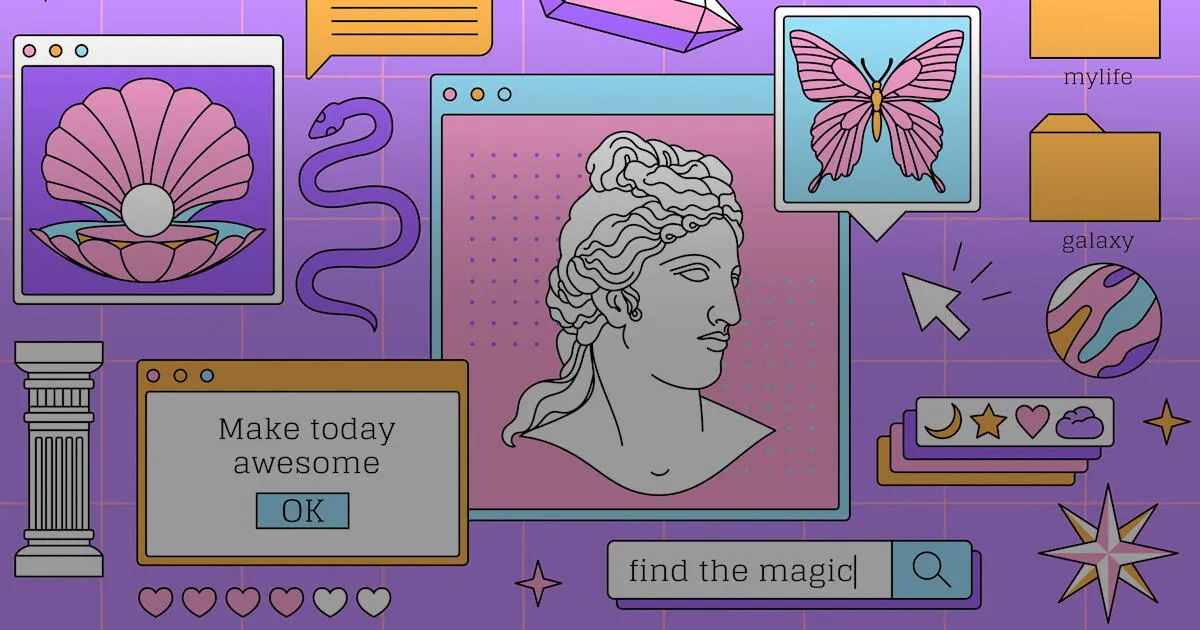
- ネットのコミュニティーから生まれた新たな音楽ジャンル「ヴェイパーウェイヴ」とは何か スーパーミュージックラバー:ケージ・ハシモト
-

- 1970年代・シティポップの歌姫たち 音楽ライター:徳田 満
NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事
-

- 冬に聴きたい、しっとりココロ潤うクラシック クラシック音楽ファシリテーター:飯田有抄
-

- LEO|箏の可能性を切り拓く新鋭箏奏者。古典と革新の演奏で箏の伝統をつなぐ LEOさん 箏奏者〈インタビュー〉
-

- 「黄金世代」のソングライター特集。1940~1942生まれの美メロメーカーたち ミュージック・リスニング・マシーン:シブヤモトマチ
-

- はいだしょうこ|宝塚歌劇団から歌のお姉さんへ。歌が誰かの支えになれるなら、歌い続けたい はいだしょうこさん 歌手〈インタビュー〉