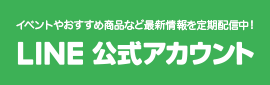【連載】人生100年時代、「生き甲斐」を創る
2019.05.14
小田かなえ
人と人がつながって伝わる、懐かしの「味」
少子高齢社会となった日本で、共同体の最小単位『家族』はどこへ向かうのか。「すべてのお年寄りに笑顔を」と願う60代の女性が、超高齢の母との生活を綴ります。
イラスト:岡田 知子
アジの開きは骨まで美味しく食べましょう。
つい先日、知り合って間もない友人たちと旅行したときのこと。朝食に定番のアジの干物が出てきた。そのアジを美味しくいただいてふと目をあげたら、私の顔と手元のお皿を、友だち三人の視線が行ったり来たりしている。
「なに?」
「あんた、アジの骨とアタマはどうしたの」
「食べたけど」
みんなのお皿を見たら案の定ちゃんと尾頭付きで骨が残っていて、私のお皿には目玉がふたつ転がっているだけだった。
私が育った家では、昔から干物の骨やアタマを全部食べるのが当たり前だった。小さめのアジならそのままかぶりつく。大きいアジやサンマの骨、鮭の中骨などは、身を食べ終わったあとにもう一度こんがり焼き直して香ばしさを味わう。明治生まれの祖母が考案したカルシウム補給の手段である。
味噌汁などのダシに使った煮干しも具として食べる。豆腐と煮干し。ワカメと煮干し。お麩と煮干し、大根と煮干し......私の子ども時代に食べさせられた味噌汁の具だ。
「かなえちゃん、煮干しも食べなさいよ」
「うん......」
しんなりと柔らかくなった出がらしの煮干しだが、まぁ美味しいと言えなくもなかった。
もっと堅い魚の骨はどうするかというと、「ミンサー」の出番である。よく焼いてからミンサーまたはミキサーで細かく砕き、ゴマや鰹節と混ぜてふりかけにする。自家製のふりかけを作る家庭は多いので、こちらはさほど珍しくないだろう。
母が育った東京の下町には「どんどん焼き」というおやつがあった。昭和初期に屋台で売りに来て、客を呼び集めるために太鼓をドンドン鳴らしたのが名前の由来である。
「昔のどんどん焼き屋さんってね、新聞紙を三角に折ったところに入れて売るのよ」
母はよくそう話してくれた。子供ごころに、古新聞に包んで売るのはずいぶん不衛生だなあと思ったものだ。
私が知っているのは自家製の「どんどん焼き」で、小麦粉を水に溶いて、千切りのキャベツと桜エビ、切りイカ、紅ショウガを入れて混ぜ合わせる。そこにミンサーで砕いた魚の骨を加えて焼くのだ。お好み焼きに似ているが生地をふんわり厚くせず、薄べったくカリッと焼きあげるのがポイント。ソースと青海苔をかけて食べる。
余談だが、山形県にも「どんどん焼き」という名前の粉物があると聞いた。ただしそちらは箸にクルクル巻いて食べるもので、東京下町の「どんどん焼き」とは違うらしい。どんな食べ物かなと思っていたら、つい最近、高速道路のサービスエリアで発見! 値段も手頃だったので買ってみたところ、生地が少し柔らかいだけで、味は東京のものとほとんど変わらなかった。
家庭と公民館、そしてインターネット。
さて、明治生まれの祖母の得意料理は何だったかを書いておきたい。アジの開きも食べたし、煮干しの味噌汁も作ったが、本当に得意だったのはハンバーグ、グラタン、ビーフシチュー、ロールキャベツなどの洋食だ。当時はデミグラスソースだのホワイトソースだのといった洒落た調味料は市販されておらず、すべて手作りである。家族への愛情に駆り立てられ、祖母は料理に手間をかけた。
やがて母の時代になるとジューサーミキサーが登場し、食材も増えて、料理のレパートリーが広がる。冷蔵庫も氷を入れて冷やすタイプから電気冷蔵庫に変わり、昭和中期には冷凍庫が付いたものも現れた。祖父母世代からの嗜好で洋食を作ることが多かった母は、冷凍庫のおかげでデザートにシャーベットも作れるようになる。私はトマトをミキサーにかけて砂糖を加えたシャーベットが好きだった。
祖母から母へと受け継がれたレシピは私にもしっかりと伝わったが、最近は作るより買ったほうが安くて美味しいものもたくさんある。そういった時代の流れに対して母はかなり肯定的だ。
「忙しいときは作ることないわよ。このビーフシチューだって美味しいじゃない」
「固形ルーだけどね」
「便利なものは使わなきゃ」
「でもコロッケはうちで作ったほうが良くない?」
「そんな面倒なことしないで買いなさい」
私より母のほうが柔軟だ。暮らしというものは刻々と変わるのだ。前回ご紹介した黒豆も、私自身はずいぶん長いあいだ作っていない。乾燥した黒豆を買い、時間をかけて煮たところで誰も喜ばないからである。各家庭で好みは分かれると思うけれど、うちの家族は黒豆に限らずお節料理全般を好まないため、我が家に欠かせないお正月料理はお雑煮だけだ。
ご存知の通り、お雑煮は全国各地に様々なものがある。もう20年も前のことだが、母の公民館仲間である韓国女性に、「岡山のお雑煮を教えて」と言われたことがあった。岡山県出身の旦那さんに故郷のお雑煮を食べさせたいのだけれど、義父母は他界しているため教えてくれる人がいないということだった。
ちょうどインターネットを始めたばかりだった私は、異業種交流サイトで知り合った岡山在住の女性にメールして「ブリ雑煮」というものを教えてもらった。その味は大変に好評で、韓国女性の旦那さんも「子どものころを思い出す」と褒めてくれたそうだ。
興味のある方のために簡単にレシピを書いておくと、大根、にんじん、里芋をゴロゴロと大きめに切って白だし系で煮る。柔らかくなったら同じ位の大きさに切った木綿豆腐を加え、味を染み込ませておく。これが下ごしらえ。食べるときに温めなおし、お餅を入れる。ブリは他の具材とバランスの良いサイズにして塩を振り、こんがりキツネ色になるまで焼いてお雑煮にトッピング。薬味として白髪ネギと千切りの柚子を多めに乗せればできあがり。
いま思い出すと、スタート直後のインターネットは現代のようにあらゆる情報が便利に溢れているわけではなく、まず「人」と知り合って、そこから役に立つ情報を得る。電話帳のようなものだった。
結局のところ、今のインターネットもそこに「人」がいることには変わりない。世界各地の情報を得る。あらゆる専門知識を学ぶ。さまざまな趣味を共有する。ネットの中に人間がいるからこそ可能になったシステムだ。今の便利なネットは、人類みんなが協力して作り上げたのだ。
そう考えてみれば、祖母から母そして自分とレシピを伝えた家庭も、公民館レベルの国際交流も、インターネットも、要するに「人と人」がつながって何かを伝える場所だ。せっかく知恵を伝えても、我が家では黒豆が絶滅寸前になっているし、コロッケは作らず買ってくることにした母のような方針転換もある。でも、それでもいい。伝える場がしっかりとしていれば、私たちの生活は変化してもいいのだ。
どんどん焼きのソースの香りで若かったころの母を思い出し、ブリ雑煮を食べるたびに私は顔も知らない岡山の女性を思い出す。私たち地球人が"自分以外の誰かとつながる"という方向に進化したことを嬉しく感じるのである。
※記事の情報は2019年5月14日時点のものです。
-

【PROFILE】
小田かなえ(おだ・かなえ)
日本作家クラブ会員、コピーライター、大衆小説家。1957年生まれ、東京都出身・埼玉県在住。高校時代に遠縁の寺との縁談が持ち上がり、結婚を先延ばしにすべく仏教系の大学へ進学。在学中に嫁入り話が立ち消えたので、卒業後は某大手広告会社に勤務。25歳でフリーランスとなりバブルに乗るがすぐにバブル崩壊、それでもしぶとく公共広告、アパレル、美容、食品、オーディオ、観光等々のキャッチコピーやウェブマガジンまで節操なしに幅広く書き続け、娯楽小説にも手を染めながら、絶滅危惧種のフリーランスとして活動中。「隠し子さんと芸者衆―稲荷通り商店街の昭和―」ほか、ジャンルも形式も問わぬ雑多な書き物で皆様に“笑い”を提供しています。
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- 高齢者でも楽しめるバリアフリーな珍道中 小田かなえ
-

- 30年前、母娘で共有した趣味と友達 小田かなえ
-

- 公民館に生まれた小さな国際交流 小田かなえ
-

- 「何でもやってみる」人たち 小田かなえ
-

- 超高齢者だって音楽を聴きたいに決まってる。 小田かなえ
NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事
-

- 最強の御守りのつくり方と不思議なジュエリー職人 小田かなえ