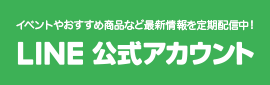【連載】人生100年時代、「生き甲斐」を創る
2019.07.02
小田かなえ
30年前、母娘で共有した趣味と友達
少子高齢社会となった日本で、共同体の最小単位『家族』はどこへ向かうのか。「すべてのお年寄りに笑顔を」と願う60代の女性が、超高齢の母との生活を綴ります。
イラスト:岡田 知子
老いた母が好きな猫と、山と、杖?
数日前のこと。母が自分の部屋で四つん這いになり、うなだれていた。両膝を揃えて床につけ、両腕を伸ばして手のひらも床に置き、ガックリと頭を下げている。落ち込んだ人の姿を表す顔文字そのものだ。何かショッキングなことでもあったのだろうか。
「どうかしたの?」
母がゆっくりと顔を上げて私を見る。
「なぁに?」
「その格好は何なのよ?」
「猫」
そういえば最近よく黒猫を見かける。近所の大きなマンションで世話している地域猫だと思うが、毛ヅヤが良くてまん丸い。あの猫が庭にやってきて悪さをしたのかしら。
「黒猫にイタズラされたの?」
「黒猫なんか知らない。猫のポーズやってただけ」
少しばかり迷惑そうに答えた。母はヨガをやっていたのだ。34年前、60歳で退職した母が公民館で始めたさまざまな習い事のうち、ヨガには私も1年ぐらい一緒に通っていた。珍しいモノ好きの母に小学生のころバレエを習わされていた私は、大人になっても身体が柔らかいのが自慢だったため、ヨガにはすぐに馴染めたのだ。だから基本的なポーズは覚えているはずだったのだが......。
その日の母はべつに落ち込んでいたわけではなく、ヨガの猫のポーズのなかでいちばん簡単なものをやっていただけ。四つん這いになり、猫のように背中を丸めたり伸ばしたりする。これは首筋のストレッチ効果があるので、机に向かって仕事しているときの休憩時間に取り入れると良い。
「あたしは毎日いろんなポーズを思い出してやってるのよ。かなえはやってないの?5分でもいいからやらなきゃダメじゃない」
猫のポーズを見分けられなかったせいで叱られてしまった。
母が時折やっているのは、猫のポーズのほかに、山のポーズと杖のポーズらしい。山というのは背筋を伸ばしてまっすぐに立つことで、姿勢矯正と心を安定させる効果がある。杖のほうはやはり背筋を伸ばし、手のひらを床につけて両脚を揃え、横から見ると直角になるように座る。ただ座っているだけに見えるが、ふだんは使わない筋肉が刺激されて姿勢が良くなるのだ。
ヨガのおかげかどうかは不明だが、母は94歳の割にはあまり足腰を痛がらない。もちろん高齢なので身体の各所に不具合はあるけれど、たとえばキッチンで私と喋っているときなど、私は椅子に座っているのに、母は20分ぐらいなら立ったままだ。
「座ればいいじゃない」
「なんで?立ってるほうが気持ちいいから大丈夫」
亡き祖母も姿勢の良い人だった。テレビを観ながらくつろいでいるときも、きちんと背中を伸ばして正座している。それがいちばん楽なのだと言っていた。
これは、ヨガをやれば、あるいは背筋を伸ばせば元気でいられるという話ではない。
何かを頑張るのではなく、自分なりの心地良さを感じることが大切なのだ。座りたいのに無理して立っている必要はないし、足が痺れるまで正座しても痛いだけ。
老化に不具合はつきもの。各人各様、いろいろなところが不調になる。自身の体調や環境に合わせ、どうすれば気持ち良さを感じるか見つけることが、人生100年時代を楽しむ秘訣だと思う。
年を重ねることは、人との出会いを積み重ねること。
私たちが今の家に引っ越してきたのは1984年で、母が定年を迎える3年前。町内には知り合いがひとりもいなかった。回覧板を届ける隣家の住人とは立ち話をすることもあったが、それ以外は向こう三軒両隣、辛うじて名前と顔が一致する程度だ。母と一緒に私もヨガを習うことにした理由は、近所に同世代の友達を作るためでもあった。
しかし公民館のヨガ教室に通ってくる女性たちは、私から見ると親の世代ばかり。友達づくりの望みは初日で潰えたかに見えた。
ヨガ教室に持参するものは大判のバスタオルだけ。公民館の広い和室に各自がバスタオルを敷き、その上で軽く体操をしてから「魚のポーズ」や「コブラのポーズ」を習うのだ。先生がカセットデッキを持参し、いつもゆったりした癒し系のBGMを流してくれる。
参加人数は日によって違い、少ないときは4~5人、多ければ10人前後。実際には15人ぐらい在籍しているのだが、入れ替わりも頻繁で、全員が揃うことはない。
そのヨガ教室に、母と私の中間ぐらいの年齢の女性がいた。その人が私の次に若いわけだが、それでも当時40歳ぐらい。仮に花川さんと呼ぶことにするが、とてもステキな人なのだ。華奢な体型と愛くるしい顔立ち。私たちはヨガ用のジャージで公民館へ行っていたが、彼女はパステルカラーのスカートやワンピースを着てきて、和室の隅で手早く着替える。
花川さんはほとんど休まなかったため、必然的に会うチャンスも増え、いつのまにか私たちは3人でランチを楽しむようになっていた。念願の友達ができたのだ。
この花川さんは典型的な聞き上手だった。自分の話はあまりせず、優しい声と品の良い言葉で母の習い事や私の仕事について聞いてくれる。下町育ちの母と私は、騒々しい声とガサツな喋りかたで答える。
ある日のこと、ヨガの先生が花川さんの素性を教えてくれた。
「あの人は旧華族のお姫様なのよ。ご主人は日本人なら誰でも知ってる◯◯製薬会社の社長よ」
私の世代では華族と聞いても実感がわかず、上から順に公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵と呼ぶという程度の知識しかない。むしろ製薬会社の社長夫人のほうがピンとくる。
そんな人がなぜ公民館のヨガ教室に来ているのか。本人に聞くと屈託なく答えてくれた。
「そう、小中学生のころはお姫様ってアダ名だったわ。夫が社長なのも本当だけど、私は私。親が華族でも裸族でも、夫が社長でも蝶々でも、私自身は自分の身の丈にあった生活を送るだけ」
ユーモアたっぷり、ダジャレ付きの回答だった。
花川さんの考えかたは母と私の心にしっくり添った。母は常々「あたしは相手が社長でも総理大臣でも平気で話せるわ、だって同じ人間じゃない」と言っており、その母に育てられた私も人怖じしない性格なのだ。相手から見れば失礼極まりないが、たとえば私は校長室にも平気で入っていく子どもだった。
そんなわけで母と私は花川さんとますます親しくなり、あるとき彼女の家にお邪魔する機会を得た。そこはいわゆる豪邸で、何十畳もありそうなリビングが色とりどりのバラが咲く庭に面しており、窓際にマッサージチェアも置いてある。
「バラは誰が手入れしてるの?」
「きれいでしょ。私が育ててるんだけど、日に焼けて大変なのよ。あらヤダ、雨が降ってきた ! 」
バタバタと階段を駈け上がり、慌てて洗濯物を取り込む姿は、華族のお姫様や上場企業の社長婦人には見えなかった。
ヨガ教室は、私自身はフリーランスの悲しさで毎週必ず同じ曜日・同じ時間が空いているとは限らず、どうしても休みがちになってしまい、結局1年で辞めてしまった。母のほうは10年以上続けていたと思う。
2019年現在、海外へ移住した花川さん夫妻とは連絡が途絶えてしまったが、私たちがあのころを懐かしんでいるように、彼女も母と私を思い出してくれているだろうか。
年を重ねるということは、人との出会いを重ねるということでもある。私より下の世代はインターネットのおかげで幼稚園時代の級友と再会したり、遠い国の人たちと友達になったりできる。しかし母の世代は途中に戦争をはさんでいるため、本来なら末長く付き合えたはずの同窓生も散り散りになってしまった。
そう考えると、せっかく迎えた長寿時代、高齢者ひとりひとりが家族や仲間と共に、あるいは自分だけの楽しみを見つけ、心地良く過ごして欲しいと願ってやまない。
※記事の情報は2019年7月2日時点のものです。
-

【PROFILE】
小田かなえ(おだ・かなえ)
日本作家クラブ会員、コピーライター、大衆小説家。1957年生まれ、東京都出身・埼玉県在住。高校時代に遠縁の寺との縁談が持ち上がり、結婚を先延ばしにすべく仏教系の大学へ進学。在学中に嫁入り話が立ち消えたので、卒業後は某大手広告会社に勤務。25歳でフリーランスとなりバブルに乗るがすぐにバブル崩壊、それでもしぶとく公共広告、アパレル、美容、食品、オーディオ、観光等々のキャッチコピーやウェブマガジンまで節操なしに幅広く書き続け、娯楽小説にも手を染めながら、絶滅危惧種のフリーランスとして活動中。「隠し子さんと芸者衆―稲荷通り商店街の昭和―」ほか、ジャンルも形式も問わぬ雑多な書き物で皆様に“笑い”を提供しています。
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- 高齢者でも楽しめるバリアフリーな珍道中 小田かなえ
-

- 人と人がつながって伝わる、懐かしの「味」 小田かなえ
-

- 公民館に生まれた小さな国際交流 小田かなえ
-

- 「何でもやってみる」人たち 小田かなえ
-

- 超高齢者だって音楽を聴きたいに決まってる。 小田かなえ