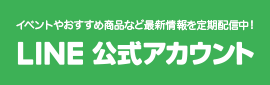【連載】人生100年時代、「生き甲斐」を創る
2020.12.09
小田かなえ
手紙と宅配便は、高齢社会の笑顔をつなぐ!
少子高齢社会となった日本で、共同体の最小単位『家族』はどこへ向かうのか。「すべてのお年寄りに笑顔を」と願う60代の女性が、超高齢の母との生活を綴ります。
イラスト:岡田 知子
異国から届く恋文、届かぬ現金
英国植民地時代の香港を舞台に描かれた「慕情」という映画をご存知だろうか? 軍人の夫を亡くした女医さんと、アメリカ人新聞記者のラブストーリーである。映画の内容より主題歌のほうが有名かもしれない。オペラの「蝶々夫人」に似た出だしの曲......と申し上げれば「ああ、アレね」と分かる方も多いはず。
内容は、ふたりで過ごした幸せな日々も束の間、新聞記者の恋人が朝鮮戦争の取材に行って死んでしまうという悲恋もの。戦地にいる彼と女医さんは何通もの手紙で愛を伝え合っていて、訃報を聞いた日にもちょうど手紙が届いていた。先に死の報せを聞いたヒロインは、愛を語り合った丘「ヴィクトリア・ピーク」に立ち、亡き恋人からの手紙を読むというお話。
これは実話だそうで、映画でも政治的な背景などが語られている。しかし、やはり女性たちの心を掴んだのは甘く切ない恋。1955年に公開された直後は香港の観光客が増え、「ヴィクトリア・ピーク」も観光スポットになったとか。
さて、何が言いたいのかというと、母はこの「慕情」がとても好きなのだ。
曰く「トシローさんと私みたい」......何度も言うがトシローさんは私の父で、先の戦争に出征している。
「トシローさんが死んじゃったら私は生まれなかったじゃない」
「分かってるわよ、そんなこと。トシローさんは、戦争中も戦後も、カナエが生まれてからも、よく外国から手紙をくれたのよ」
父は商社に勤めていたため、単身赴任が多かった。私が1歳の頃から中学生になるまで海外を転々と異動。
そんな父を送り出す際、母が私に「パパはブンブン(飛行機のこと)でお仕事だからバイバイね」と教えたため、私は飛行機の音がするたびに上を向き「パパ、ブンブン、バイバイ」と手を振るようになったそうだ。そのせいで母は、知らない人から「旦那様はパイロットなんですか?」と聞かれたこともあったとか。
というわけで「慕情」のヒロインと自分を重ね合わせる母なのだが、戦時中は言うまでもなく、戦後も国際郵便はあまりアテにならなかったらしい。特に手紙だけではなく現金を同封すると、無事に届く確率がグーンと下がる。
父は手紙を託した現地のメイドさんたちの誰かが懐に入れてしまうのだと思っていたようだが、それを糾弾しなかったあたり、事なかれ主義の父ならではの呑気さだ。
幸いなことに母は手に職があったため、父からのお金が行方不明になってもさほど困らなかったと言っているが、ラブレターも送金もスマホひとつで完結する現代人にとって、昭和の国際郵便事情は何もかも不安である。
お年寄りを楽しませる自筆の便り
あれから60年。
トシローさんは15年前に「お空へバイバイ」し、母も100歳から数えたほうが早い年齢になった。以前はよく集まっていた親戚も、高齢および新生活習慣によって、このところ会うことも叶わない。
そのせいで、意外にも復活してきたのが手紙だ。いや、世間的なスケールではなく、単に我が親類縁者の間で......という話ね。
もちろん私たちの世代はメールで連絡し合っているし、約100歳のお婆さんたちも固定電話でおしゃべりすることが多いのだが、記憶力に若干の問題を抱えるようになってくると、何度も読み返せる手紙はうれしいもの。うちの母も、姪っ子が送ってくれた手紙、弟からの手紙、甥っ子が送ってきた姉の写真などを大切に保管し、ときどき取り出しては眺めている。
面白いことに、パソコンが普及する前はワープロで手紙文を打つ人も多かったのに、メールが主流となった今は、逆に自筆の手紙が増えてきた気がする。
ときどき母に手紙をくれる従妹も、私にはメールで連絡を寄越すのだが、母宛の手紙は丁寧な自筆で書いてある。可愛らしい手描きのイラストを散りばめ、時間をかけて仕上げてくれたのだろうと思われる完成度の高さだ。
現代人は字を書く機会が激減した。私自身も同様で、この原稿だって鉛筆で書いているわけではない。その結果として漢字を忘れてしまうんじゃないかという気もするが、たとえ漢字が書けなくなっても困らないのが恐ろしいところ。
うっかりミスの誤変換はあるにせよ、端末に頼っていれば漢字そのものを書き間違えるという恥ずかしい事態は発生しないわけだ。それに甘んじているものだから、なおのこと漢字が書けなくなる。
そこで! 大袈裟に言えば「漢字という文化の衰退」を防ぐための提案をひとつ。
今はオンラインで相手の顔を見ながら話せる時代ではあるが、それとは別に、故郷のご両親に手紙を出そうじゃありませんか。自分が書きたいことを綴り、ついでにお子さんの絵なども同封すれば喜ばれると思うのだが、いかが? 高齢者は、好きなときに読み返せる手紙や、何度でも眺められる写真を手元に置くのがうれしいのだから。
走れ、トラック! 愛とグルメを載せて......
手紙で思い出したが、うちにはよく親戚からフルーツや野菜、海産物が届く。従姉や叔父・叔母が食べて美味しいと思ったブドウやマンゴー、山芋、サーモンなどを送ってくれるので、どれも絶品だ。
会えないけれど大切な人たちと、その家族に贈るグルメ......宅配便が発達したおかげで可能になった愛情いっぱいのプレゼントである。配送日時も指定できるため、通院やデイサービス等で忙しい高齢者宅にも便利だ。
余談だが、今からわずか100年前には、日本全国のトラック数は200台ほどだったそうだ。ほとんどの人は「えっ、そんなに少なかったの?」と感じるはず。
ちょうどその頃に銀座で創業した運送会社が、1970年代半ばに全国的な宅配ネットワークを作り上げた。それ以前は6kgまでの荷物なら郵便局へ、もっと重いもの(30kgまで)は国鉄の駅へ持参しなければ送れなかった。面白いと思ったのが「チッキ」という単語。私も子どもの頃に何度か耳にした記憶がある。これは国鉄で送る荷物の名称で、語源は英語の「check」もしくは「ticket」らしい。
郵便小包にしろチッキにしろ到着がいつになるか分からないので、生モノはもちろん、ほとんどの食品が送れない。おまけにチッキのほうは自宅まで届けてくれないため、6kgより重く30kgあるかも知れない荷物を、通知が来たら駅まで取りに行くわけである。これは想像を絶する不便さだ。
100年後の現在ではあらゆる仕事を担い、たくさんのトラックが走り回っている。郵便小包も親しみやすい名前に変わり、何社もある宅配業者と同じように配達日時や配達場所が指定できるようになった。いつ届くかハッキリしない昭和時代とは違う。これはトラックの台数が増えただけでは成し得ない変化だ。
「どうすれば人はもっと便利に暮らせるのだろうか」「いま必要とされているのはどんなサービスか」そういったアイデアがあればこそ、大きなトラックや冷凍車などが大活躍して私たちの生活を変えてくれたのである。
おかげで母と私も、遠くの県から直送されたグルメにありつけるという次第。ありがたや、ありがたや。
※記事の情報は2020年12月9日時点のものです。
-

【PROFILE】
小田かなえ(おだ・かなえ)
日本作家クラブ会員、コピーライター、大衆小説家。1957年生まれ、東京都出身・埼玉県在住。高校時代に遠縁の寺との縁談が持ち上がり、結婚を先延ばしにすべく仏教系の大学へ進学。在学中に嫁入り話が立ち消えたので、卒業後は某大手広告会社に勤務。25歳でフリーランスとなりバブルに乗るがすぐにバブル崩壊、それでもしぶとく公共広告、アパレル、美容、食品、オーディオ、観光等々のキャッチコピーやウェブマガジンまで節操なしに幅広く書き続け、娯楽小説にも手を染めながら、絶滅危惧種のフリーランスとして活動中。「隠し子さんと芸者衆―稲荷通り商店街の昭和―」ほか、ジャンルも形式も問わぬ雑多な書き物で皆様に“笑い”を提供しています。
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- 珍客万来、愉快な高齢コミュニティー! 小田かなえ
-

- 「大正生まれ女子」も熱中したグルメとレジャー 小田かなえ
-

- オーバー90女子の『恋バナ』はいかが? 小田かなえ
-

- 超高齢者だって音楽を聴きたいに決まってる。 小田かなえ
-

- 30年前、母娘で共有した趣味と友達 小田かなえ
NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事
-

- 最強の御守りのつくり方と不思議なジュエリー職人 小田かなえ