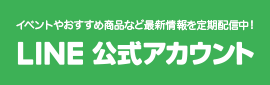スポーツ
2023.10.10
平山ユージさん プロフリークライマー〈インタビュー〉
平山ユージ|世界の岩場で死力を尽くして見つけた、クライミングの魅力
10代の頃から世界を舞台に活躍し、日本人で初、2度のクライミングワールドカップ総合優勝を達成したプロフリークライマー・平山ユージさん。現在はクライミングジムの運営や埼玉・小鹿野(おがの)クライミング協会の会長を務める傍ら、東京オリンピックのクライミング競技では解説者を務めるなど、クライミングを広める活動も精力的に行っています。クライミングとの出合いや競技の魅力、これからの活動についてお話をうかがいました。
写真:加藤 甫
忘れられない、初めてのクライミング体験
――平山さんがクライミングを始めたきっかけはどのようなものだったのでしょうか。
中学1年生の頃から登山を始めたんですが、「もっと高い山を登るためには、岩登りの技術も身に付けたい」と思うようになっていました。でも、山岳会などに問い合わせても「危ないからダメだ」と断られてしまったんです。中学を卒業して航空高専に入学した後も「岩登りの技術をどこかで身に付けられないか」とずっと考えていました。
15歳の時、登山用品店のセールに行ってクライミング用品を見ていたら、店員さんが「君、クライミングやりたそうだね。スクールやるから来ない?」と誘ってくれたんです。その店員さんは、日本クライミング界の第一人者である檜谷清(ひのたに・きよし)さんという方でした。それから1週間後に、埼玉県にある日和田山(ひわださん)で行われたスクールで、初めてクライミングを体験しました。生涯忘れることはないと思うくらい、面白かったですね。

――クライミングのどのような点を面白いと感じたのでしょうか。
最初は怖くて身がすくむような気持ちだったんですが、一生懸命登って頂上に立った時の景色や解放感がものすごくよかったですね。ひとつの岩壁でもちょっとスタート地点を変えるだけで登り方が全く違うんです。「目の前にある岩壁だけでもこんなに違う表情を見せてくれるなら、世界中にある岩や壁となると......」と想像すると、一生飽きない気がしました。
あと、登りきるためには体を鍛えたり登り方を工夫しなきゃいけない点も魅力でした。日和田山の時は1本だけ何度挑戦しても登れなかったルートがあって、檜谷さんに「どうやったら登れますか」って聞いたら「懸垂して腕と指を鍛えたらいい」と言われたんで、帰りの電車内で、鉄枠を指でつかんで懸垂していました(笑)。
――「もっと違う景色を見たい」という気持ちが湧き起こったわけですね。
そうですね。僕は東京都出身なんですが、小学校の頃は夏休みのうち2~3週間くらいは茨城県にある叔父の家で過ごしていました。そこで田んぼがぶわーと広がっている景色を見たり、虫捕りや魚捕りをしたりして、自然の中にいることが好きだったんですよ。山を見るのも好きだったし。思えばその時も、普段とは違う景色を見る楽しさを求めていたんだと思います。
ヨセミテで目の当たりにしたヨーロッパのレベル
――17歳の時に初めて渡米していますが、アメリカに行こうと思ったきっかけはどのようなものだったのでしょうか。
実は、クライミングを始めて1カ月後くらいには「アメリカに行こう」と決めていました。
現在、クライミングが禁止されているんですが、その頃、東京の常盤橋公園にある江戸城城壁跡の石垣でクライミングの練習をしていました。そこでクライマーたちから世界中のいろんな岩場の話を聞いていたんです。その中で、クライミングの聖地と言われているヨセミテの話が出てきまして「絶対行きたい」と思っていました。
そして1986年、クライミングの練習を通じて知り合った山野井泰史(やまのい・やすし)さんから誘われて、アメリカに行きました。ちなみに、山野井さんはのちに世界的クライマーとなって、現在も活躍しています。
――初めてのヨセミテでのクライミングは、どのように感じましたか。
実際に行ってみて感じたのは「クライミングの中心はアメリカじゃなくてヨーロッパだ」ということでした。ヨセミテでヨーロッパのクライマーが登っている様子を見ると、卓越したスキルとそれを使いこなす身体能力がずば抜けていました。
僕自身もヨセミテで40本くらいのルートを登ったので、ある程度のスキルが付いたと思っていましたが、「強くなるためには、ヨーロッパのスタイルを取り入れなければいけない」と強く感じました。ヨセミテから帰国し、1年ほど経ってヨーロッパに行きました。

――行動力がすさまじいですね......! ヨーロッパでも現地のクライマーたちと交流する機会があったと思いますが、その中でも印象的だった出来事はありますか。
フランスのナショナルチームでコーチをやっていた方が、各国のクライマーを集めて開いてくれた講習会に参加した時でした。それまでの僕は「どのような体勢でどのように登るのか」をぼんやりとしかイメージできていなかったんですが、参加したクライマーの多くが、映像で再現できるくらい事細かに登り方をイメージしていることが分かったんです。「イメージ」という言葉のとらえ方がこんなにも違うのか、と感じました。
また、ヨーロッパのクライマーたちの間では「デターミネーション(determination)」という言葉がよく使われていました。日本語では「死力を尽くすこと」などと訳される言葉なんですが、「クライミングにはこういうロジックがあって、それを踏まえたからこそ死力を尽くせる」という合理的な意味合いで使われていたのが印象的でした。ヨーロッパのクライマーたちの考え方に触れることができたのは、良い経験だったと思います。
ギリギリな気持ちだった「プロクライマー宣言」
――「プロになる」と決意したのはいつ頃だったのでしょうか。
20歳の時ですね。高専を休学してヨーロッパに渡った後、世界最難ルートを登りきったり、国際コンペで8位入賞したりしたのですが、次の目標がなかなか決まらなかったんです。しかも、帰国して復学しても、学校の勉強が進んでいて授業の内容が全然分からない。先生の言葉が子守歌のようでした(笑)。
「このままじゃいけない」と思って、自分が本当にやりたいことは何なのかをいろいろ考えた結果、クライミングがほかの選択肢と比べてちょっとだけ興味があって、自分の能力を生かせることなんじゃないかと思ったんです。
それで、1989年5月31日に退学届を出し、「私は、世界一のクライマーを目指し、努力します。」と書いた紙を部屋の壁に貼り付けて、有言実行するんだと自分に言い聞かせることにしました。クライミングにおいて、世界で自分の実力を認めてもらうためには、大会で優勝することが重要です。ちょうどワールドカップが始まった時期だったので、ワールドカップの総合優勝を「世界一」と定めて、これを目指そうと思いました。
でも、「ほかの選択肢よりクライミングがちょっとだけ興味があったからプロになる」って、今思うとけっこうギリギリな気持ちで判断していますね(笑)。

――退学する時、周りの反応はいかがでしたか。
もともとは漠然と家業を継ごうと思って高専に入学しましたし、クライミングという競技は常に危険が付きまといます。プレス業を営んでいた父は最初は反対していましたが、最終的にはクライミングの道具を製作してくれるなど、応援してくれるようになりました。先ほどお話しした「プロクライマー宣言」の紙も、後で額に入れて飾ってくれたんです。本当に感謝しています。
国際コンペで8位入賞した時から援助してくれていた企業の社長からは、「もし学校を途中でやめたら提供してきたお金は全額返してもらう」と言われていたんです。緊張して退学の報告をしに行ったのですが、「平山君の人生だから大丈夫だよ」と不問にしてくれました。今思うと、クライマーを引退した時に多少の学歴を持っていてほしいという親心だったんだと思います。
――プロになってから数々のコンペに出場されましたが、その中で一番印象に残っている試合は何ですか。
1989年11月に出場したドイツ・ニュルンベルクのフランケンユーラ国際シュボルツクレッテラー・カップ。初めて優勝した国際コンペです。
その年の5月に高専を退学して、8月の終わりくらいにヨーロッパに渡り、イタリアやオーストリア、ドイツにある岩壁でクライミングしつつ、その合間にコンペに2つ出場しました。1つ目のコンペで3位になって手ごたえは感じていたのですが、「まだ優勝までいける感じではないな」と思っていました。でも、その2カ月後に開催されたこの大会で優勝してしまったんです。
それまでは、自分が世界中の憧れの選手たちと同じ土俵で戦えている実感がありませんでした。「ヨーロッパの選手はすごい!」と思って、何年もただひたすらトレーニングしていたら、いつの間にか優勝できたという感じです。この優勝のおかげで、世界で通用するという自覚が芽生え、「プロでやっていこう」という気持ちが深まりました。
1,000mの崖を「ほぼ事前情報なしで」登る前代未聞の挑戦
――プロになってからもさまざまな岩壁を登ってきたと思いますが、特別な思い入れがあるのはどこでしょうか。
ヨセミテにエル・キャピタンという巨大な一枚岩があるのですが、その中にサラテというクライミングルートがあります。1997年9月にこのルートをオンサイト・トライしたことが、僕の人生で大きな意味を持っています。
「オンサイト」とは、事前情報をほぼ持たず、初見で落下せずに登りきることを指します。事前に許されるのは「トポ」と呼ばれるルート図を見たり、離れた場所から岩肌を見たりする程度。ほかの人が登る様子を見たり、手順を聞いたりするといったヒントを得ることができません。
エル・キャピタンは高さ1,000m以上ある巨大な岩壁です。特にサラテはとんでもなく難しくて、綿密に下調べして長期日程で登るのが普通でした。当時、オンサイトで登ることを誰も想像していなかったと思います。「世界中でこのことを考えているのは自分だけ。オンリーワンなことを成し遂げたい」という気持ちでした。
ほぼ垂直の岩壁に取りつき、約40時間かけて登る。それまでにないくらい自分の底力を出した挑戦でした。ヨーロッパで学んだ「デターミネーション(=死力を尽くす)」のもっと深い部分を出している、という感覚です。実はその年の4月に結婚していて、この時には妻が妊娠していたんです。それ以前の自分だったら「もう限界」って100回くらい言っていたと思いますが、自分がそれまで培ってきた技術をフル動員して、妻とおなかの中にいる子どものためにも登りきろうという気持ちで臨みました。
結果的には、オンサイト・トライは失敗。初見で最後まで登りきることはできませんでしたが、途中2回落下しただけで登りきることができました。
 平山さんが経営するBoulder Park Base Camp飯能店に飾られている「エル・キャピタン」の写真
平山さんが経営するBoulder Park Base Camp飯能店に飾られている「エル・キャピタン」の写真
――登りきった後は、どのようなことを考えましたか。
登りきった直後は興奮していて「1週間後にまた挑戦しちゃう?」って話していたんですが、次の日、そのまた次の日とどんどん疲れが押し寄せてきて、2週間後には家に帰っていました(笑)。
でも、サラテを登りきったことで「この力を出せるならワールドカップで少なくとも1勝はできるだろう」という自信につながりました。結果、1998年のワールドカップで日本人初の総合優勝を達成することができました。
ジム設立、自治体との連携。クライマーとしての「第2の人生」
――選手とは別の側面として、2010年、埼玉県入間(いるま)市にクライミングジム「Climb Park Base Camp」をオープンします。クライミングジムを始めようと思ったきっかけは何でしょうか。
自宅の近くでカフェをやっているオーナーさんから「カフェの前に大きな土地があるから、そこでジムをやってみないか」と誘われたのがきっかけで、ジム運営を考えるようになりました。結局、その土地は農地だったので、ジムを建設することができなかったんですが。
それからしばらく経って、妻がやっているダンス教室の折り込みチラシを新聞の集配所に届ける手伝いをしていた時に、集配所の隣によさそうな物件を見つけたんです。「ここだ!」と思って手続きをし、2010年に「Climb Park Base Camp」としてオープンしました。
 2010年に埼玉県入間市にオープンした「Climb Park Base Camp」
2010年に埼玉県入間市にオープンした「Climb Park Base Camp」
――ご近所の方との交流から構想が始まったのですね。コンペへの参加や岩壁を登る以外の活動をしようと考え出したのはいつ頃だったのでしょうか。
サラテを登った1997年の頃からですね。当時のアスリートは20代半ばで引退されている方が多く、僕自身はサラテのオンサイト・トライを最後に、仕事を見つけて安定した収入を得られるようにしようかなと考えていました。
また、その翌年にはシューズ製作に関わるビジネスの話があったり、クライミング講師の仕事を始めたりして、選手を引退した後の人生について考える機会が多かったです。でも、当時は「ワールドカップの総合優勝」という目標に向けて頑張っていて、後のことはそれを果たしてから考えようと思っていました。
――現在は7つのクライミングジム経営に加えて、一般社団法人小鹿野クライミング協会の会長としても活動されています。こちらはどのようなきっかけで始めたのでしょうか。
2008年にクライミングによる町おこしの提案書を埼玉県小鹿野町に送りました。当時は形にならなかったのですが、2018年に町会議員の方から連絡をいただいたことがきっかけで、協会設立に至りました。
会長になったのはジムの設立より後なのですが、ジム設立の頃から岩場との連携を考えていました。ジムの名前を「ベース・キャンプ」にしたのも、岩場に通うクライマーたちが集まってトレーニングや情報交換をする場所として利用してもらいたいと思ったからなんです。
――クライミングスポットとして小鹿野町に注目したのはなぜですか。
町と岩場の距離感がすごく近いと感じたんです。都心から近くて、週末に岩場に登る人もアクセスしやすい。岩場を登るために来たクライマーに、町の宿泊施設やレストランを利用してもらうといった経済効果が期待できると思いました。
町おこしの一環として、岩場の整備やルート開拓に加えて、町営クライミングジム「クライミングパーク神怡舘(しんいかん)」のオープンにも携わりました。「神怡舘」は埼玉県と中国・山西省の友好県省締結10周年を記念して建設された建物だったんですが、取り壊しが検討されていた時期がありました。地元の方からも「残してほしい」という声があり、クライミングジムへのリニューアルを提案しました。

 唐代の寺院をモデルにした記念館をリノベーションした「クライミングパーク神怡舘」。ボルダリング壁やキッズスペースなどが完備されている(提供:小鹿野町役場まちづくり観光課兼山岳クライミング推進室)
唐代の寺院をモデルにした記念館をリノベーションした「クライミングパーク神怡舘」。ボルダリング壁やキッズスペースなどが完備されている(提供:小鹿野町役場まちづくり観光課兼山岳クライミング推進室)
クライマーがほとんどいなかった町に、今では年間で何百人ものクライマーが小鹿野町に来ています。町の人を含め老若男女問わずコミュニティができていたりするので、いろんなところで良い化学反応が起きていると思います。
「一つの遊びを通じてつながること」がクライミングの魅力
――自治体との連携や東京オリンピックでの解説など、プロクライマーとしてさまざまな活動をされている平山さんですが、今後はどのような活動をしたいと考えていますか。
まだ自然の岩場に登ったことがない人に向けた活動をしたいです。自然の岩場には、ジムにはない魅力があります。登れないところがあったら、ジムに戻ってトレーニングして、再挑戦する。そのために「Base Camp」を利用してほしいと思っています。
また、海外でクライミングによる町おこしに成功した場所に、自治体の方を連れていきたいですね。例えば、イタリアのアルコという町は、周辺に100以上のクライミングスポットがあったり、子ども専門のクライミングショップがあったりするなど、町おこしにより町の人にとってクライミングがとても身近な存在になっています。自治体の方に成功事例を見てもらうことで、クライミングによる町おこしをイメージしてもらえたらうれしいですね。

――平山さんが考えるクライミングの一番の魅力は何でしょうか。
僕がクライミングを始めた時は、目の前の岩壁を登るために体を鍛えて、登りきった達成感を得ることが楽しみでした。ですが、今ふとジムの様子を見てみると、目の前の壁を登っているうちに自然と知り合いが増えている人が多いんです。自分自身の経験をかえりみてもやはりそうです。もともとは他人同士だった人たちが、一つの遊びを通じてつながっていくことが魅力なのかなと最近思うようになりましたね。
また、海外の岩場で、「この壁はどうやって登るの?」と現地の人と身振り手振りでコミュニケーションを取るうちに仲良くなることがあります。日本だけでなく、世界各国の人たちともつながりを作れることも、クライミングの魅力です。
答えを見つけるためには「いったん寝かしておく」ことも必要
――最後に、プロクライマーとして世界各国のさまざまな岩場を登ってきた平山さんですが、困難に直面し、心が折れそうになった時はどのように打開したのでしょうか。日本人初のワールドカップ総合優勝や、サラテのオンサイト・トライといった偉業を成し遂げた平山さんの考えを聞かせてください。
困難を乗り越えるためには急いで答えを探しがちですが、「いったん寝かしておく作戦」もいいかもしれないなと思います。実はクライミングでも同じことが言える時があるんです。どうしても登れない壁があっても、しばらく経ってまた登ろうと思ったら、以前は見えなかったルートが見えてくることがあります。
「困難に対する答えを見つけよう」とずっと考えていると疲れちゃうし、疲れた中で答えを出してもいい結果につながりません。まずは目の前のやるべきことに集中して、結論を急がないことで、困難に対する答えが見つかるタイミングが来るんじゃないかな、と思います。

――本日はお忙しい中、ありがとうございました。今後のご活躍を楽しみにしています!
取材協力:Boulder Park Base Camp飯能店
※記事の情報は2023年10月10日時点のものです。
-

【PROFILE】
平山ユージ(ひらやま・ゆーじ)
1969年生まれ。15歳でクライミングに出合い、10代の若さで国内トップに。その後、渡仏しトップクライマーとして活躍。1998年のワールドカップでは日本人初の総合優勝を達成し、2000年には2度目のワールドカップ総合優勝を飾って、年間ランキングも1位になるなど、数々の輝かしい成績を納めた。現在はクライミングジムの運営や一般社団法人小鹿野クライミング協会の会長を務める傍ら、東京オリンピックのクライミング競技の中継で解説者を務めるなど、クライミング競技の魅力を伝えるため多岐にわたる活動を行っている。
公式ホームページ
https://yuji-hirayama.com/
Instagram
https://www.instagram.com/yuji_hirayama_stonerider/
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- 林家彦いち|全力で面白がることで身に付いた「面白がり力」 林家彦いちさん 落語家〈インタビュー〉
-

- 林家彦いち|一歩踏みだせば、面白いことは必ず起きる 林家彦いちさん 落語家〈インタビュー〉
-

- 中学から日本代表まで、走り続けた「キャプテン」 廣瀬俊朗さん 元ラグビー日本代表〈インタビュー〉
-

- 軽やかに全力で。多彩なプロジェクトを推進 廣瀬俊朗さん 元ラグビー日本代表〈インタビュー〉
-

- 村上佳菜子|恩師の言葉を胸に。プロフィギュアスケーターとしてのこれから 村上佳菜子さん プロフィギュアスケーター・タレント〈インタビュー〉
-

- 世界チャンピオンを目指す最年少プロ。ビリヤードの楽しさを広めたい 奥田玲生さん ビリヤード選手〈インタビュー〉
NEW ARTICLESこのカテゴリの最新記事
-

- 葛󠄀西紀明|50代のメンタルと体づくり。 9回目のオリンピック出場へ、レジェンドの挑戦は続く 葛󠄀西紀明さん スキージャンプ選手〈インタビュー〉