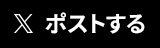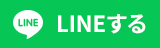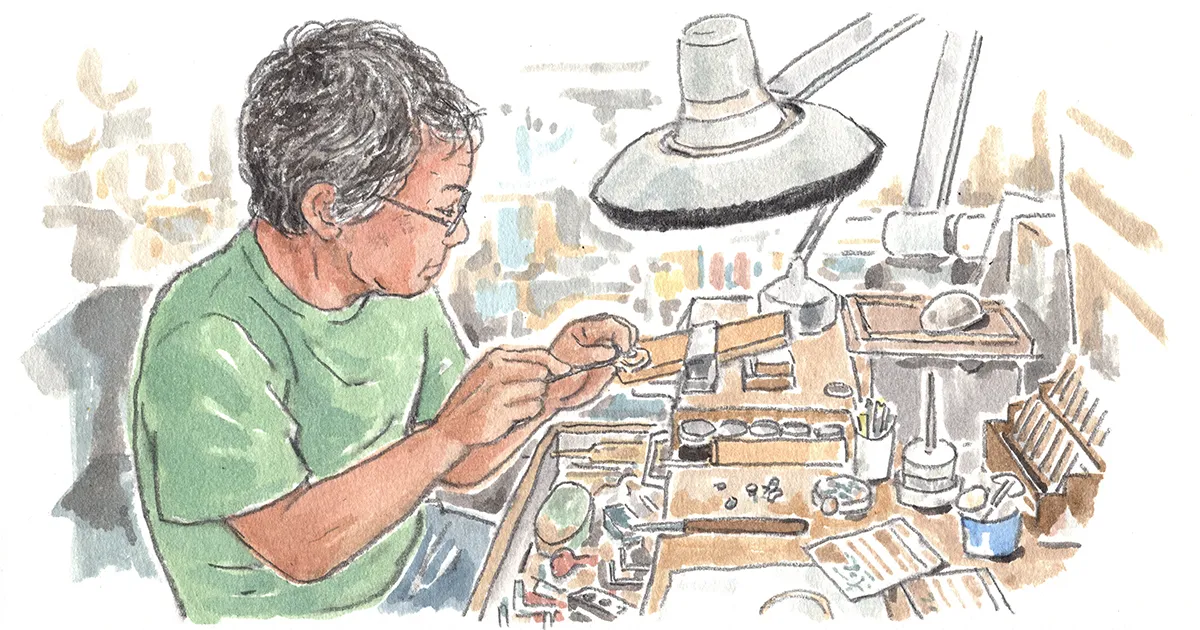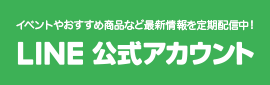【連載】防災士おすすめ! 会社員のための防災グッズ
2025.02.18
防災士:矢野きくの
日常で持ち歩くべき携帯用防災グッズ|防災ポーチの中身リスト。通勤時の災害から身を守る!
防災士の矢野きくの(やの・きくの)さんに、会社員として日ごろから備えておきたい防災グッズをご紹介いただく連載「防災士おすすめ! 会社員のための防災グッズ」。第2回は「日常で持ち歩くべき携帯用防災グッズ」です。防災ポーチや防災ボトルなどに入れる、最低限必要な中身のリスト、持ち歩き用の防災グッズを教えていただきました。
【目次】
- なぜ防災グッズを持ち歩く必要があるのか?
- 〈持ち歩く携帯用防災グッズを用意する前に〉会社員が気をつけたいポイント
- 持ち歩く携帯用防災グッズの入れ物は何がおすすめ?
- 日常で持ち歩きたい防災ポーチの中身【必要なものリスト】
- 持ち歩く携帯用防災グッズは定期的に点検しよう
なぜ防災グッズを持ち歩く必要があるのか?
自然災害はいつ発生するかわからないものです。とくに地震は予測ができず、突然やってきます。家にいるときだけでなく、勤務先や通勤途中に発生することも十分にあり得るわけです。
東日本大震災のとき、首都圏、とくに都内では多くの帰宅困難者が出ました。10km以上の距離を歩いて帰った人や、何時間もタクシーを待った人、避難所として開設されたところに身を寄せた人もいました。
そのような事態になったとき、全く備えがないのと、携帯用防災グッズとして備えがあるのとでは、物理的にも精神的にも大きく状況が変わってくるのです。
今回は、会社員が持ち歩くべき携帯用防災グッズについてご紹介します。
〈持ち歩く携帯用防災グッズを用意する前に〉会社員が気をつけたいポイント
日頃の移動距離と勤務先に想定される被害内容を把握してから、携帯用防災グッズをそろえる必要があります。
自分は近距離の通勤なのか、電車で1時間以上など長距離の通勤なのか。長距離通勤の場合はそれなりの備えが必要となってきます。
また、勤務先や通勤経路でどのような危険が想定されているのかの把握も必要です。広範囲で被害が出ている場合や、首都直下地震で鉄道網が壊滅的な被害に遭い、何日も歩かなくてはならない場合。火災が懸念されているエリア、耐震基準に満たない建物が多く倒壊が想定されているエリア、津波や洪水が懸念されているエリアなど、通勤経路すべてのハザードマップを確認し、想定被害を把握して、携帯用防災グッズをそろえましょう。
持ち歩く携帯用防災グッズの入れ物は何がおすすめ?
携帯用防災グッズをどのようにして持ち歩くのかもポイントです。自分に合わない入れ物で携帯しても、いざというときに使えなかったり、日々の荷物の中で邪魔になってしまったりすることも考えられます。携帯用防災グッズの入れ物として代表的なものをご紹介します。
・防災ポーチ
おすすめは防災ポーチとして、ポーチに防災グッズを入れて持ち歩く方法です。100均で買える透明や半透明タイプがおすすめです。
 100均で買える半透明タイプのポーチ。23×17×5cmのサイズで、すべての防災グッズが収まった
100均で買える半透明タイプのポーチ。23×17×5cmのサイズで、すべての防災グッズが収まった
メリットとしては中身が見えるので、日頃から自分が何を持ち歩いているか意識することができる点です。ビニール素材なので、多少の水をかぶっても、中のものを守れるでしょう。
マチがあるため、ある程度の量の防災グッズをポーチの中に入れられます。またファスナーが広く開くので、とっさのときにでも中のものを出しやすいのもメリットです。
デメリットとしては、ファスナー部分があるので、完全防水にはならない点でしょう。どうしてもその点が不安であれば、防災ポーチをポリ袋に入れてカバンの中に入れておくという方法はいかがでしょうか。ポリ袋であれば、サッと中のポーチも取り出せるのでさほど手間ではないでしょう。
・防災ボトル
近年SNSなどでも話題になったのが、ウォーターボトルに携帯用防災グッズを入れる防災ボトルです。
 コンパクトに持ち歩ける防災ボトル。写真は500mLサイズで、必要な防災グッズが入りきらず、口が狭いので出し入れしにくく感じた。すべてを入れるには、口の広い1,000mLサイズがおすすめだ
コンパクトに持ち歩ける防災ボトル。写真は500mLサイズで、必要な防災グッズが入りきらず、口が狭いので出し入れしにくく感じた。すべてを入れるには、口の広い1,000mLサイズがおすすめだ
メリットとしては、コンパクトにして持ち歩ける点と、防水性能が高いことです。
しかし、ボトルにぎゅうぎゅうに詰めて作るので、いざというときに中身を取り出しにくいというデメリットがあります。また長距離通勤の人の場合は、防災ボトル1本だけに必要となりそうなもののすべてを入れるのは困難でしょう。
・防災袋(ファスナー付き食品保存袋)
ファスナー付きの食品保存袋を防災袋として利用する方法もあります。
 中身が見えやすい食品保存袋
中身が見えやすい食品保存袋
メリットは防災ポーチと同じく中身が見えやすい点です。ファスナーをしっかり締めておけば防水性能もあります。
デメリットは、いくつかの袋に分けて携帯しなければならないこと。カバンの中でごちゃごちゃになり、いざというときに探すことになるかもしれません。防災ポーチや防災ボトルと比べて、耐久性が低いのも難点です。
日常で持ち歩きたい防災ポーチの中身【必要なものリスト】
続いて、実際に防災ポーチに入れておきたい必要なものをご紹介します。冒頭でご紹介したように、通勤距離や想定される被害内容によって変わってくるので、ご紹介するものを軸に自分用にアレンジして考えてください。

・食料となるもの
防災ポーチには、いざというときに食べられるような食料を入れておきます。長期保存可能なようかんであればエネルギー補給になります。水は、防災ポーチとは別に荷物に入れておきましょう。
・照明となるもの
帰宅時に備える照明は、手を使わなくていい頭につけるヘッドライトタイプがおすすめです。100均で購入することができます。
 ヘッドライトタイプの照明は100均でも購入できる
ヘッドライトタイプの照明は100均でも購入できる
・簡易トイレと90L ゴミ袋
大きな災害のときはそんなことは言ってはいられないという場合もありますが、簡易トイレは、1つは防災ポーチに入れておきたいものです。その際に女性であれば90Lのゴミ袋も一緒に備えておくことをおすすめします。
90Lのゴミ袋の底を切っておき、顔を出してポンチョのようにかぶれば、トイレの際に隠すことができます。このゴミ袋は防寒具にもなるので、穴を開けたものを防災ポーチの中に入れておくといいでしょう。
 オシッコを素早く固め、臭いを包む「携帯ミニトイレ プルプル」(株式会社ケンユー)
オシッコを素早く固め、臭いを包む「携帯ミニトイレ プルプル」(株式会社ケンユー)
 ゴミ袋の底を切っておくと、トイレの際にかぶって体を隠せる
ゴミ袋の底を切っておくと、トイレの際にかぶって体を隠せる
・モバイルバッテリー
災害時、とくに災害発生後に家に帰るまでの時間というのは、情報の入手や連絡手段としてスマートフォンの役割が大きくなってきます。電池切れで使えないということは避けたいので、モバイルバッテリーを持ち歩いておきましょう。
できればソーラー充電もできるモバイルバッテリーがおすすめです。モバイルバッテリーの電池がなくなっても、太陽光で充電できます。
 太陽光で充電できるモバイルバッテリー
太陽光で充電できるモバイルバッテリー
・日頃服用している薬
毎日、薬を服用しなければならない人は、必ず多めに持ち歩いておきましょう。
・小銭を含む現金
災害時には停電になり、キャッシュレス決済が利用できなくなることが往々にして考えられます。また、誰かに連絡をとりたいのに、スマートフォンの電池がなくなってきたというときも、小銭さえ持っていれば公衆電話を見つけたタイミングで電話ができるかもしれません。
現金は日頃のお財布とは別に、防災ポーチの中に入れておきましょう。防水性を高めるためにも、ファスナー付き食品保存袋などに入れておくのがおすすめです。
 小銭と千円札を含め、最低でも2,000円分、通勤距離が長い場合は多めに入れておく
小銭と千円札を含め、最低でも2,000円分、通勤距離が長い場合は多めに入れておく
・家族の電話番号
家族の電話番号を覚えていないと、スマートフォンの電池が切れたら連絡をとれなくなります。覚えている人でも災害時には混乱して思い出せないかもしれません。紙に書いたものを防災ポーチに入れておきましょう。
・メモと油性ペン
スマートフォンが使えなくなり、途中で何かをメモする必要が出てきたり、家族を探すために避難所に書き置きしたりすることも考えられます。数枚のメモと、水に濡れても消えないように油性のペンを入れておくと安心です。
・雨具
最近はコンパクトな雨具もあります。雨に濡れると体力が奪われてしまうので、雨具は必須。両手をフリーにするためにも、レインコートがおすすめです。
・マスク
状況によっては倒壊した建物のホコリや、火災の煙が広がるなど、過酷な状況も考えられます。可能な限り性能がいいマスクを入れておくと安心です。
・除菌ウェットティッシュ
衛生面を考えて、除菌タイプのウェットティッシュも防災ポーチに入れておきましょう。
・絆創膏類
スペースがあれば絆創膏類も入っていると安心です。
・小型ラジオ
スマートフォンが使えない状況として、電池切れとともに、通信の混雑や基地局が倒壊したというような場合もあります。その際に携帯用の小型ラジオがあれば、情報を入手することができます。意外とコンパクトで軽いので、防災ポーチに入れておくと安心です。
 ポケットサイズで軽い、携帯用の小型ラジオ
ポケットサイズで軽い、携帯用の小型ラジオ
・防災アプリ
グッズではないですが、災害用アプリもいざというときに役立ちます。普段使っているスマートフォンにダウンロードしておきましょう。災害時、使い方に困らないよう、操作方法を把握しておくことも大切です。おすすめのアプリについて、詳しくは連載第3回でご紹介します。
持ち歩く携帯用防災グッズは定期的に点検しよう
持ち歩く携帯用防災グッズは1度そろえて終わりではありません。半年から1年に1度は必ず点検をしましょう。
ライトやモバイルバッテリーが正常に動くかどうか。入れている食料品が賞味期限切れになっていないかなどのチェックとともに、何が自分には必要かを定期的に見直すことで、より自分に必要なものが入った防災グッズをそろえられるからです。
いざというときに必ず役に立つ携帯用防災グッズ。災害はいつやってくるか誰もわかりませんので、この記事をご覧いただいたのであれば、ぜひ今日から自分に必要なものをそろえてください。
※記事の情報は2025年2月18日時点のものです。
-

【PROFILE】
矢野きくの(やの・きくの)
家事アドバイザー・防災士・食育指導士・節約アドバイザー
効率化を考えた家事術、暮らしの中での防災などを中心に、テレビ、講演、コラム連載などで活動。働く人向けの時短家事術、シニア層への家事改革などをアドバイス。「防災士」の資格を持ち家庭での備え、「食育指導士」の資格も持ち、食品ロス削減をテーマにした講演も定評がある。100円ショップや業務用スーパーでのお得な買い物術の紹介や、便利グッズの開発にも携わる。
【テレビ出演】あさイチ、ニュースウオッチ9(NHK)/情報ライブ ミヤネ屋(日本テレビ)/ゴゴスマ~GOGO!Smile!~、Nスタ(TBSテレビ) 他。【連載実績】HONDA・東芝・イオン等企業のオウンドメディアや、日経新聞・時事通信 他。【著書】「幸せな時間とお金を生み出す! シンプルライフの節約リスト」(講談社) 他。
公式サイト https://yanokikuno.jp/
RELATED ARTICLESこの記事の関連記事
-

- オフィスに備えたい防災グッズ|本当に必要な備蓄品リスト、置き場所をご紹介 防災士:矢野きくの
-

- 町の人と共につくる「海岸線の美術館」。宮城・雄勝町の防潮堤を資産に変える 海岸線の美術館 館長 髙橋窓太郎さん 壁画制作アーティスト 安井鷹之介さん〈インタビュー〉
-

- モバイルツールをスマートに持ち運ぶポーチ 菅 未里